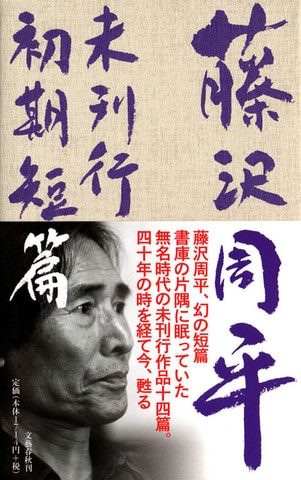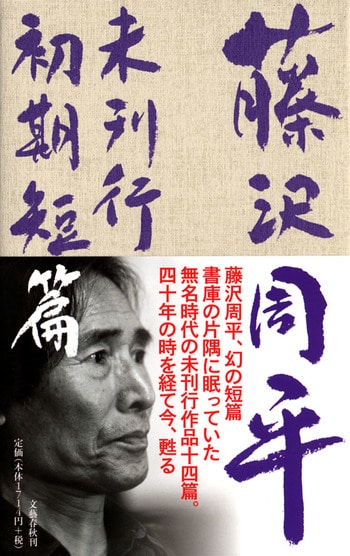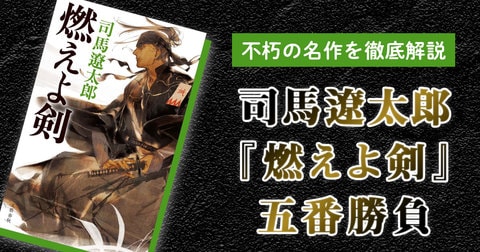本の半ば、「木曾の旅人」を読み終えたあたりで涙があふれてきて、あわてて本を伏せた。
物語に涙したのではない。この短篇に込められている〈祈り〉が見えてしまったような気がして、胸を突かれたのだ。この短篇を書いていた時期、藤沢周平の妻は病に冒され、生まれて間もない娘を残して、死へと滑り落ち始めていた。そういう状況の中で、こういう短篇を書いていたのかと思ったとき、その結末に、彼の祈りが見えてしまった気がしたのだった。
その瞬間、解説を先に読むべきではなかったな、という思いが頭に浮かんだ。本来私は、こういう風に、作家の事情や心情を忖度しながら作品を読むのは好きではない。作品は、世に出たときに、作家との間にある臍の緒を断ち切っている。少なくとも私は、拙著を読みながら、私がどういう状況に在って、こういう物語を書いたのかなんて、考えて欲しいとは思わない。
そんな考えがひらめいた後、いや、この本に限っては、解説を先に読むのが正しい読み方なのかもしれない、という思いが、ゆっくりと心に広がってきた。
この本は、藤沢周平自身が選んだ短篇集ではない。彼の死後、発見された未刊行の短篇――それも、「溟(くら)い海」で本格的に文壇デビューをする八年から九年前に書かれた短篇――を編んだ本なのである。私のような熱狂的な藤沢周平ファンがこの本に出会ってしまったら、どうしても、「彼がいかにして、あのような作品を書くに至ったか」を、本の中に探らずにはいられない。そういう読者のために世に出てくれた本なのだとさえ、言えそうな本なのだ。
実際、本書を読み進むと、否応なく、彼が「藤沢周平に成って行く」過程が心に迫ってくる。藤沢ファンであれば、それを感じずにはいられない本なのである。
それにしても、この時期、藤沢周平は、なんと多彩な試みをしていたことか。隠れキリシタン物もあれば、驚くなかれ、古代エジプトを舞台にした短篇さえあるのだ。書いて、書いて、書いて、己の中にある語り部の才が鋭く震えながら発動する、天性に繋がるその一点を探しながら書き続けていたことが、唸る風のように書面から立ち上がってくる。
印象的なのは、その文章の荒々しさだ。この本に収められている短篇には、後年の、あの簡潔だが、まろみのある文体は、まだ見ることができない。読んでいると、鬱屈するものを胸に抱えた若者が、ひたすら鑿を木に打ちつけ、木っ端を散らして木を穿ち続けるのを見ているような気がしてくる。
最初の二篇(なんと隠れキリシタン物!)など、藤沢周平がこういう物を書いていたのか、と驚いてしまうほど、文章も展開も荒いし、斬り合いの場面にも、藤沢周平ならではの静かで冴えたリアリティはない。
けれど、「木地師宗吉」には、ああ、これは藤沢周平だ、と思われる何かが濃厚に立ち上がってくる。力まかせに打ち付けられていた鑿が、打ち付ける、その繰り返しの動きの中で、次第に打つべき線を捉え、余計な木っ端を散らす頻度が減っていく。そして、「佐賀屋喜七」に至っては、これを書いているのは、もはや、まごうことなく「藤沢周平」だと感じられるのである。
この短篇集を読んでいると、荒い夜風になぶられて飛び去る雲の合間から時折現れる月のように、後年の藤沢周平の、文体や人の描き方、風景描写、場面展開などが、ふいに冴えた光を放つのを見るという不思議な経験をすることになる。
読みながら、これは怖い本だと思った。こんな風に、作家が成長していった過程が、まざまざと見えてしまう本は、そうないだろう。作家の仕事は、自分が成長していく(あるいは成長できない)過程を、ひとつひとつ人前に晒していく仕事ではあるけれど、それでも、自分の死後、若書きが人目に晒されるのは、私なら真っ平ごめんである。だから、この小文をお引き受けするかどうか、正直なところ、かなり迷った。
けれど、『未刊行初期短篇』を読み終えたとき、そういう感想とは全く別の思いが、勃然と心に浮かんできたのである。それは、藤沢周平とは、なんとうつくしい人であろうか、という思いだった。
前半までは、しばしば頭に浮かんできた、ままならぬ人生に苦しみながら書き続けている若者のイメージは、読み終えた時には遠く消え去って、その向こうに、筆を手に、ひたすらに書き続けて生涯を終えた作家の後姿が見えてきたのだ。そして、その姿は、私には、たとえようもなく、うつくしく見えた。
一人の作家の「序章」として読まれ、遥か遠くまで、ひたすらに道を歩んでいった人の後姿を見せる。本書は、そういう本である。