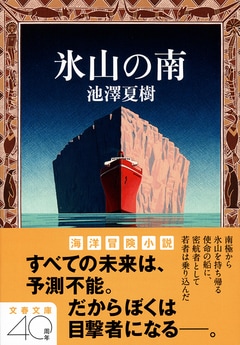そもそも、このタイトルもなんだか謎めいている。たぶん、サリンジャーの『ザ・キャッチャー・イン・ザ・ライ』、つまり「ライ麦畑の捕手」を意識して、こちらは本当に野球のバットを持ち歩いている男たちの話だよ、とでも言おうとしているのだろうか。よくわからない。しかし、なかなか決まっている。小説の構成も短い章を連ね、さらにそれぞれの章は短く感傷にひたらないきびきびしたセンテンスから織り成され、とぼけているようで洒落た感じがある。
一方、本書に納められたもう一編、「つぎの著者につづく」は、はるかに手ごたえがある高度にメタフィクション的な実験小説だ。語り手の「私」は、ある批評家にR氏なる人物との類似性を指摘されるのだが、「私」はR氏の書いたものを読んだことがない。そもそもこのR氏は、生前、一つも著作を発表したことがなく、死後、部屋から発見された草稿が出版されるようになったという経緯がある謎めいた存在で、その点では、一生自分の作品を人に見せることなく「非現実の王国」を作り上げて死んだアメリカのヘンリー・ダーガーを思わせる。はたして、このRという作家は実在したのだろうか?
「私」は、カフカがかつて住んだことがあるプラハの錬金術師小路の古書店まで探索し、Rという作家を追い求める。この作品には、カフカ、トーマス・マン、ボルヘス、ウンベルト・エーコなどの作品への言及が縦横無尽に張りめぐらされ、特に「小国の国家予算規模の値札」がついた稀覯(きこう)本が書棚に並ぶプラハの古書店での書物談義あたりから、読者は渦を巻くような書物の連鎖に引き込まれ、目がくらむ思いをすることになる。
作品の表題の「つぎの著者につづく」とは、R氏の最晩年の著作のタイトルだという設定だが、もちろん、円城塔にとっては「前の作家を受け継ぐ」という意味でもあるのだろう。おそらく、ここで作者の意識にあるのは、文学が模倣され、伝統の中で受け継がれていくとはどういうことか、類似の中からどのように新しい独創性が生まれ得るのか、という問題ではないだろうか。
これほど豊かな才能をもった若い書き手が、カート・ヴォネガットや安部公房のように、現実にわたりあうだけのタフさとヴィジョンをこれから身につけたら、そしてボルヘスのブッキッシュな機知とスタニスワフ・レムの科学的思考を融合させることができたら、何か途方もないものを創り出すことができるに違いない。