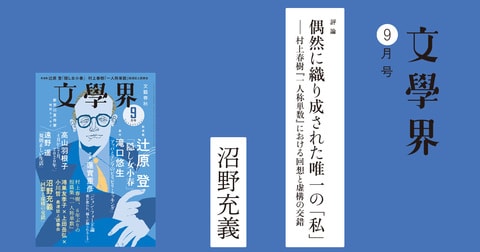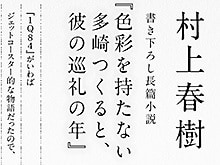それは空前の、そして小林秀雄じゃないが絶後と言ってしまってもいい光景だった。
なにしろ一人の存命の作家(しかもまだ五〇代だ)について、世界の一六もの国・地域から異なる言語の翻訳者らが集まり、話を交わしているのだ。まして、その作家というのが、英米文学でも仏文でも独文でも露文でも中国文学でもない、日本の現代文学の小説家だっていうんだから。
今年三月下旬に東京、神戸、札幌で開かれた国際シンポジウム「春樹をめぐる冒険――世界は村上文学をどう読むか」は、たぶん長い時を隔てて振り返ったとき、今の時点で思っている以上に、ほとんど稀有の出来事として語られるんじゃなかろうか。
東京プログラムの共催者の一員としては不穏当かもしれないが、だいたい国際化とか、国際交流とかいう言葉を掲げた物事は、多くがきれいごとというか包装紙みたいなもので、たいした中身は期待できないというのが世間の通り相場だろう(国際交流基金のみなさん、ごめんなさい)。誰でも海外に行こうと思えば行ける時代、難しい言葉を並べるより自分で実際に体を運び、具体的に行動したり考えたりしたほうが早いっていうのは当然の話だから。
正直に言うと、筆者もそう思っていた。
ところが、このシンポジウムで目の前に展開されたものは、そういう怠惰な「国際化(交流)慣れ」を吹き飛ばす劇的な瞬間の連続だった、大げさでなく。まずは基調講演とパネルディスカッションなどが行われた初日の東大駒場キャンパス。九〇〇番教室といういかにも由緒ありそうな大講堂は、開会前から、抽選で席を確保した約六〇〇人の聴衆の熱気で埋めつくされた。
まあ、たしかに聴衆のある部分は、いわゆる「ファン」で占められていたんだろう。しかし、銘記しておきたいのは、この場に主役たるべき「村上春樹」の姿はなく、かつまた、村上氏の不参加は事前に周知されていたという事実である。にもかかわらず村上氏のことを何でもいいからもっとよく知りたい、という願望が、では、会場の熱気の理由だったのか。それも皆無じゃないだろうけれど、その場に身を置いた者としていえるのは、このシンポジウム会場を満たしていた、ある、もっとずっと真摯な空気の存在だ。独断でいうなら、この空気は、聴衆一人一人が自らの生きる「この時代」の輪郭をより深くつかもうとする欲求の真摯さから成り立っていた。