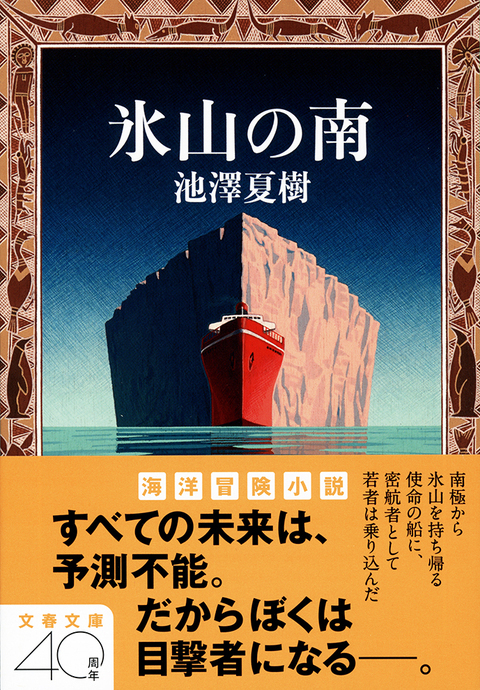もう一つ、『氷山の南』の小説空間の「ユートピア性」を支えているのは、言語である。これは確かに日本語で書かれた小説だが、登場人物たちはいったい何語で会話をしているのだろうか。考えてみればすぐに分かるように、日本育ちのジンを含め、ここでは登場人物のおそらく大部分が英語で自由に会話をしている。つまり、この小説はあたかも英語からの翻訳であるかのように書かれているのだ。これはオリジナルなき翻訳と呼ぶべきものかもしれない。翻訳こそは現代の世界文学の原動力となっているものであり、池澤夏樹自身すぐれた翻訳家であると同時に、翻訳による新たな『世界文学全集』(河出書房新社)の編集という途方もない仕事を軽々とこなす希有の「世界文学者」である。その彼がここでは、文体によってもその「世界文学の精神」を実践しているように見える。実際、『氷山の南』の文体は、以前のどの長編の場合にもまして、簡潔で、きびきびして、明快である。『氷山の南』は、若者を主人公とした冒険小説であり、また新聞に連載された小説でもあるといったジャンル上の要請が影響していることは確かだろうが、それにしてもこの日本語は鮮やかに独自のものだ。現代日本の純文学を代表する別傾向の作家たちの、粘り強く晦渋な文体と比較すれば、同じ言語かと疑問に思えるほど違っていることがわかるだろう。
このような文体は、作家にとって単に文章技巧の問題ではなく、むしろ思想につながるものではないだろうか。つまり思想としての文体、ということだ。『氷山の南』の場合、思想の問題は、氷山の利用をめぐって問われることになる。氷山の利用は、水不足に苦しむ人々を救うものであるかも知れないが、自然を人間の都合によって破壊するものでもある。これをどう考えたらいいのだろうか。これは現在、人類が直面しているその他あらゆる環境問題にも共通するジレンマではないか? 実際、小説には氷を崇め、無益な欲望を抑えることの必要を唱える「アイシスト」という信者たちが登場し、氷山曳航計画を阻止しようとエレガントな策動をしかけてくる。それを知ったジンの心も揺れるが、彼はむしろ心の混乱を重要なものとして受け入れたうえで、未来を探ろうとする。それは、開発を一定程度必要としながらも、環境と自然を守ることも可能にする新たなバランスの模索になるだろう。そして、そういった倫理的志向性を支えているのが、まさに簡潔で明晰な文体なのではないか。
三月十一日の大震災と原発事故以降、私たちはともすれば絶望に駆られ、バランスを失いがちになった。しかし、『氷山の南』が教えてくれるのは、何か大事なものを守ろうとする私たちの戦いにおいて、勝負はすぐに完勝や完敗で終わるわけではなく、ジンが最後にアイシズムの教祖宛の手紙に書くとおり「五分五分」のまま続けていかなければならないということではないだろうか。「未来というのはいつだって混乱の向こう側にあるものでしょうから」という、結びの言葉はすがすがしく、力強いメッセージになっている。