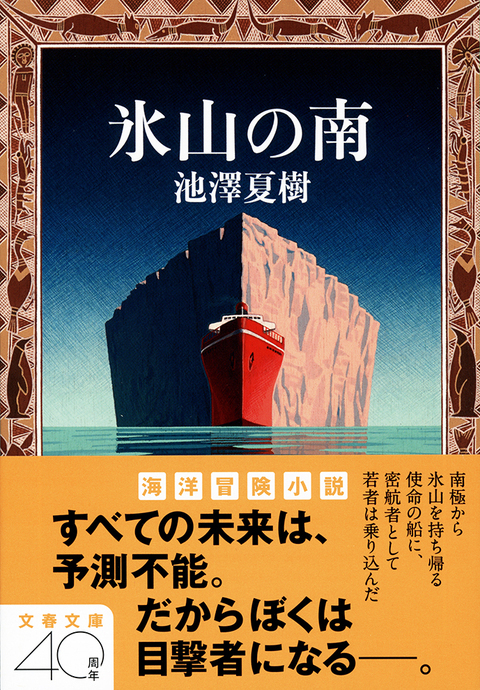この物語の成功の鍵となったのは、「密航者」として発見されたジンが、正式に船に乗り組むことを認められる代わりに与えられた二つの仕事の絶妙の組み合わせである。その一つは、厨房で働き、食事の準備を手伝うこと。やがて彼は、粉からパンを焼く技術に習熟し、それまで不味い冷凍パンで我慢していた乗組員たちにとって、なくてはならない存在になっていく。もっとも最初のうちは、料理書に書いてある通りの分量、時間、温度をまもってやっているつもりでも、なかなかうまく行かない。しかし、試行錯誤を重ねながら、作り方を覚えて行くのは「知らない町で迷うようなものだ」という。「こねる時間を少し増やし、寝かせる時間を減らし、発酵の具合を見て、焼き上げる温度を五度だけ下げ、時間を三分増す」。こうしてジンは美味しいパンの焼き方を覚えていくのだが、その際も描写はこのように具体的できびきびしていて、正確で、曖昧なコツや言葉で説明できない名人芸などといった説明に逃げることはない。池澤夏樹は、料理をしたり、ものを組み立てたりする作業の具体的な手順を描く際も、決して手を抜かないのだ。それでいて彼が料理を描くと、実に美味しそうだ。考えてみると、これはパンの焼き方であるだけでなく、作家の小説の書き方にも通じるものなのかもしれない、という気がしてくる。
ジンに与えられたもう一つの仕事は船内のオフィスに勤め、「パブリシティ」を担当すること、具体的に言えば、船内新聞を編集することだった。彼は同じ船に乗り合わせた様々な人たちに毎日のようにインタビューして回り、それを興味深い記事にまとめていく。その結果、読者の前に立ち現れるのは、じつに様々な生い立ちを持った人々が織り成す多民族の光景である。専門技術者集団を束ねる総司令部の役割を果たし、ドクター・ドラゴンの異名をとる、こわもての中年女性。オキアミを研究する半分中国系のアイリーン。ケニア出身の万能エンジニア、ワンジジ――といった具合だ。これほど多彩な人々の異なった経歴や出自を描くためには、十九世紀リアリズム小説だったら神の全知の視点が必要なところだが、この小説ではジンが「新聞記者」の視点から、自然に世界の多彩さを引き出していく。
「パン」が人間の生命を肉体的に維持するために必要な食べ物であって、胃袋に関わるものであるとすれば、それに対して「新聞」は世界の多様な情報を手に入れるためのメディアであって、頭に関わるものだろう。どちらも大事なものだが、人間は胃袋だけでも、あるいは頭だけでも生きてはいけないし、「パン」か「新聞」のどちらかだけだったら、世界は単純でつまらないものになってしまうだろう。その両方を主人公が兼ね備えることによって、小説は生きる手ごたえと世界の多様さの両方を取り込むことに成功した。
実際、この小説に登場する人々の民族的な多様さは驚くべきものだ。船長はパパディアマントープロスというギリシャ人。ジンの友達になるのは、絵を描くアボリジニの少年。船員にはパキスタン、フィリピン出身のムスリムが多く、彼らの祈りのための場もちゃんと設けられている。そして「アイシズム」と呼ばれる謎めいた教団の教祖は、フィンランド人のタイナ・ライティネン。ヴォイチェフ・ヴァイダという、ロマンティックでいささか人騒がせなポーランドの詩人まで登場する。主人公のジンもまた、半分はアイヌの血をひき、ムックリの演奏が上手である。
この国際的なセッティングは、いかにもポスト・エスニック時代の文学に相応しい現代的なものだが、私にはなんだか懐かしいものにも思えた。というのは私がかつてよく読んだり訳したりした、旧ソ連時代のインターナショナリズムの気風に満ちたSFの類は、たいていこういった国際的な人的構成を強調し、それが一種のユートピア空間を作っていたからだ。例えば、ポーランドのスタニスワフ・レムによるSF作家としてのデビュー作『金星応答なし』(一九五一年)は八人の「宇宙飛行士たち」がロケットに乗り組んで、金星を探検するという物語だが、その乗組員たちとは――インド人の数学者、ロシア人の天文学者、ポーランド人の技師、アメリカの黒人の血を引くソ連育ちのパイロット、等々といった顔ぶれである。いい意味での国際主義と、困難を克服して未来を切り拓こうとする姿勢があいまって、独特の魅力となっているが、池澤夏樹の小説は、ある意味では共産主義のユートピア的実験が頓挫した後、いったん不可能になってしまったこの種のユートピアを、小説的想像力によって再創造しようとする楽しくも野心的な試みだと言えるだろう。