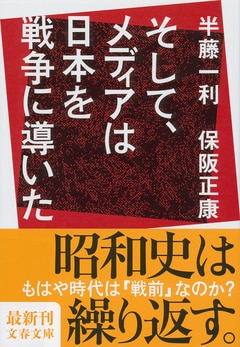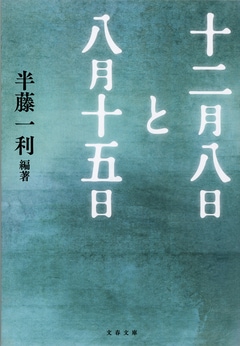いきなり突拍子もないことから書くが、明治三十八年(一九〇五年)九月、アメリカの軍港ポーツマスでの講和会議によって日露戦争は終結した。このとき、日本帝国の“勝利”という形でまずは目出度く国際世論では認められたが、その実は、海軍はともかく、陸軍は戦力を消耗しきってこれ以上の継戦は望めない“惨勝”という状況での、やむなき講和であったのである。この事実からはじめなければならない。
それから二年後の明治四十年四月に、山県有朋を軸として日本の指導層は「帝国国防方針」(国防方針・所要兵力・用兵綱領の三つより成る)をまとめ、御前会議を経て決定した。それは、日本帝国は満洲・韓国における利益線擁護を国家発展のための不可欠の大方針とし、そのためには「我国権ヲ侵害セムトスル国ニ対シ、少クモ東亜ニ在リテハ攻勢ヲ取リ得ル如クヲ要ス」と攻勢的国防論を主眼とするものとなった。“惨勝”であったのに、なぜか国家方針の舵を大国主義にきったのである。
そのため国防方針としては、想定敵国を陸軍は帝政ロシアとし(つまりその復讐戦を恐れ)、海軍は陸軍と共通の仮想敵国を設定することを拒否、あえてアメリカを第一の仮想敵国とした。そして所要兵力は、陸軍二十五個師団(戦時五十個師団)、海軍は新鋭の八・八艦隊プラス旧型巡洋戦艦八を基幹とした。ともに日露戦争開始時の二倍の大兵力である。それが果たして可能なのかを考える必要はなく、ともかく大兵力建設を目標にした。
いったい本書のおわりに、何を言いたいのかと思われる方も多いであろうが、要はこの大それた戦略思想が昭和まで陸海軍をひきずってきた、ということをとりあえず指摘しておきたいのである。そして、このときを第一回として、近代日本の国防問題は、ときの政府に関与させない形で、こうした軍備拡張の実現に努力する義務だけを政府に課し、ずっと策定されていくことになった。わかりやすくいえば、資本と労働、技術といった総力をあげて強い国をつくろうとしたのである。
さて、以上の簡略な説明でおわかりのように、昭和史探偵として、いくつもの歴史的事実をさぐってきたわたくしの念頭には、いつも仮想敵国のこの二つの国のことがあった。それでも、アメリカのほうは、ちょっぴり英語が読めるので翻訳ものだけに頼ることはなく、少しはアメリカという国のかたちや軍の戦略戦術や国民がどんなものか理解を深めることができた。が、言葉が珍粉漢粉(ちんぷんかんぷん)の上に、大正六年(一九一七年)の革命で帝政が倒れ、新しくなったソビエト連邦という複雑な国家となったもういっぽうのほうは、国家や人民についての認識を断片的にももつことができないでいた。
たとえば『ノモンハンの夏』という本をわたくしは書いている。そのとき、スターリンは、兵卒あがりの叩き上げの将軍ジューコフ中将をモスクワに呼び、ただちに戦場に赴くよう厳命する。この呼び出しがかかったとき、ジューコフは、「ああ、自分もついに“人民の敵”にされるのだな」と覚悟を決めたというのである。そんな事実をちらりと知ったため、「有能との定評あるゆえ、かえってスターリンによっていつか粛清されるのではないか、とまわりのものたちからも思われている」と、確かにわたくしはジューコフについて書いているが、正直にいってそれほど確信はなかった。ところが事実は、もっと深刻であったようなのである。
このとき、スターリンのいわゆる「大テロル」の嵐が吹き荒れていて、トロツキー派ファシストとして多くの将校たちがつぎつぎに逮捕・拘禁されている真っ最中であったというのである。その数およそ三万人。しかも将官クラスの高級軍人たちは多くが銃殺され、また佐官クラスの過半数のものが「ベリヤの肉挽き器」、すなわち拷問にかけられて、荒唐無稽な自白を強いられていた。ジューコフはそうした犠牲者の何人とも親しく交流していた。それゆえにジューコフはすでに呼び出しのあったその日にはすでに身辺整理を済ませ、収監の日を待ち受けているときであった、というではないか。
しかも、その直前のこと、スターリンは内戦時代からの僚友である国防人民委員ヴォロシーロフ大将に尋ねている。
「いかなる国のどんな攻撃にも動じない赤軍を編制するのに、どのくらいかかるか」
ヴォロシーロフは正直に答えた。
「まず、あと三、四年はかかります」
スターリンはさすがにたじろいだ。ヒトラーのポーランド併合を目指すという東方への野望が、このときには明らかになっていたからである。つまり、スターリンにとっては最高に危機的状況にあるときに、アジアでノモンハン事件が勃発した。そこで有能の評のあるジューコフを急ぎモスクワに呼んだという経緯があったという。ノモンハンの戦場でジューコフが日本軍撃破のために死にもの狂いになったのは当然のこと、何の不思議もないことであった。『ノモンハンの夏』はその意味でちょっと書き足りないところがあったと、いまになって思っている。
それにつけても、当時の陸軍中央部や外務省にはいわゆるソ連通、ソ連屋と称する人がいっぱいいたのであろうに、ジューコフの総指揮官着任が何を意味するのか、まったく考えてみようとはしなかったのはどうしてなのか。
当時の日本にはソ連に関する正しい情報が入ってはこなかったのか。いや、そんなことはあるまい。明治末いらいの第一の仮想敵国なのである。むしろ情報の量があまりにありすぎて、結局はその小部分しか利用しない、あるいはできない。しかもその利用の選択はソ連通と自負する人の偏見、またはこうであってほしいという希望的観測にもとづいていた、と考えたほうが正しいのではないだろうか。であるから、その予想はつねに外れる。ノモンハン事件でもそうであったし、事件が終わる直前の独ソ不可侵条約もまさにそれで、「複雑怪奇」といって内閣は辞職するほかはなかった。さらには終戦直前のソ連軍の満洲侵攻においてをや。参謀次長河辺虎四郎中将が「予の判断は外れたり」と叫んでも、あまりにも遅すぎたのである。
このことは、豈(あに)昔ばなしのみならんやと思っている。いまの日本にもそのまま通じているのではないか。国際情勢の見透しについては、戦前と戦後との違いがそんなにあるとは、とても思えない。あっさりいえば、政治的責任のとり方の問題がいまの指導者(官僚も含めて)にもあって、それは昔とそんなに変わらないからである。要は、ほとんどソ連・ロシアのことを知らないでいるがゆえに、責任のとりようがないのである。いや、昔よりもっとひどくなっているかもしれない。
*
そんなこんなで、ソ連という国が相変わらず俺にはわからないな、と酒席などでぼやいているのであるが、そんなある日、佐藤優さんとの対談の話が文藝春秋の新書編集部からもたらされた。正直にいって、すぐに「来たか半ちゃん待ってたホイ」と乗るほど、わたくしは浅はかではなく、大いに後込むところがあったのである。佐藤さんは文句なしのソ連・ロシア研究の専門家であるし、現場でジカにソ連・ロシアの高官たちとやり合った経験豊富な元外交官である。危険な現場を知りつくしている。わたくしの話など、専門家からみればシロウトもいいところ、世にいう床屋談義にすぎないし、また実務家からみれば何も知らない高みの見物衆の阿呆陀羅経としか聞いてもらえぬだろう。そう思うしか、なかったからである。
でもね、とあとで考え直した。わたくしは根が雑誌編集者育ち。名刺一枚で、高位高官であろうと碩学であろうと、取材の名目のもとに厚かましくもおしかけていって、秘話を聞きだした体験が山ほどある。その雑誌編集者の原点に戻れば、相手が博覧強記の、どこまで知識があるのか底しれない、正体のつかめぬ“怪物”だろうと何程のことやあらんである。で、承諾の返事を新書編集部に送り届けた。
対談は約三時間ずつ五回にわたって行われた。そして本書ができ上がった。一部が「週刊文春」や季刊誌「文藝春秋SPECIAL」、「文藝春秋」に掲載されたりしたので、あるいは読んだ記憶のある読者がおられるかもしれない。が、せっかくの対談ゆえゲラには存分に手をいれることにした。それで雑誌掲載よりも内容的にちょっとはましなものになっているであろうと思い、読者にはご海容を願う次第である。
思い返すと、佐藤さんとの対談をわたくし自身は、終わるのが惜しいくらい大いに楽しんだ。人生の楽しみとは知的力量、実体験豊富な人との出会いにあり、そして話を聞きながら自分も考える、楽しいおしゃべりをすることにあるのである。結果としてかなりロシア人への我が理解が深まったことが有難く、佐藤さんに心から感謝する。そして読者の皆さんにもきっと愉しんでもらえるものと、いまは確信を強めている。
二〇一六年三月一〇日
──七十一年前の東京大空襲でやっとの思いで死ななくてすんだ日
半藤一利
(「おわりに」より)