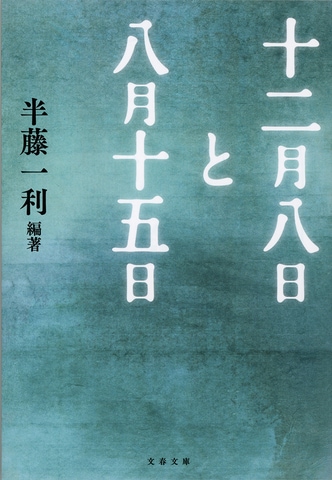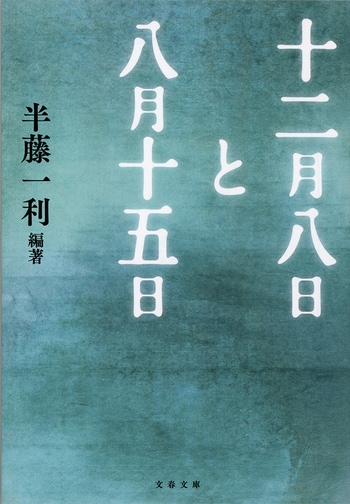いまゲラを読みおえてみて、困惑を隠せない思いでいます。読み返すのもためらわれる過去の拙作と無理矢理に対面させられているような感じなのです。いっぺん世に出た活字は、いくら嫌だからといって本人が勝手に消すことはできない、ということは承知しているものの、やっぱり過去の恥はさっさと消してしまいたいという隠微な欲望が人間にはあるようです。
「はじめに」にも書きましたが、本書は、結局は過去にわたくしが書いた本のいくつかのダイジェストを土台にして、かなり加筆をし、多くの人びとの日記やら回想やらをちりばめてまとめたものであります。もととなった『日本のいちばん長い日』は五十年前、わたくしが三十五歳のときに無我夢中で書いたものです。『聖断』が三十年前、『[真珠湾]の日』が十五年前といずれも老耄した頭にはいったい何を書いたやらと忘れてしまうほどの、年月が経っています。そして《今》の眼でみてみると相当に不満なところもあるし、「なんと拙劣な」と自己批判せねばならぬところもある。といって、流行(はやり)の都合に合わせた“歴史修正”はすべきことではありません。厳然たる“事実”がそこにあるからです。それで、あまり過去の拙作を動かさずに本書をまとめることは、心理的に無残にして無慈悲な作業となりました。
ところが、編集部の児玉藍さんが艶然と微笑んでいうのです。
「ほんとうに知らないことばかり。菊池寛先生のいう“四分の学芸、六分の面白さ”そのものの本になると思います」
その言葉に気をとり直し(いや、だまされて)とにかくまとめることができました。ありがとうございました。
そこでまた、読者の皆さんには、「はじめに」に記したことと同趣旨の言葉をくり返します。原稿の二重売りか、怪しからん、とお叱りをうけることになろうかと思います。それでもう一度、あらためまして低頭してお詫び申しあげる次第です。
本書にも登場しました文芸評論家の河上徹太郎氏は、開戦の当時は「文學界」の編集長をしていました。その雑誌の新年号の「後記」にこう書いています。
「本号の締切間際になって突如開戦となったので、編集部では大分気遣って奔走したが、大体予定の顔触れが揃って新年同人特集号が出来上った。/覚悟はしていたものの、何しろ相手はなうての大物だから、気になるのは当然だ。(以下略)」
これで察しがつきますが、たいていの雑誌は原稿の締切りが一両日に迫っているところで、対米英戦争が寝耳に水ではじまったようなのです。つまり、各雑誌の昭和十七年新年号には怱忙の間にあわただしく書かれたものが載り、じっくり落着いたものは二月号に載った、といっていいと思います。したがって大戦争に直面して日本人は何を思いどう考えたかの長いものは、各雑誌とも二月号になっています。本書の「第一話 開戦の日」の知識人たちの思いの多くは、学術論文ではありませんのでいちいち細かく出所は記しませんでしたが、ほぼ各雑誌新年号と二月号に寄せられたもの、ということになります。
たとえば、「文藝」新年号には「戦いの意志(文化人宣言)」と題して、ずらりと識者が顔をならべております。労を厭わず全員の名を挙げてみます。
斎藤瀏、本多顕彰、亀井勝一郎、張赫宙、浅野晃、保田與重郎、上田広、富沢有為男、石川達三、清水幾太郎、津村秀夫、火野葦平、中河与一、崔承喜、秋山謙蔵、島木健作、伊藤武雄、(詩)丸山薫、(句)水原秋桜子、(絵)中村研一、小磯良平、野間仁根、(歌)齋藤史。
といった具合です。
そのなかのたとえば保田與重郎氏は「文藝春秋」新年号に「攘夷の精神」という力のこもったものを書き、火野葦平氏は「文學界」二月号に「全九州文化協議会」と題する堂々たるの論を発表しておられます。以下同様なので、引用はあまり恣意的にならないよう注意を相応に払いましたが、あるいはまた別の観点からみた“十二月八日”を書くこともできるわけであります。
「第二話 終戦の日」についてはそれこそ汗牛充棟といえるほど資料があります。日記、当時の感想、そして戦後の回想と、こちらはむしろ選ぶに困ります。「はじめに」で紹介した井上ひさし氏他著の本、永六輔氏監修の本の二冊だけでも十分といえば十分なのです。そこでかなり苦心が要りました。ただ、注意しなければいけないことがあります。それは、とわたくしが偉そうにいうよりも、本書にも引きました正宗白鳥氏が昭和二十年十二月二十三日に発表の回想の、“付記”のような一文がいいかと思います。
「与えられた紙数だけの感想であるが、数カ月を隔てた過去の日に於ける感想の記録は、八月十五日当日の実感とおのずから異っているであろう。止むを得ない。この頃頻繁にあらわれる知名人の回顧録、過去の感想談も、眉に唾をつけて見るべきであり聞くべきである」
まったくそのとおりなので、わたくしも本書でときどき疑問を投げかけて書いているのは、歴史好きの悪癖としてうっかり信用しやすいこころがあるとの自戒によるものなのです。たとえばいまも新聞・雑誌・テレビなどで“八月十五日の皇居前”として使われている民衆が土下座して涙にくれている写真があります。あれはじつは前日の十四日の午後の、終戦と承知しているメディアのいわゆるヤラセであるという風評がある。たしかによくみると、向うのほうに写っている何人かの人は見物かたがたのんびり歩いているようにも見えます。本書では、当日たしかに皇居前にいったという人の日記をいくつか見つけました。結果は、その風聞は風聞にあらずあるいは本当かもしれない、というものでした。
いずれにせよ、白鳥先生がいうように「眉に唾をつけて」ということが必要で、歴史を書くことのむつかしさはそこにあることは間違いありません。
なお、本文中の敬称はすべて略しました。
また、引用の日記や回想などの文献は、詔書をのぞき、新かな、新字とし、ときに漢字をひらき句読点をほどこすなど、読みやすくしたことをお断りいたします。歴史を知らない近頃の若い人たちにも読んでもらいたいと思うからです。いまの若い人は作家や作品を気に入っても、その人の作品をさかのぼって探して読むことをしない。書店の店頭でしか本を選ばない。であるから、こちらから差しだして見せてやり、読んでもらうようにすればいい、と内田樹氏の本で教えられ、なるほどと思ったからです。余計なお世話かもしれません。
そうそう、識者たちの年齢は誕生日がくれば満でその年齢になるという数え方で統一いたしました。
二〇一五年四月二十二日
――大正十四年(一九二五)、治安維持法が公布された日
(「おわりに」より)