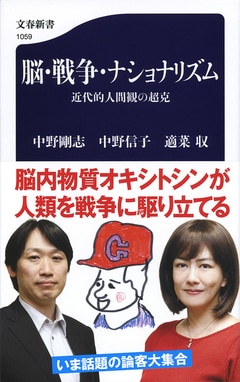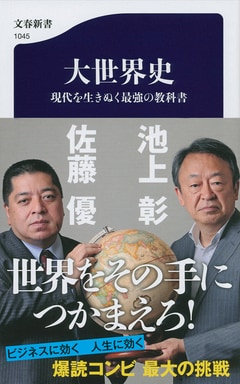首相コールが、各国の取材カメラマンが日本製のカメラばかりを持っているのを見て立腹し、「君たちはなぜドイツ製のカメラを使わないのだ」と言い放ったのもこのころだった。
改革開放によって中国という巨大市場が出現しつつあった当時、ドイツはそのパイをめぐって日本をライバル視する戦略に舵を切っていた。
一九九〇年代前半、当時の駐日ドイツ大使が、あまりに親日的すぎるという理由で更迭されたとするスクープ記事が大手紙に掲載されたこともあった(無論、ドイツ政府はその更迭理由を否定した)。世紀が変わり、二〇〇一年には皇太子殿下を侮辱する記事が、クオリティーペーパーとされる『南ドイツ新聞』の付録雑誌に掲載され、日独関係に冷水を浴びせる事件もあった。
一九九三年、コールは経済界の大代表団を引き連れて北京に乗り込み、空前の規模の投資案件をまとめた。このコール訪中はその後の独中関係の原型となり、シュレーダー政権を経てメルケル政権に至るまでの「ドイツ首脳の北京詣で」の最初のパターンとなった。
このコール訪中は、前年の一九九二年の天皇陛下訪中が刺激になっていた。天安門事件で国際的孤立を深める中国に対し、経済権益の拡大を目指す日本が抜け駆けの急接近を図ったとドイツは判断していた。そうした焦燥感の下、コールはにぎにぎしい大代表団を連れて訪中し、巻き返しを図った。
その後、ドイツ首脳の中国訪問が定例化し、頻繁な首脳間の往来が続く中、日独は急速に疎遠になっていた。
二〇〇〇年代前半のシュレーダー政権時代、あるドイツ外交官が言った。
「ドイツの首相が何度、中国に行っているか数えたことがありますか? その間、ドイツの首相は何度日本に来ましたか?」
そして、この外交官はこう言った。
「これはもう、ジャパン・パッシング(日本素通り)などというものではない。ジャパン・イグノアリング(日本無視)なんだ」
一九七〇、一九八〇年代の自由で開かれた西ドイツ社会を経験し、日独の絆の神話を大切にしている日本人に、一九九〇年代以降の日独間に漂うよそよそしい空気を伝えてもなかなか信じてもらえなかった。