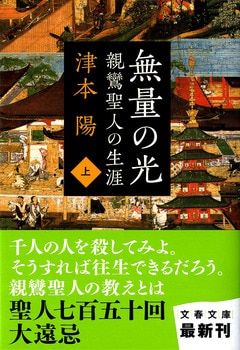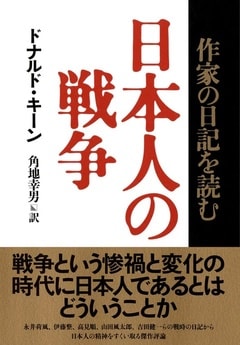――菊池寛賞ご受賞おめでとうございます。今回の受賞は、剣豪小説や歴史小説での長年の御功績と、『八月の砲声――ノモンハンと辻政信』(講談社刊)や『名をこそ惜しめ――硫黄島 魂の記録』で、戦記文学にも幅を広げられたことが評価されていますが、戦記物に取り組まれた動機をお聞かせください。
終戦から六十年経っていますが、日本では戦記については、アメリカによる教育指導などもあって興味が持たれていない。歴史がそこでスーッと切れたようになっている。しかし、あと三十年、五十年経ったら、そこにブランクができるということは無視できないと思ったんです。
――問題意識は現在とつながっているわけですね。
日本は戦争で壊滅してから三十年で世界有数の産業国家になりました。それを成し遂げた日本人のポテンシャリティというか、生きるための意欲というのは、硫黄島で非常な悪条件の中でとにかく戦おうとした人の努力と、実は一体だと思うのです。日本人は島国で暮らしていて互いの連帯は強く、変な方向に走り出したら全員が行くとか、今だったらいろいろ言えますが、当時、日本はかなりいろいろな方面で追い詰められていた。非常にゆがんだ世情の中で皆がそれぞれの状況下で努力をした。その努力の仕方が、日本人の特徴だと思うわけです。
――硫黄島について書かれるきっかけというのは、何かあったのでしょうか。
ペリリュー島(現パラオ共和国)の玉砕(一万人。昭和十九年十一月)を、最初は書くつもりでした。
新陰流の先代のお弟子さんに、ペリリュー島の斬込み隊の指導教官をしていて、島がアメリカ軍に襲われる前にフィリピンに渡り、その後、東京の陸軍大学の教官になった方がおられたんです。ペリリュー島に行く前にはニューギニアのラエで海軍陸戦隊の教官をしていたそうで、私の義兄が大阪高槻の工兵連隊の中隊長でラエにいたので、話が合いましてね。そこで編集者と一緒にペリリュー島の話を聞きに訪ねると、関の孫六なんかを持ち出して、これを使ったんですよなどと言う。しかし、肝心のところになると泣いてしまって、話がとれないんですよ。これはだめだと。
日本一の現役部隊といわれたのは、鹿児島の歩兵第百四十五連隊(硫黄島で玉砕)と水戸の歩兵第二連隊です。その水戸の第二連隊がペリリュー島で玉砕しているんですが、山の上で最後まで三十二人が頑張っていて、昭和二十二年に降りてきた。そのうち四人にはいつでも会えるというので、水戸まで行くことにしたのですが、これから行きますと連絡をすると、今日は頭が痛い、今日は体の具合が悪いなどと言われる。いまだに複雑なものを抱えているのでしょうね。
それで、これは難しいなと思っていたところに、硫黄島協会事務局長の金井さんにお会いしたわけです。金井さんの話は非常に状況把握が的確で臨場感があり、夢中で三時間ノートを取って。それがきっかけです。
――金井さんの他にも、お話を聞かれたわけですか。
玉名山陸戦隊の大曲覚さんや野戦病院の衛生兵だった吉住鉄五郎さん。鉄五郎さんは下町の勇み肌の人が年取ったという感じの人です。硫黄島と横須賀との間の衛生資材の移送をしていて、アメリカ軍との決戦で、最後まで金鵄勲章を貰うつもりだったと言っていますよ。その他にも本文には出てきませんが、広島在住の方も訪ねました。
ペリリュー島は現役兵ばかりですが、硫黄島は、補充兵で三十五、六歳とか四十五、六歳という人も引っ張って行かれた。金井さんの部下にも四十歳ぐらいの兵隊がいて、敵が来ても弾の込め方を知らなかった。恥ずかしそうに笑ったのが今でも忘れられないと言っていました。
でも凄い戦いをしています。アメリカ兵は七千人近くが死んでいる。アメリカの負傷者は二万二千人近くで、そのうち大手術を要する負傷者がものすごく多かった(九〇パーセント)そうです。日本軍は全体で二万一千人がいたというけれど、病死したり爆死したりして、実際は一万七、八千人に減っていたでしょう。戦闘で死んだのは、その内の三割の五千人。残りは、投降しようとして後ろから撃たれたり、嫌われた上官が殺されたり、それが一割ぐらいですね。あと六割は、水が無くて、焦熱地獄で、爆死。つまり手榴弾を使っての自殺です。それらすべてを合わせて、日本軍戦死者は一万九千九百人といわれていますが、島にはまだ一万二千体の遺骨が残っているといいます。だから、今でも霊がいっぱい出る。硫黄島に行ったら幽霊の話ばかりです。
――硫黄島は現在海上自衛隊の基地があるだけで、一般の人は行くことができないそうですが。
幕僚長にお願いしまして、特別に取材の許可はもらえたのですが、いざ行く段になると、イラク戦争で飛行機が出払ってしまって全然ない。途方にくれていたところ、入間の飛行機を配機する係に示現流の本を書いたのが縁で知り合った方がいまして、便宜をはかってくれました。南大東島に行く飛行機を硫黄島に止めてくれたのです。佐官クラスが七、八人同乗していましたが、全員日に焼けて真っ黒でした。
島の中をジープで移動すると、遺骨の臭いを隠すために草の種が蒔かれて、それが樹林みたいになっている。地下壕にも入りましたが、地熱がすごくてとても奥には進めない。同行の若い編集者は頑張って十メートルほど行ったけど、わずか一分ほどなのにシャツはずぶ濡れになっていました。
四階建ての鉄筋の宿舎に泊めてもらい、島の司令や幹部が歓待してくれるのですが、霊とお酒を酌み交わしたとか、夜中に何千人も行進してくる足音が聞こえたとかいう話ばかり。半分感心して、半分呆れて聞いていました。
――硫黄島は東京の南千二百五十キロ、面積二十平方キロの小さな島ですが、太平洋戦争では戦略的に重要な拠点だったわけですね。
平坦な島で、飛行場がありましたから。アメリカの爆撃機は、サイパンから東京に行こうとすると爆弾を二トンしか積めないが、硫黄島からなら六トン積めるというんです。本土爆撃のため、絶対に欲しい島だった。
――昭和十九年五月に栗林忠道中将が着任し、最後には、陸軍一万三千五百人、海軍七千三百人が布陣します。千二百人足らずの島民は東京に疎開させました。
ただし十八歳以上六十歳未満の百五十人弱は、農耕作業要員として残しました。その人たちも玉砕です。
栗林中将は、留守近衛第二師団長で皇居防衛の任に就いていた。部下の見習士官が酒を飲んでボヤを出したため予備に入って待機しているときに東条首相に呼び出されて、第百九師団長兼小笠原兵団長を拝命します。栗林は、アメリカとカナダに足かけ六年間いて、向こうの平和産業はちょっと切り替えたら軍需産業になることをよく知っていた。だから絶対戦ってはだめだという考えでしたが、東条は、そういう反対論を唱える連中をみんな前線に行かせている。死なせてやれと。たいへん非情なやり方です。司令部には父島に本部を置けと唱える者もいましたが、そんなところから指揮はとれないと、栗林は硫黄島に本部を定めました。マリアナ沖海戦で連合艦隊が壊滅した今となっては、一日でも持ちこたえて、アメリカに損害を与えてやろうと、それだけですよ。先の望みなんて何も無かった。それを栗林は腹の中に隠しておいて、戦った。最後に出撃する時はヨボヨボになっていたと言いますね。相当な心労だったんでしょう。
――栗林中将は、地下要塞に立て籠もる作戦だったが、海軍には別の作戦があった。栗林中将が全体の指揮官なのに、海軍が言うことを聞かないということがあったのですか。
軍艦で砲戦するのが海軍の本領ですから、陸上戦闘は苦手なんです。海軍は七千人ぐらいいたけれど、上陸されたら勝ち目はないというので、水際で叩き潰すという水際撃滅作戦を主張して、厚さ一メートル三十センチもあるトーチカを作った。栗林中将は、仕方ないから協力しようと。その代わり鉄筋とセメントを半分くれといった。海軍のトーチカは敵を引き寄せるための目印として、地下に総延長十八キロの複廓陣地を作った。そこで出血を強いて、本土爆撃の日を遅らせようとした。
――バンザイ突撃をするのではなく、消耗戦に引きずりこむ作戦をとったのは、ペリリュー島の戦いから栗林中将が教訓を得たということですね。
ペリリュー島は天然の要害で、アメリカはそれまで百人単位の戦死者だったのが、ペリリュー島で三、四千人が死んで、指揮官を交替せよというぐらい問題になった。水戸の第二連隊が海岸線の珊瑚礁に鍬や鶴嘴で自分が入るタコ壺を掘るのに二十日間かかったという。上に椰子が生えていたでしょ。それが砲撃で吹っ飛んで丸見えになったけれど、その戦死者は五パーセントだったといいます。アメリカ軍は皆死んだと思って上陸してきたが、千八百人の日本兵がタコ壺に入っていて、向こうも千八百人。三昼夜白兵戦を戦って両方とも全滅。向こうもそんなことをやられたら弱いんですよ。
――それで硫黄島でも地下壕を掘ったが、サイパン島が玉砕(昭和十九年七月)して、サイパンからの米機来襲、艦砲射撃の中での作業だったわけですね。
掘るだけで二千人ぐらいが死んだのではないですか。凝灰岩の地質にダイナマイトを入れて爆発させて掘っていく。硫黄島の地下は温度が六十度くらいなのですが、段差をつけた空気穴を開けると二十八、九度になり、それで皆が立て籠もった。本部の地下壕は地下四十メートルぐらいのところにあって、一トン爆弾が落ちても、将棋盤の駒が倒れるぐらいで、なんら影響を受けなかったといいます。
――そして、いよいよ昭和二十年二月、アメリカ海兵隊が三日間艦砲射撃をした後、硫黄島に上陸してくるわけですね。
艦砲射撃は爆撃よりはるかに恐ろしいといいます。
僕も勤労動員先の明石で、二百五十キロの特殊爆弾を直径三十メートルの範囲の防空壕に六発も撃たれたのでその恐ろしさはわかります。B29の第一波八機で工場がやられた。みんなが丘の上に上ると、煙が上がっている、チクショーと。第二波がまた来て、下の方で破裂している。配属将校が顔を真っ青にして走ってきて、こんなところにいたら皆殺しにされる、逃げろと。坂の途中の防空壕は満員で、みんな尻を出している。むりやりもぐりこんだが、第三波十六機が高度一万メートルで来て、それが私たちの防空壕に集中した。ドカンとかバーンではなくて、もうカァン、カンカンカンという音なんです。体は、ガリバーに箱に入れて揺すられる小人のよう、滅茶滅茶ですよ。工場破壊の特殊爆弾だから、六階建ての鉄筋の建物の地下三階まで到達して吹っ飛ぶ。そんな爆弾を五百発、わずか三十分の間に落とされた。
硫黄島は、それを何ヶ月もやられたわけです。しかも八百隻の軍艦の艦砲射撃がある。壕の中の兵は、壁にしがみついて、漏らしてしまった者もいたといいます。気がおかしくなったって不思議じゃありません。
アメリカ軍はそういった艦砲射撃を続け、誰もいなくなったと思って上陸してきた。ところが、殆ど生き残っていた。
――上陸した最初の三日間だけで、アメリカ軍は七千名近い死傷者を出すわけですね。
すごいと思ったのは、木更津基地から三十二機の大特攻隊が来て、硫黄島を包囲している艦船に突入して、空母を轟沈している。あんなに成果を上げた特攻隊は他にないですね。島の塹壕から一万数千の日本兵が出てきて、
万朶(ばんだ)の桜か襟の色
花は吉野に嵐吹く
大和男子(おのこ)と生まれなば
散兵線の花と散れ
と、全島揺るがす大合唱になったそうです。
――アメリカ軍が島の南端の摺鉢山に星条旗を立てる写真はピュリツァー賞を受賞し、アーリントン共同墓地の像になるほど有名ですね。
玉名山の銃眼から見ていた人によると、摺鉢山の旗は夜になると日章旗に変り、朝になると星条旗になったそうです。山の洞窟に隠れていた日本兵が夜陰に紛れて出てきては日章旗に差し替えて、砲撃や爆撃でやられて死ぬ。明るくなると米兵が星条旗に替える。それを四日間繰り返したといいます。あの写真は、日本兵が力尽きてから大きな旗を持ってきて、やらせで撮った。旗を立てた五人の兵士の内、生きて帰ったのは一人。四人はその後の戦闘で死んだといいます。
――島では水の確保が大変だったそうですが。
湧き水は島の西部に井戸が二つ、それだけですよ。この島はもともと何百という雨水を貯めるタンクに頼っていたんですが、すべて爆撃で壊された。壊れた水タンクのかけらみたいなのに水がたまっているでしょ。それを飲みに行くと米兵が機関銃を構えて待っている。やっと水に近づくと猫いらずの黄燐弾をぶちこまれている、腐乱死体も入っている。それをすくって飲むと、カリッと口の中にね、ふやけた死体から離れた小骨があたるというんですよ。しかし、あの水のおいしさは一生忘れられないと、大曲さんが言っていました。
――硫黄島の取材から帰られた日に、夢をごらんになったそうですが。
非常にリアルな夢でした。部下を率いながら自ら速射砲を操り上陸する敵をなぎ倒し、死体から武器を奪い、銃弾降り注ぐ中、弾尽きるまで戦うのです。全身にみなぎるのはただ闘争本能のみ。恐怖も、国家への怨念もなく、ただ敵には絶対に殺されたくないという強い願望だけです。洞穴の中、近づいてくる敵の息遣いも生々しく、最後は自ら顎の下に銃をあて、足で引き金を引いた。そこで目覚めました。一人で水陸両用戦車を三十台近く破壊し感状を受けた中村少尉という人がいるんですが、彼の死に際として小説に書きました。夢に見たまま弾帯を垂らした拳銃と書いたら、武器に詳しい方からそんな形状の拳銃はありえない、機関銃でしょうとの指摘を受けた。念のため義兄に聞くと、そういう拳銃を見たことがあると言う。こういうことを話すと、何かのメッセージでは、という人もいるんですよ。私はそうも思わないんですけど……。でも島から帰ってくるとき左の肩が重かったんですが、書いた後は肩が軽くなっていました。
――「勇将の下に弱卒なし、という諺は、真理であった」と本書にあります。
しっかりした少尉でも、やはり不安でしようがなくなることがある。そういうときに、しっかりした中尉がいると頼れるから、揺れないんです。で、中尉は大尉に頼り、大尉は少佐に頼る。少佐は大佐が出てきたら頼る。そういう親にすがる子供みたいな気持ちはあったようです。西中佐はたいへん勇敢だけど厳しい人で、戦車への肉薄攻撃なんか他の海軍はやったことがない。エライところにきたもんだと、大曲少尉たちはびっくりしたそうです。
――西竹一中佐(昭和七年のロサンゼルス・オリンピック大会の馬術大障害飛越競技で金メダル)の最期を大曲さんは見ているわけですね。
西戦車連隊は、東条によって満州から硫黄島に行かされた。どうせ死ぬと思っていたからか、西連隊はものすごい戦いをしますね。栗林中将も騎兵で西さんも騎兵、気が合っていた。死ぬ時は一緒と思って合流しようとしたが、途中に谷があってたどり着けなかった。大曲さんは、西さんは最後まで生きたかったのだと手記に書いていますね。何とかして生きたかったが、追い詰められて戦車砲に撃ちまくられ、自殺していたと書いています。
――そのように将兵が勇敢に戦う他方、軍中枢が頽廃していたことを、長年書かれてきた信長などの戦国武将の判断力・統率力の優秀さなどと比較されていますが。
右の端と左の端ぐらいの違いがありますね。中枢の連中は何も世間を知らないからです。大学を卒業して、陸軍は参謀本部、海軍は軍令部に入った秀才でしょ。専門の軍人は階級でしか人間の値打ちを考えない。明治以降、人並みの智恵が出たのは、松下村塾の末端だった山県有朋や桂太郎まで。彼らが維新の元勲になったでしょう。戦う時は先ず補給ラインを考え、停戦の調停をどの国に頼むかと、それを決めてからでないと開戦しなかった。下積みの生活をしてきたから世間というものを知っているわけです。その後は、兵棋演習といって将棋の駒を動かすようなことをやって、勝ったとか負けたとか。兵隊は自給自足だといって、輜重(しちょう)なんかを一番ばかにしていた。新兵器の情報を海外の大使館が流してきても、大部隊を作りたいから肉弾で行けと。日露戦争は肉弾で戦って世界最強といわれ、それから三十年ぐらいしか経っていないから信仰として残っていた。日本は日露戦争のときにも支那の軍閥に兵器を売っているし、第一次大戦ではヨーロッパにまで駆逐艦を売っていて、兵器の先進国だった時期もあった。だんだん辻政信みたいな出世欲の塊みたいなのが出てきて、事件を起こしては、一銭五厘で兵隊を集めて、武器の足りないところは肉弾で補えと。実際肉弾で夜襲に来られたら、最新の武器でも弱いんですよ。そういう夜襲の力をただで使おうとした。積極的は積極的だが、国民の人権なんかはまったく無視したやり方です。
――題名の『名をこそ惜しめ』は、『保元物語』の「命な惜しみそ、名を惜しめ」から取られたのでしょうか。
「戦陣訓の歌」というのがあるのです。
日本男児と生まれ来て
戦さの場(にわ)に立つからは
名をこそ惜しめ武士(つわもの)よ
散るべき時に清く散り
御(み)国に薫れ桜花
東条が、「生きて虜囚の辱を受けず」という『戦陣訓』を作ったときにできた歌です。この『戦陣訓』で日本の兵隊がどれだけ死んだかわからない。
――本書で、将兵の一人一人の名前が記されているのは、顕彰という意味もあるのでしょうか。
これだけの戦いの手記を残された方々ですから、実名を載せるべきだと思ったのです。鎮魂ですね。今回の執筆にあたり、非常に生き生きと書かれた多くの手記に感嘆しました。大本営の記録などではなく、こうして実際に戦った人々の言葉にこそ真実があると思った。野呂邦暢氏も書いていますが、戦いの中にこそ、その民族の本質が出るのです。戦場で弾が飛んでくると、普通は怖くなって砲弾の跡の穴とかに隠れるでしょう。ところが、日本兵は銃とか大砲の音を聞くと途端に血がバーッと頭に上って、無意識で飛び出して突っ込むそうです。それが大和魂というのではないか。そういった日本人の遺伝子が、戦後の日本の活力にもつながってきていたんじゃないかと思うのです。
最近、敵が攻めてきたらどうするかと日本の若い連中に質問したら、八割が逃げますと答えたそうですが、外国に逃げたってマイノリティでいじめられるだけですよ。日本の有難みをそのときになってわかったってもう遅いんです。国の主権を守るということは非常に難しいけれど、しっかりした政治家が出てきて、軍国主義にならずにやり遂げることは必要だと思います。アメリカも覇権国家になって信じていいのか悪いのかわからない状況ですから。日本は金だけ持って武器なんて無くてもいいと言っていたら、誰かに食われてしまいます。もう少し覚醒して欲しい。日本人は、昔バカな戦争をやって負けたらしいよ、というだけでは死んだ人に済まない。書き残して置かなくてはいけないと思ったわけです。
――津本文学にとっても大きなターニング・ポイントになる作品ですね。ありがとうございました。