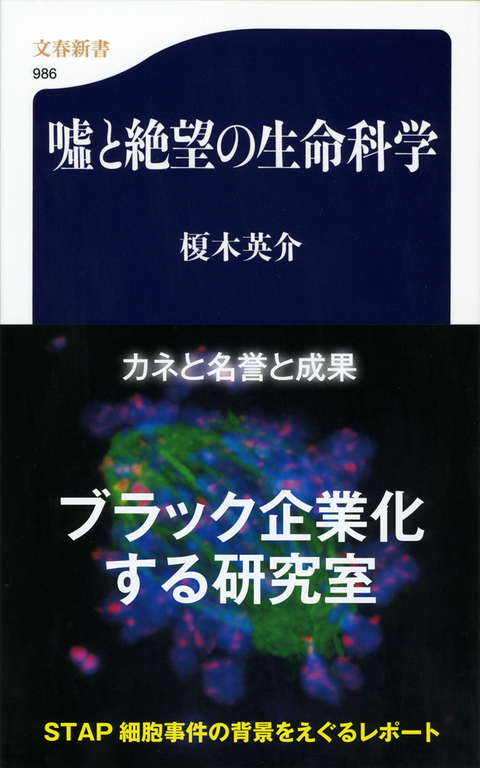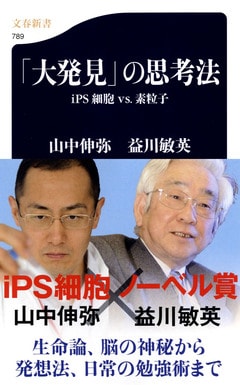STAP細胞をめぐる騒動はおそらく、多くの人たちにとって信じがたいものだったのではないだろうか。30歳の「リケジョ」が画期的な研究成果を出したとして、日本中がその業績を讃えた。その内容は、血液の細胞を弱酸につけると「万能細胞」ができるという革新的なものだったが、論文に不正が見つかると、世論はたちまち牙を剥いた。報道は過熱し、ついに自死者まで出ることになった。
問題がここまで大きくなった原因のひとつには、筆頭著者や共著者の所属機関であった理化学研究所(理研)の対応の危機管理対応のまずさがあった。しかし、より本質的な問題は、むしろ生命科学研究を取りまく構造にある。その問題意識からSTAP細胞騒動の背景に切り込んだのが『噓と絶望の生命科学』だ。発売から2ヵ月が経過し、賛否を含め様々な反響が寄せられているが、まずは本書の内容を少し紹介させていただきたい。
そもそもSTAP細胞をめぐってセンセーショナルに報じられた研究不正とは、何も今に始まったものではない。いろいろな分野で発生しているものの、その発生数は医学、生命科学の分野、いわゆるバイオ系が多い。東京大学の加藤茂明教授の事件や韓国のファン・ウソク博士の捏造事件、ノバルティス ファーマの高血圧治療薬「ディオバン」をめぐる論文データ不正問題、認知症研究「J-ADNI」をめぐる不正事件などが相次いでいる。
その背景には、若手研究者たちの奴隷のような労働実態をはじめ、研究費の獲得競争激化や、未熟で自己流の研究者が多数生み出される教育なき研究室、さらには大学院重点化で大量に生まれた漂流する博士たちの存在がある。それに何より、iPS細胞をはじめ、バイオ分野が成長産業として過剰に期待される現実もある。