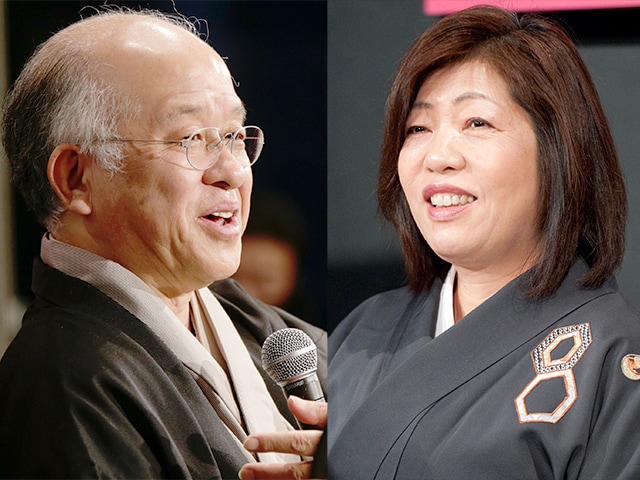
こちらもおすすめ
プレゼント
-
『生きとるわ』又吉直樹・著
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募締切 2026/01/03 00:00 まで 賞品 『生きとるわ』又吉直樹・著 5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。
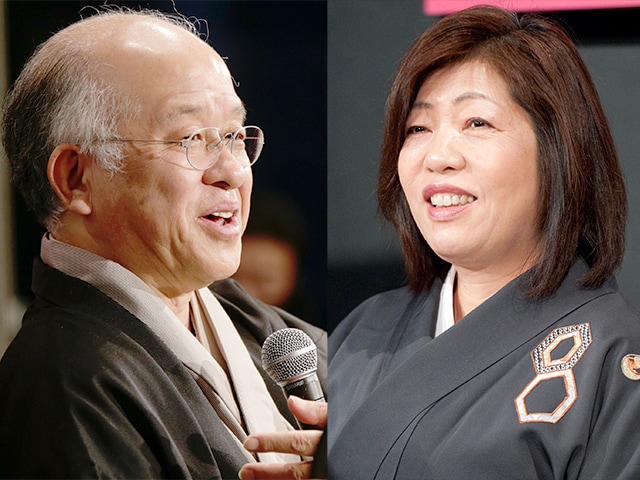

ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
| 応募締切 | 2026/01/03 00:00 まで |
|---|---|
| 賞品 | 『生きとるわ』又吉直樹・著 5名様 |
※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。