この小説全体も、都の、内なる母との長い長い時間をかけた対話なのである。対話の中で弟を思い、父を思い、母の少女時代を思い、母の友達とその娘のことを思い、母が恋したであろう人を思う。それは合わせ鏡のように、弟は自分をどう思っているか、父は、母の少女時代は、と裏返して考えることでもある。
この、思いのリバーシブルは、血縁を伴う関係だからこそではないだろうか。例えば会社の同僚やクラスメートなどだと、それぞれをつなぐものはその人の表にあらわれているものへの興味で繋がっているため、興味の範疇を越えた部分を探り合ったりはしない。必要がなくなれば関係は終わり、消えてしまう。
しかし血の繋がりのある場合は、その関係性に長い空白があったとしても、葬式など、命に関わる行事が起きたときは、呼び出される。不文律の絆に繋がれているのだ。
《奈穂子も、ママも、おばあちゃまも、わたしの知っている女たちはみな、このようにくちびるをかさねたことがあったのかと、愕然とした。自分が、なべての女たちのしてきたことをただなぞっているだけのような気がした。なぞれば、その芯にある心もちが、わかるのだろうか。女たちの、ママの、心もちが》
都は、異性と唇を重ねながら、他の女たちのことを思う。一つの身体と重なりながら、精神的には他の身体と繋がろうとしている。都は、あらゆる人の身体の中に流れる水のように、他の人の体感や心を考え、感じているのである。
都と、「ママ」の語りで綴られる、戦前から今年に到るまでの時間の中には、東京大空襲や昭和天皇の崩御、地下鉄サリン事件、東日本大震災など、実在の大きな出来事と、登場人物との関わりが描かれている。各時代に生きていた、各年代の生活の細部はリアリティーがあり、同時代の現実を生きていた自分の記憶もゆさぶられた。過ぎ去った時間が、身体の中に堆積しているということを実感する。
社会の大きな流れの底にある、閉ざされた個である「家」で、都という一人の女性が感じた密かな経験。それを特殊なこととして強調して描くのではなく、低音の文体で現実的な細部を重ね、その流れの中で漂っている空気ごと念入りに追体験できることが、この小説の恐ろしさだと思う。

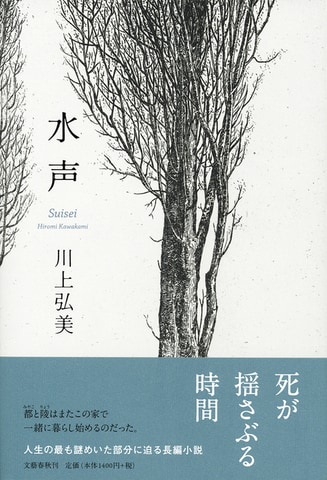
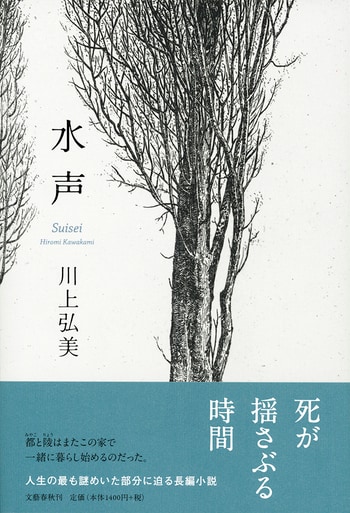

![[選者対談]小池真理子・川上弘美作家の全随筆を読んで見えてくるもの](https://b-bunshun.ismcdn.jp/mwimgs/9/9/480wm/img_99dfda8f29ff2d71bb2819048258a0de47962.jpg)












