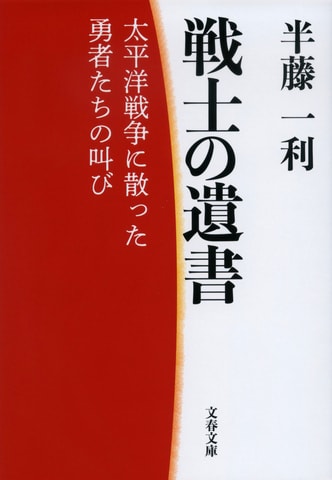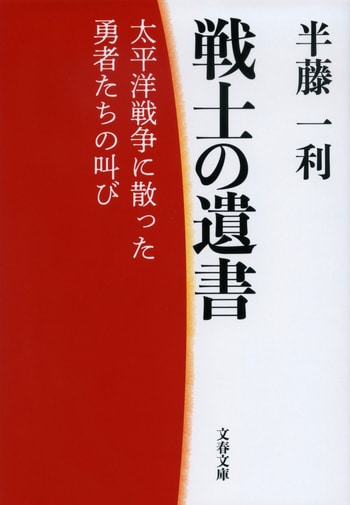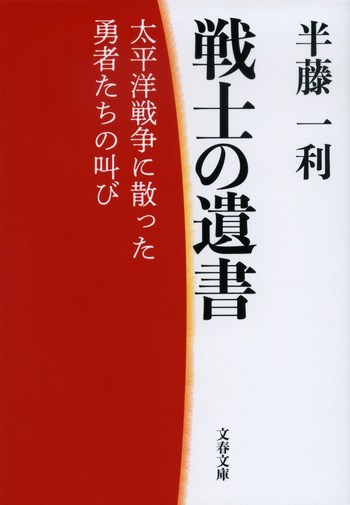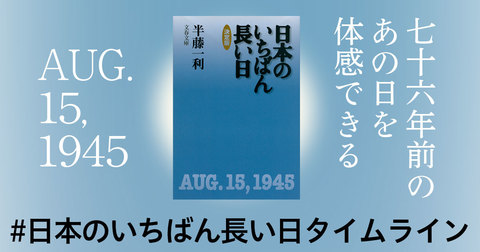8月3日に発売された、半藤一利『戦士の遺書 太平洋戦争に散った勇者たちの叫び』。
本書は「語り継ぎたい昭和軍人たちの遺書のことば」として、太平洋戦争に散った二十八人の軍人の遺書をもとに、各々の人物像、死の歴史的背景へと迫ります。
今回はその中から「マレーの虎」と呼ばれた、山下奉文の章を公開します
悲劇の名将、死処を得ざる苦しみ──陸軍大将 山下奉文
満洲の曠野(こうや)にあって対ソ戦に備えて指揮をとっていた山下奉文(やましたともゆき)大将に、第十四方面軍(在フィリピン)軍司令官の大命がくだったのは、昭和十九年九月二十三日である。マリアナ諸島防衛の決戦に敗れ、この戦争における大日本帝国の勝機は完全になくなっていた。山下は明らかに自分の国の最終的な敗北を予期し、あわせて自分の運命についても正確に見通した。
一緒に満洲にいた久子夫人ら家族のものに山下は言った。
「内地に帰って、最後のときは両親と一緒に死ぬほうがよい」
その覚悟を決めて九月二十九日に東京に戻ってきた山下を激怒させたのは、戦況緊迫を理由に、十月一日には比島へ出発せねばならなくなっている限られた日程であった。正味二日では、大本営での諸打ち合わせが手一杯で、各方面の人に別れを告げる余裕がない。ましてや天皇に拝謁する時間がないではないか。
対米英戦争の緒戦のマレー・シンガポール攻略戦において、山下は殊勲の将軍となった。しかし作戦終了と同時に、軍機の名のもとに東京の土を踏むことなく、一直線に満洲の牡丹江(ぼたんこう)へ赴任させられてしまった。軍司令官の新任務への就任には、天皇に拝謁し、戦況上奏とともに親任式が行われることになっている。山下にはこのとき、武人の無上の光栄ともいうべきこの式を、省略させられた痛恨の想いがある。
「こんどもまた親任式を省略するというのか。大本営は一体何を考えているのか。この出陣におれは服するわけにはいかん」
戦争がはじまっていらい、はじめての帰京なのである。大本営の命なりといえども絶対に後へは引かぬ決意が、山下のいかつい顔面にみなぎった。だが、その反面にかれの心中には、沈潜しているある淋しさがふたたび湧きあがってきていた。陛下はそれほどまでに山下を嫌っておられるのか、というつらい想いである。
それは昭和十一年の、いわゆる二・二六事件における天皇の、山下にたいして放たれたという強い叱責の言葉であった。皇道派の一員として、叛乱将校に一掬(いっきく)の同情をもっていた山下は、二月二十八日に川島義之陸相とともに宮中に侍従武官長本庄繁大将を訪ねた。かれは青年将校の苦衷を語り、かれらが罪を謝するために切腹する覚悟でいることを、武官長に語った。ついては、かれらを安んじて自刃させるためには特別の慈悲をもって「勅使を賜り死出の光栄を与えてもらえまいか」と涙ながらに申し出たのである。
しかし侍従武官長から奏上をうけた天皇は、かつてない怒りを示していった。
「たとえいかなる理由があろうと叛軍は叛軍である。自殺するならば勝手にさせるがいい。かくのごときものに勅使などもってのほかのことである」
そして天皇は語をついで言ったという。
「そのようなことで軍の威信が保てるか。山下は軽率である」
あからさまに臣下を名指しで戒(いまし)めることをしない天皇が、はたして「山下は軽率である」と言ったかどうかについては確証はない。ただし「軽率」の一語が天皇の言葉として山下の耳に入ったことは確かであった。
あのときから、すでに八年半もの暦日がすぎている。にもかかわらず、山下の名のあるところにまだ雪の日の惨劇が大きく立ちはだかるのか、という絶望の想いが、かれの胸中を埋めるのである。
その山下が、参謀総長梅津美治郎(うめづよしじろう)の計らいで、天皇と皇后に拝謁することができたのは、出発が延ばされた十月一日のことであった。襟を正した山下が、やや上気した面持ちで退出してきたとき、控えていた副官にはその表情が「もうこれで、いつ死んでも心残りはない」といっているように感じられたという。事実、皇居を辞するとき、侍従長に「私の生涯においてもっとも幸福なときでありました」としみじみと語っている。忠誠なる軍人として山下はひそかに天皇に別れを告げた。

こうして山下は比島防衛の大任を負って、日本本土から飛び立った。しかし、それはあまりに遅すぎていた。着任が十月六日、それから一週間もたたないうちに、米機動部隊は比島の日本軍陣地に大空襲をかけてきた。決戦準備よりさきに戦闘がはじまったのである。しかも当初計画されていたルソン島に兵力を集中しての一大決戦は、台湾沖航空戦で大戦果をあげたという大本営のとんでもない誤判断から、兵力分散のレイテ島決戦に変更された。山下はこの愚策に猛烈に反対したが、大本営も上級司令部の南方軍も、頑として耳を藉(か)そうとはしなかった。
山下は天を仰いで言った。
「レイテ決戦は後世史家の非難を浴びることになろう」
はじめから無謀愚策の一語につきたレイテ決戦に敗れ、兵力の大損耗をまねき、昭和二十年二月からは超優勢な米軍のルソン島上陸を迎え、山下軍は北部山中に籠城しゲリラ的抵抗をつづける持久戦に入った。寡兵による広大なる守備範囲、食糧と弾薬もままならず、補給なしとあっては、放胆な攻勢作戦のとりようもなかった。しかし第十四方面軍の将兵はねばれる限りねばり抜いて抵抗した。
八月十四日夜、ポツダム宣言受諾を知った山下司令部では、参謀たちが、虜囚の辱(はずかしめ)をうけず、また敗戦の責任を負って軍司令官は自決すべきかどうかで、議が闘わされた。
しかし山下は淡々として言った。
「私はルソンで敵味方や民衆を問わず多くの人びとを殺している。この罪の償いをしなくてはならんだろう。祖国へ帰ることなど夢にも思ってはいないが、私がひとり先にいっては、責任をとるものがなくて残ったものに迷惑をかける。だから私は生きて責任を背負うつもりである。そして一人でも多くの部下を無事に日本へ帰したい。そして祖国再建のために大いに働いてもらいたい」
山下はその言葉どおり、ルソン作戦中にたびたびあった住民虐殺の責任を負い、マニラのアメリカ軍戦犯法廷で絞首刑を宣告される。
「十分に覚悟しているから安心しろ。それよりもお前たちは、日本へ帰ってしっかりやってくれよ」
と弁護に立ったもとの部下たちに言うのを、山下は常とした。
山下が刑死したのは昭和二十一年二月二十三日。独房にあったとき、山下は毎日のように「アメアメフレフレ、カアサンガ……」と口ずさんでいたという。そして処刑のとき通訳としてつきそった僧職森田師に、辞世の歌三首と、将兵一同とその家族にたいする最後の言葉を口述している。
野山わけ集むる兵士十余万還りてなれよ国の柱に
今日も亦大地踏みしめ還り行くわがつはものの姿たのもし
待てしばし勲(いさお)残して逝きし友後な慕ひて我も逝かなむ
「私の不注意と天性が暗愚であったため、全軍の指揮統率を誤り何物にも代え難いご子息、あるいは夢にも忘れ得ないご夫君を、多数殺しましたことは誠に申し訳のない次第であります。激しい苦悩のため、心転倒せる私には衷心よりお詫び申し上げる言葉を見出し得ないのであります。(中略)
私は大命によって降伏した時、日本武士道の精神によるなれば当然自刃すべきでありました。事実私はキヤンガンで、あるいはバギオで、かつてのシンガポールの敗将パーシバルの列席の下に、降伏調印した時に自刃しようと決意しました。しかし、その度に私の利己主義を思い止まらせましたのは、まだ終戦を知らない部下たちでありました。私が死を否定することによって、キヤンガンを中心として玉砕を決意していた部下たちを、無益な死から解放し、祖国に帰すことができたのであります。
私は武士は死すべき時に死処を得ないで恥を忍んで生きなければならない、というのがいかに苦しいものであるか、ということをしみじみと体験しております……」
悲劇の名将とよぶにふさわしい山下の、刑執行四十分前の言葉には、かつての部下を一人でも多く祖国へ帰してやりたいという、あふれんばかりの想いだけがある。忠誠な軍人としての、天皇にたいする別れはもうとっくにすんでいたのであろう。