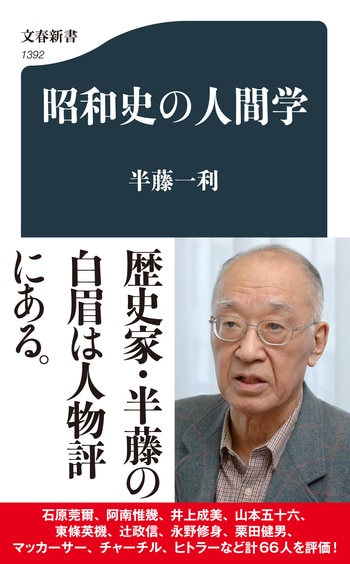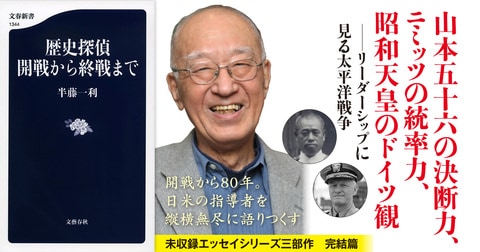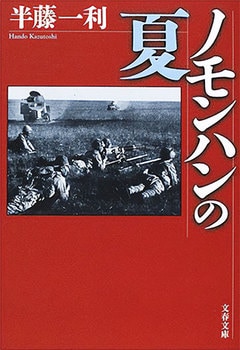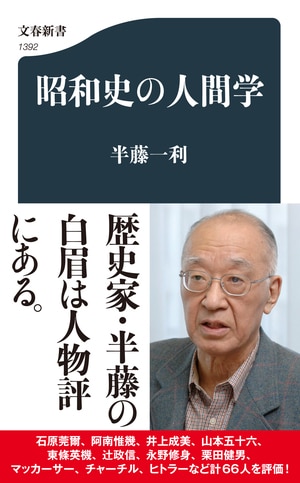
“歴史探偵”と自らを称した半藤一利は、共著も合わせれば百冊近い書物を遺しました。書籍化されていない雑誌記事を含めれば、その仕事量はじつに膨大です。
そもそも半藤が“歴史探偵”に目覚めるのは文藝春秋に入社して一週間目に、群馬に住む坂口安吾のところに原稿をもらいに行った折のことです。原稿は一枚もできておらず、しばらく泊めてもらって待つことになりました。
「安吾さんは、古代史や戦国時代を中心に、歴史の話を毎晩、話題を変えて話してくれました。歴史のおもしろさや解釈の多様さを教えられましたね。完全な意味の『歴史開眼』、いや『人生開眼』をしたと言ってもいい。『史料なんてものをいくら並べたって、歴史の本当のところはわからない。歴史というのは史料の裏側を読まないとわからないんだ』という言葉を今でも覚えています。
『もしかすると、もしかするんじゃないか』と考える人が発想の転換ができるんであって、初めから『これはそういうもんだ』と思ってしまってはけっして発想の転換ができない。史料と史料を重ね合わせて、なおかつそこの行間に、ごく常識的な推理力を働かすことによって、本当の全容が浮かび上がってくるもんだという、いわゆる『歴史探偵学』を毎日のように教わったんです」(「半藤さんが『歴史探偵』になるまで」)
その後、半藤はとりわけ昭和史にのめり込み、手当たり次第に史料を集めて読破することになります。氏の仕事がその価値を失わないのは、そうした巨大なバックボーンがあるからでしょう。一文一文、ひと言ひと言の背後には、途轍もない量の裏付けがあるわけです。
半藤は文藝春秋に勤務する編集者でもありました。ゆえに、当事者たちへの旺盛な取材による見聞が加わります。もちろん、当事者といえども話にウソはつきものですから、それを看破し精査するにはやはり膨大な知識が必須となります。
半藤を比類のない存在にならしめたのは、こうしてでき上がった知識と見聞の双方から成る蓄積といえます。氏の仕事をさらに価値あるものにしているのは、そうした莫大な蓄積を土台にした上で、安吾の指南よろしく、史料の裏側を読む確かな視点があったからだと思われます。史料の裏側を読むとは、人の心理を読むことでもありましょう。なぜなら、本人も言うように、「歴史とは人間学」(本書198ページ)だからです。
歴史を見つめ、人間を見つめるゆるぎない視座があればこそ、半藤の月旦は面白いのです。氏の仕事の白眉は、その人物批評にあるといえるでしょう。
今回、本書を編むにあたって、半藤が人物を評している部分にスポットを当てました。
人物は昭和期の軍人と政治家に限りました。
これらの軍人と政治家は昭和史を動かしたキーパーソンです。したがって、本書を一読すれば昭和史のキーポイントが大づかみでわかるようになっています。
また、当時の国民の空気や熱が背中を押すものとしてあったにしても、歴史を実際に一歩前に進めたのは、どの場面でもごく少数の人たちであったことがわかります。良い例をあげれば、御前会議での鈴木貫太郎と昭和天皇の阿吽の呼吸がなければ太平洋戦争は確実に延びていたし、日本の被害は拡大していたでしょう。逆に、悪い例として歴史の「if」を言うなら、近衛文麿、伏見宮博恭王、東條英機、永野修身、松岡洋右らがあの時あのポジションに就いていなければ、日中戦争や太平洋戦争は起きなかったのかもしれません。
それはさておき、とりわけ戦争という異常な状況において、人は正体をさらけ出します。出世欲をたぎらせる者、卑怯この上ない者、右顧左眄する者、信念を貫く者、部下思いの者……。その人間模様は、さまざまな示唆に富んでいます。それはまた現代のビジネスパーソンの戦いの場にも通じる普遍的な人間の姿ともいえるでしょう。
読者諸氏におかれましては、歴史探偵が残したもっとも“おいしい部分”を熟読玩味されることを願うばかりです。
編集部
「はじめに」より