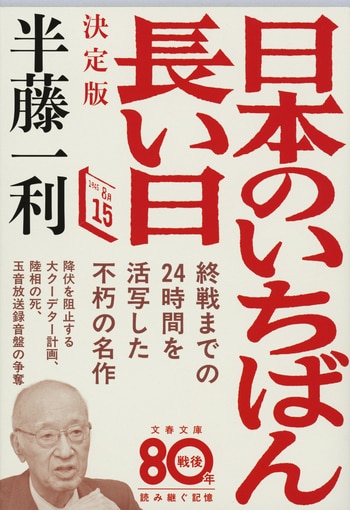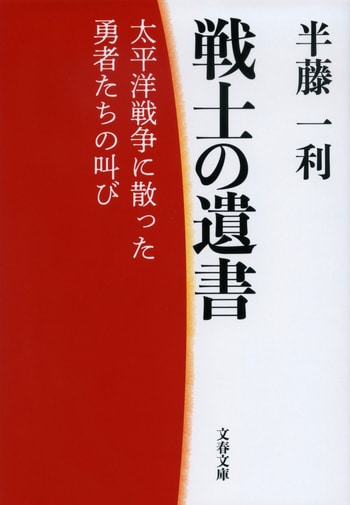6月6日、東京會舘で「半藤一利さんの思い出を語り合う会」が催された。本降りの雨の日で、11時からである。11時にこうした会の開かれることに戸惑ったお方もあったようだが、11時開演が当り前の商業劇場で慣れている私は、まったく痛痒を感じない。
会では、印税や原稿料の前借りでしのいでいた若い時分、さんざお世話になった多くの元文藝春秋編集者に久し振りにお目にかかれ、嬉しくも懐かしかった。圧巻は宮部みゆき、澤地久枝、阿川佐和子、竹下景子の女性4人の心情あふれたスピーチだった。半藤さんが文藝春秋を退社したとき、女性社員だけでの送別会が開かれたようにきいている。

文藝春秋時代の半藤さんとは、「文藝春秋デラックス」増刊の『昭和50年をつくった700人』など、何度か仕事をさせて頂いた。『昭和50年をつくった700人』では、700人のなかにジプシー・ローズを入れたことを戸板康二に褒めてもらいながら、二代目市川左團次の写真が三代目だったのを指摘されたことを明かしてくれた。
畏敬する永井荷風の顰(ひそみ)に倣ったものか、若かりし日、三代目三遊亭金馬に入門志願したと半藤さんからきいたことがある。「学校をちゃんとすませなさい」と入門を断わられたそうだが、歴史探偵半藤一利から落語家半藤亭一利というのは、イメージがわいてこない。ならなくてよかった。

1時をまわったところで、会のほうはお開きになった。さて次なるところへ行くのに迷った。むかしはシティホテルのバーは朝から営業していたものだが、昨今は夕方までクローズしている。東京會舘のメインバーも午後4時オープンだという。
親しかった友人の葬儀には出席しないで、その時間故人の著作に目を通しながら、ホワイトホースのミルク割りで偲ぶという、木下順二の供養のしかたを思い出し、それをすることにした。綺麗好きだった荊妻(けいさい)に七年前逝かれていらい、ごみ屋敷然とした我がリビングで、木下順二風に半藤さんに思いをいたした。手近にあった『世界史のなかの昭和史』(平凡社)を取り出し、東京駅構内の駅弁屋で求めた大船軒のサンドイッチを皿にうつし、到来物のワインを抜いた。