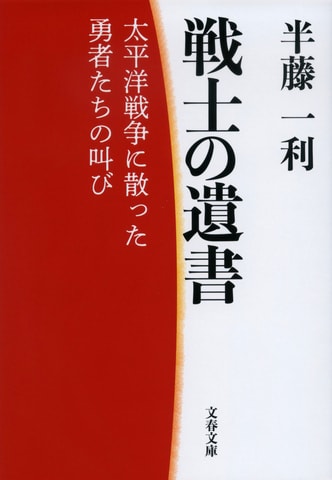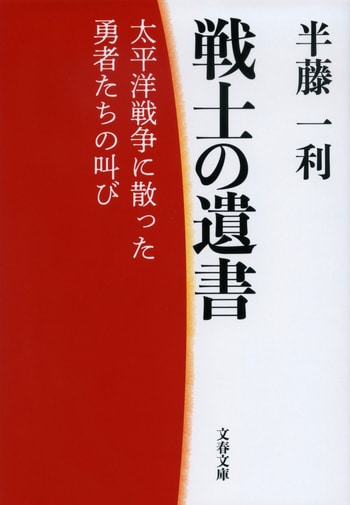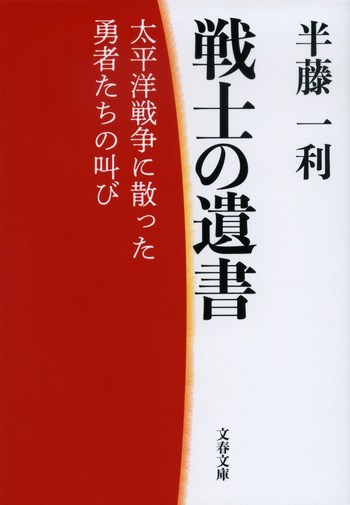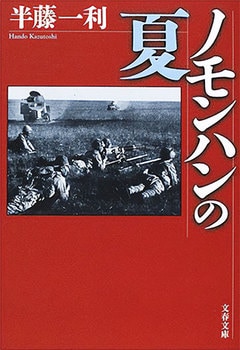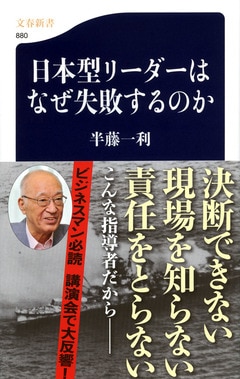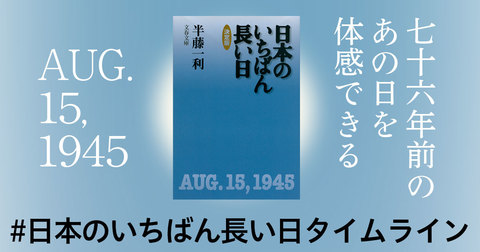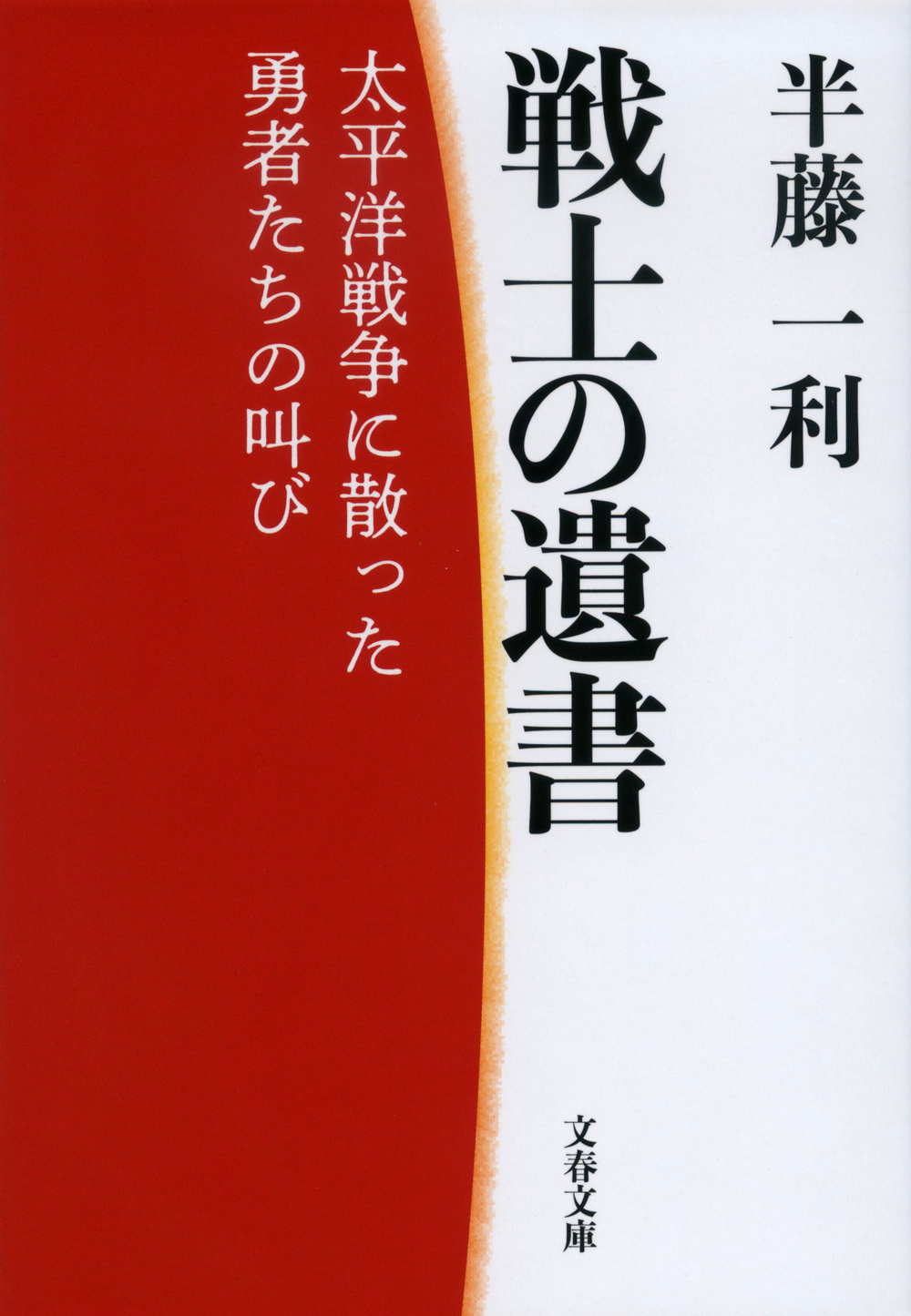
本日発売された、半藤一利『戦士の遺書 太平洋戦争に散った勇者たちの叫び』。
本書は「語り継ぎたい昭和軍人たちの遺書のことば」として、太平洋戦争に散った二十八人の軍人の遺書をもとに、各々の人物像、死の歴史的背景へと迫ります。
今回はその中から「特攻の父」と呼ばれる、大西瀧治郎の章を公開します。
押しつけられた偶像「特攻の父」──海軍中将 大西瀧治郎
軍令部次長大西瀧治郎(おおにしたきじろう)中将が自決したのは、昭和二十年八月十六日午前二時四十五分である。作法どおり腹を切り、頸と胸を刺したが、なお死ぬことができなかった。急報でかけつけた軍医の姿を認め、大西はこのまま死なせてくれとばかりに手をふった。たしかに、腸のとびだしている状態ではたすかる見こみもなかった。「死ぬときはできるだけ長く苦しんで死ぬ」と言っていた大西は、介錯も強く拒み、
「これでいい、送り出した部下たちとの約束を果たすことができる」
と、あふれる血のなかで破顔しながら十数時間後に息を絶えた。
遺書は二通。一通は長野に疎開中であった淑恵夫人に宛てたものであり、もう一通は、かれに見送られて十死零生の作戦に散った全特攻隊員に宛てたものであった。
「特攻隊の英霊に曰(もう)す/善く戦ひたり深謝す/最後の勝利を信じつゝ/肉弾として散華(さんげ)せり
然れ共其の信念は/遂に達成し得ざるに至れり/吾死を以て旧部下の/英霊と其の遺族に謝せんとす
次に一般青壮年に告ぐ/我が死にして軽挙は/利敵行為なるを思ひ/聖旨に副(そ)ひ奉り/自重忍苦するの誡(いましめ)とも/ならば幸なり/隠忍するとも日本人たるの/矜持(きょうじ)を失ふ勿れ/諸子は国の宝なり/平時に処し猶ほ克(よ)く/特攻精神を堅持し/日本民族の福祉と/世界人類の和平の為/最善を尽せよ」
終戦の天皇放送の流れるその直前まで、無条件降伏に反対し、全軍特攻を提唱し神州不滅を叫んでいた闘将とは思えないほどに、遺書には冷静な祈りが織りこまれている。徹底抗戦の主張から一転し、ここでは軽挙妄動をつつしめという。生き残った若い人たちに「諸子は国の宝なり」とよびかけ、これからの日本建設そして世界平和のために、特攻隊のような自己犠牲の精神を発揮し最善を尽せよ、と大西は願っている。
国家のためとはいえ、非情な特攻攻撃でつぎつぎに生命を散らしていった隊員たちは、すべて若人である。国の宝であった。その国の宝を体当り攻撃で送り出した痛恨の想いが、大西にこの遺書を書かせた。死に臨んで闘将大西は、何よりも平和を希んでいた、と言えるかもしれない。

今日われわれは大西中将を「特攻の父」とよんでいる。特攻作戦を発案し、それを実行に移した提督という意である。地下に眠る大西もまた、その名をかならずしも拒否するものではないことであろう。全責任を一身に負って自刃したかれの胸中には、十万億土で散華した多くの若者の先頭に立つの想いがあったであろうから。
しかし、歴史的事実を深くたずねれば、そこに疑問なしとはしないのである。特攻戦術が採用されるに至るまでの経過は、きわめて混沌として見極めがつけにくい。一概に、大西中将の提唱によって、などと結論づけることは事実を見失うこととなろう。
昭和十九年七月、サイパン島を失い、戦局は日本帝国にとって最悪の段階を迎えた。本土全部がB29の爆撃圏内に入ることを意味し、軍事工業が壊滅すれば近代戦の遂行は不可能になる。当時、軍需省航空兵器総局の総務局長であった大西は、この事態に対応すべく断乎たる処置を強請する意見書を、海軍大臣嶋田繁太郎大将に突きつけた。
その所見が海軍中央を震撼させるのと前後して、東条英機内閣が総辞職し小磯国昭内閣が成立、海軍首脳部が一新してしまう。しかし大西の意見書の波紋はおさまらぬどころか、いっそう荒立ち、十月五日付で大西の南西方面艦隊司令部付が発令される。やがて、つぎの決戦正面であるフィリピンの第一航空艦隊司令長官に任命されるであろうふくみが、その裏にあった。
この最前線転出が、はたして懲罰人事であったのか、それとも決戦正面へ海軍航空のエースを登場させる重要な意味をもっていたものなのか、真相は曖昧模糊とした霧の中にある。しかも人事発令四日後の十月九日、大西は蒼惶(そうこう)として東京を去るのである。
途中で台湾沖航空戦の予期せぬ戦闘もあって、大西がフィリピンのマニラに着いたのは十月十七日。翌十八日、米軍の比島上陸作戦が開始され、捷(しょう)一号の決戦作戦が発令される。大西は十九日夕刻に最前線であるマラバカット基地へ赴いた。そしてその夜も、時計の針が二十日になろうとする午前零時前後に、下からの盛りあがる力によって、敵艦船に体当りする特別攻撃隊の編成が決定された、ということになっている。
もう少しくわしく書けば、その特別攻撃案を一つの案として、マラバカットにいた第二〇一航空隊の副長玉井浅一中佐と参謀猪口力平中佐に示したのが、大西中将なのである。
「零戦に二百五十キロの爆弾を抱かせて体当りをやるほかに、確実な攻撃方法はないと思うが……どんなものだろうか」
これに玉井副長が答えた。
「私は副長ですから、勝手に隊全体のことを決めることはできません。司令である山本栄大佐の意向を聞く必要があります」
これにたいして大西中将は、おおいかぶせるように、
「山本司令とはマニラで打ち合わせずみである。副長の意見はただちに司令の意見と考えてさしつかえないから、万事、副長の処置にまかす、ということであった」
と言った。しかし、事実は、マニラで大西は山本司令と会ってなんかいなかった。ということは、大西が完全な噓をついて、玉井副長に決定的な判断を求めたことになる。
ここで少し前のところを読み直してほしい。大西はまだこのときは南西方面艦隊司令部付の一中将で、なんの命令権も決定権もない。であるから、わたくしは大西中将と書いてきた。第二〇一航空隊を指揮する第一航空艦隊司令長官に正式に任命されるのは、翌十月二十日なのである。ならば、玉井副長をだましたりせず、長官になってから大西は正々堂々と話し合えばよかったのである。大西はそれをしなかった。何故なのか。
ここに一通の興味深い電報が残っている。軍令部の源田実(げんだみのる)参謀の起案になるもので、日付は昭和十九年十月十三日。
「神風攻撃隊ノ発表ハ全軍ノ士気昂揚竝(ならび)ニ国民戦意ノ振作ニ至大ノ関係アル処 各隊攻撃実施ノ都度 純忠ノ至誠ニ報ヒ攻撃隊名(敷島隊、朝日隊等)ヲモ併セ適当ノ時期ニ発表ノコトニ取計ヒ度(たし)……」
この電報起案は、大西中将が東京を離れた数日後に、すでにして書かれている。しかも、何ということか、神風攻撃隊の名も決められている。さらに言えば、十月二十日に特攻作戦が正式発令となり、大西が名付けたという本居宣長の「敷島の大和心を人問はば……」の歌に発する敷島隊、大和隊、朝日隊、山桜隊の攻撃隊名も、この電報の中にある。
この合致は決して偶然なんかではない。明らかに、体当り攻撃は作戦の総本山軍令部の発案、そして決定によるものであったことを語っている。つまり特攻という非人間的な攻撃の責任は、海軍中央が負うべきものである。大西はその実施命令の発動者になる役割を負わせられて、早々に東京を旅立った。しかし、大西には長官として「命令だけはしたくない」の深い想いがあったと思われる。それが真夜中の、まだ一中将の提案となり、玉井副長への欲せざるごまかし発言となった。
明治二十四年(一八九一)生まれ、海兵四十期、百四十四人中の二十位で卒業、頭も決して悪くない。生えぬきの航空屋として山本五十六大将の信頼の厚かった大西は、単なる我武者羅な勇猛、豪胆の士ではない。親分肌の人情家、神経もこまやかであった。そして作戦は九死に一生をもって限度とす、自分ができぬことを命令してはならぬ、そうしたよき海軍魂を身につけた闘将でもあったのである。
それだけに特攻攻撃の生みの親とならねばならぬ自分の立場をのろったと思えてならない。大西長官は、だから、たえずこう洩らしていた。
「特攻なんてものは、統率の外道の外道だ」
また、副官の門司親徳(もじちかのり)大尉にしみじみ語ったという。
「わが声価は、棺を覆うても定まらず、百年ののち、また知己はないであろう」
大西の死を聞いたとき、かれを知る海軍航空の関係者は驚きもなくうけとめた。なぜなら、大西中将は戦争に勝っても腹を切ったであろうと、だれもが思っていたからである。
辞世がある。
これでよし 百万年の仮寝かな