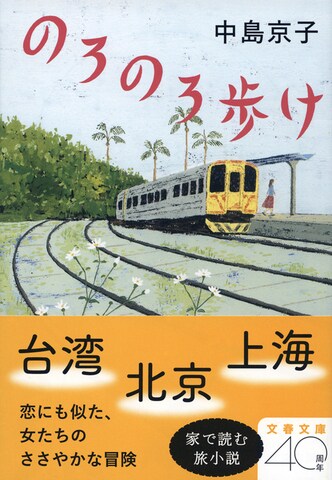ところで、中島さんはきっと食いしん坊だ。台湾のおいしいものが次から次へ、これでもかと登場する。花蓮の扁食(ワンタン)にはじまり、練乳とフレッシュ・マンゴーをどっさりかけたふわふわのかき氷、担仔麺、青々しい菜っ葉の炒め物、甘くて八角の匂いのするソーセージ、胡椒餅、生姜の入ったサトウキビジュース、豆乳スープに揚げパン、マンゴージュース、水餃子……。
美雨はおじさんたちに会って、みんなと一緒にこれらのおいしいものを食べたからこそ元気になったのだ。単行本では最後のエピソードだった「天燈幸福」だが、大きく膨らんだランタンのように、平渓の夜に浮かび上がるトニーの丸い笑顔が、オープニングにふさわしい。
「北京の春の白い服」の舞台、北京の街には黄砂の混じる風が吹くが、それでも魅力的な場所は色あせない。路地端で老人たちが中国将棋に興じ、コメや豆を入れた袋が路地に置かれ、家々の戸口に福の字が逆さに貼り付けられている胡同(フートン)の街並みや、大通りにびっしり屋台が並ぶ旧市街。働く女、夏美に、露店の砂糖菓子売りのおじさんが「マンマン・ゾウ」と声を掛ける。「のんびり行けや」と。
中島さん自身が、かつて北京の出版社で二週間ほど編集者をした経験を題材にしたそうで、夏美と中国人スタッフのやりとりを読んでいくうちに、中国のファッション雑誌の誕生が、まるで目の前で展開されているような感覚に陥る。その中で、夏美が一九八六年の男女雇用機会均等法施行のとき、銀行に「一般職」として不本意な就職をしたことや、ウルムチの女性カメラマンが一人っ子の子供を親元に残して北京に来ていることなどが描かれ、今より少し前の日本と中国の働く女性が置かれた状況が簡潔に示される。
描写はそれだけにとどまらない。「一億人のオムツ」を想像する夏美。二〇一四年に入って、中国人観光客のオムツの買い占めが日本でニュースになったが、中島さんはそれよりもずっと前にこのオムツ需要を予測していた。この小説を書いたあと、中国のオムツ業界に進出していたら、いまごろ大金持ちだったはずだ。それにしても、お尻にスリットの入ったズボンは本当にもうないのだろうか。
お別れに赤いカーディガンを夏美にプレゼントした常盤貴子似の服務員の気持ちと言葉が心に染みる。中国人スタッフが主張したファッション業界らしくない「冬の服をまだ着て春に備える」という巻頭特集が、中国の伝統的な考え方に基づいていたなんて。わたしたちは、そのことを夏美と一緒に知り、そして、とても温かい気持ちになる。
中島さんは、そんな素敵なエピソードでほっこりさせてくれるかと思えば、時に女の毒をチクリと注入してドキリとさせる。美雨がトニーの昔の恋の話を聞いて、「ほんとにつきあってたの? そう思ってただけじゃなくて?」と口走る。そんな無遠慮な! 夏美がアメリカ人の恋人、ジェイソンとの電話を切る場面。「無言で受話器を置いた」。怖い! 亜矢子が夫と久しぶりに再会したとき。「だいじょうぶだった?」という夫の問いかけに対し、「何が?」と返す。恐ろしすぎる切り返し! ルー・ビンが元夫のことを語るとき。「私は彼をよく知っています。キスと同じだけの時間もったかどうかわかりませんよ」のくだり。戦慄! イーミンにマグカップを投げつけるリー・リーなんてかわいいものだ。女は温度が低いときほど怖い。そのことを、女である中島さんはよくご存知だ。