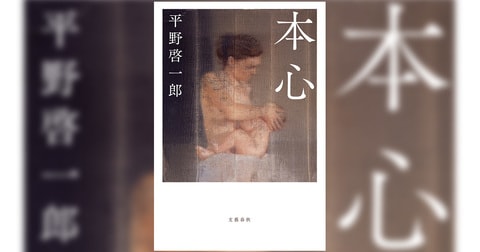血盟団事件が起きたのは、一九三二年である。――昭和の、しかも戦前の遠い出来事ではあるが、本書は冒頭に、その最後の団員であり、五・一五事件の実行犯の一人である川崎長光のインタヴューを置くことで、読者にこの不穏な時代へとアクセスする術を与える。
こんな人が、我々の隣人として存在していたのかとまず驚かされるが、それは、事件直後に当時の人々が感じた衝撃とも通ずるものであろう。
川崎は、地元の保育園の「名園長として慕われてきた」そうだが、その一方で、四元義隆のように、戦後、フィクサーとして政界に大きな影響力を持った団員もいる。
歴史の年表を見れば、事件はただ、ある時、ある期間に起き、その隣には、もう次の別の事件が入れ替わるようにして並んでいるが、人間の寿命は、その行動を超えて遥かに長く続くものであり、影響は容易には消えない。そして、それは決して予測可能なものではなく、またコントロール出来るものでもないのである。
川崎の肉声から筆を起こした著者は、首謀者の井上日召を中心に、団員一人一人の生の軌跡を丹念に辿りながら、事件を一篇の群像劇のように描き出してゆく。
本書は、読み物としても非常に面白く、とりわけ、決行の日時を全国各地に散らばったメンバーに伝える役目を担った四元が、憲兵のマークを外すために行動を偽装し、結果、計画の実行そのものが危ぶまれることとなる場面などには、サスペンスがある。
個々のメンバーには、内的動機があり、また彼らをテロリストたらしめた時代と社会の現実がある。
著者はその両者を視野に収めつつ、主に事件に至るまでのプロセスに重きを置いて、周到な調査を行い、明晰な分析を加えてゆく。
一読して非常に印象的なのは、血盟団のメンバーの多くが、病弱な少年期を過ごしている、という点である。川崎、小沼、古内、照沼、久木田、池袋、……と、いずれの生い立ちにも、そのような事実に触れた箇所がある。
近代の政治権力は、前近代の生殺与奪権に基づく君主的な権力から、公衆衛生を通じて国民の生命をマネジメントする所謂(いわゆる)「生権力」へと変化した、というのが、フーコーの指摘以来の認識だが、西洋列強と肩を並べるべく、富国強兵のための政策に邁進してきた大日本帝国に於いて、彼らはその不健康の故に、社会から排除されるべき存在だった。実際、今し方名前を列挙した各々が、就職や徴兵検査といった人生の重要局面で、大きな挫折感を経験している。
近代以降、機能的にひたすら細分化されてゆく社会の中で、職業選択の自由化は、言わば必然だった。そして、身分制度という「出自」がアイデンティティを保証する社会から、何をしたかという「行為」がアイデンティティの根拠となる社会へと変化した時、当然のことながら、職業は、「自分とは何か?」という問いへの一つの答えとなる。社会的に認知された、はっきりとした仕事を持っていないことは、自他共に不安であり、またそれが自分の生き甲斐と合致していないと、内面的に分裂が生じる。
ところが、そこには一つのパラドクスがある。というのも、自分が何の職業に就くべきかを知るためには、自分は一体何をしたいか、つまり、「自分とは何か?」という自己の本質規定がアプリオリになされなければならないからである。
行為こそがアイデンティティを確定するにも拘らず、その行為を社会的に可能とする職に就くためには、まずアイデンティティを確定しなければならないというジレンマ。――これが、近代以降の青少年の苦悩の根源であり、そして、“健康でない”という事実は、この循環的なアイデンティティの液状化からの脱出を挫折させてしまうのである。
これと相関して、本書で注目されるのが、井上や古内の一種オカルト的な「病気治し」である。
彼らは一旦、病という“不可抗力”によって、社会システムから排除され、失意と貧困を経験させられる。その身体には、国家の“役に立たない”という烙印が押されてしまう。彼らのパーソナリティそのものが、到底、社会に無批判に従順であることを肯(がえ)んじなかったという点も大いに強調すべきだが、いずれにせよ、そうした人々は、決して少なくなかっただろう。その時、彼らの受け皿となるべき救済のシステムは、肉体的な慰謝と精神的な慰謝との両方に亘(わた)っていなければならなかった。実際に、心の拠り所が与えられたというだけでなく、病気が治ったというのは不思議としか言いようがないが、そのオルタナティヴな「生権力」によって、死への墜落を免れた彼らは、複雑な感情を内に孕(はら)んだように見える。
彼らは、自らを排除した資本主義の社会へと復帰することを拒む。絶望的な格差を生み出すその腐敗に対して、彼らは激しく憤っている。そして、今や健康を恢復した身体は、本来、就職を通じて得られたはずの社会的なアイデンティティに代わる何かを要求する。固(もと)より、彼らの“生まれ”はそれに値しない。その時、彼らの発想は、社会を超越して国家へと飛躍する。つまり、共同体の構成員として“真に正しい”、“本来的な”振る舞いをしたいと願望するに至るのである。
なぜ、社会的な成功を収め、国家の然るべき役職にある財界人や政治家、或いは官憲――つまりは「支配階級」――よりも、自分たちの方が正しいと信じられるのか?
一つには、虐げられた人々の不幸が歴然としていて、また自らも身を以てその理不尽を経験していたからである。しかし、更にもう一つ、著者が重要な点として指摘しているのは、彼らが、「宇宙の大原則」の神秘主義的な直感を得ていたという点である。「病気治し」は、それを象徴的に垣間見せるエピソードである。その非合理な思想は、近代の科学からも資本主義からも排除されたものであり、だからこそ、彼らが社会と対峙する上での思想的な足場となり得た。その言語化されたテクストこそが、彼らの場合、日蓮宗であり、その影響下にあった国家主義、或いは超国家主義だった。
この大いなるものと孤立した自己との一体感、そして、それを阻害しようとする中間的存在という世界観は、天皇とその臣民、そして「君側の奸」といった発想までをも含めて、彼らの認識の基盤をなしている。彼らが、裏道を抜けて飛躍しようとする国家、或いは宇宙といった次元は、階層的には世俗的な社会よりも上位に存し、持続という意味では、決して一時的ではない、永遠性を備えている。こうした発想を、著者は、単なる私的なコンプレックスとして、心理的な次元に矮小化することなく、歴史と社会構造に根差した精神の問題として扱うことで、今日の我々にも有意義な視点を与えている。
血盟団は、国家と個人との間で、市民社会を虚無化し、それを挟み撃ちにする。なぜなら彼らは、そこから何ら恩恵を被っているという実感を持っていないからである。現状を追認するいかなる動機をも欠いている。これは、テロリストについて思考する上で、決定的に重要な認識である。今日という一日と同様に、明日や明後日が訪れてほしいと願うならば、人はこの世界の持続のための努力を払う。しかし、そうでないならば、たとえ「大馬鹿」と見なされようとも、革命のための「破壊」を遂行しなければならない。暗殺は、その一環に過ぎず、通念的な倫理も、国家の法規も、「宇宙の大原則」という絶対的な視点からは、悉(ことごと)く相対化されてしまうのである。
しかし、いかに腐敗していようとも、社会こそは、この世界の複雑な多様性を抱え込んだ現実である。そして、その変革のためには、決して純化し得ない実践(プラクシス)が求められる。もしその次元を捨象してしまうならば、なるほど、美しく完結した世界像が得られるであろう。そしてその必然的な帰結は、政治の否定である。
興味深いのは、血盟団が、破壊のための行動に関しては、極めて積極的で、観念的な論者たちと交わっては失望し、その無力さを馬鹿にしている点である。
しかし、著者が再三強調する通り、井上を始めとしてメンバーらは、一貫して「破壊」の後にあるべき肝心の「改造後の建設」への関心を放棄していた。これが、血盟団事件の最も皮肉な点である。
藤井斉が、満州で「売薬して生活」している日本人を二、三人、中国人に殺させ、それを国際問題化させて、どさくさに紛れて革命を成就させることを大川周明から聞かされたという話が書かれている。この何とも暗鬱な、卑劣な計画に、井上が激怒したという件りは、彼の中の塩湖のように澄んだ純粋さを感じさせて、強い印象を残す。
井上の目指した革命とは、一言で言えば、江湖の人の意識改革である。そして、彼らの行動によって、ひとたび日本人が覚醒しさえすれば、あとは必ずやそのうちの“誰かが続き”、“何とかなる”という楽観がある。そのためには、なるほど、彼らの行動には私心があってはならず、また、共感を阻むような不正があってはならない。――が、そのアナウンス効果をもたらすのは、彼らが憎悪の対象とする、まさに中間物たるマスメディアである。そして、彼らが夢想する革命の時系列の機能分担こそは、近代の社会構造の見事なまでの無意識の反映である。
血盟団の中でも、最初期から井上の周りに集っていた「大洗グループ」の関心が、貧困を始めとする「内憂」であったのに対し、海軍の藤井や後に合流する四元ら東京帝大グループは、むしろ「外患」としてのロンドン海軍軍縮条約に革命への焦燥を募らせている。
この二つの、一見、必ずしも結びつかないようなグループが行動を共にしたという点に、恐らくは、血盟団事件の秘密があり、著者の理解の深さがある。それを実現したのは、井上のカリスマであったろうが、その井上自身にせよ、大洗グループのみに取り囲まれていたのであれば、暴力革命は志向しなかったのかもしれず、陸海軍との連携といった壮大な計画には発展していかなかっただろう。血盟団事件そのものに於いては、この連携は成功しなかったが、これが冒頭の川崎も参加した五・一五事件へと連なることを考えるならば、このことの意味は、幾ら強調しても足りない。組織とその運動という意味では、ここには、キリスト教の最初期に見られた、ペテロに代表されるヘブライ語とヘブライ文化出身のグループと、パウロが代表するギリシャ語とギリシャ文化出身のヘレニズム・グループとの競争的な共存関係に似たものが見えている。血盟団の対社会的な求心力は、この内部の異質な要素の間の力学に負うところが大きかった。その潜在的な緊張関係は、戦後社会にまで生き延びた個々のメンバーの有り様にも見て取れるように思う。
血盟団事件とは、一体何だったのか?
今日の読者は、本書を、世界的な危機としての格差とテロという現実に於いて読んでいる。それは決して幸福とは言えない状況だが、だからこそ、それに知を以て果敢に応じようとする著者に深く敬服する。