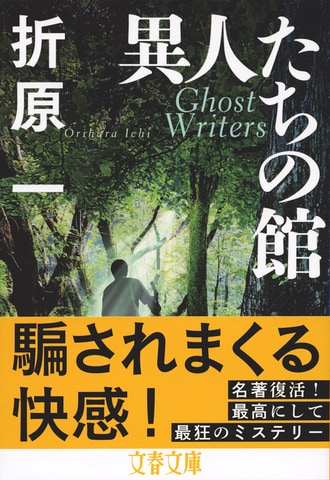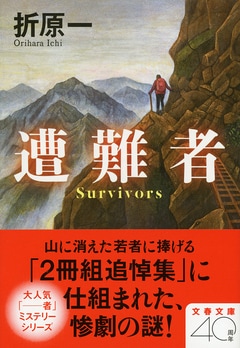多重文体によって読者を惑乱し、B級事件の与える先入観で読み手の推理を誘導する――本書は極めて技巧的な作品である。
誘(いざな)われた読者を待ち受けるのは、折原一の代名詞ともいえる“叙述トリック”だ。この系統のミステリーでは、“語っているようで語っていない情報”が重要な役割を果たす。それが明らかになることで事件の様相が大きく変貌するのである。本書における多重文体は、この効果を高める強力な源泉となっている。折原は異なる次元にある文書の数々に、その語らないことを――大量に――仕込んだ。読み手は錯綜するテキストの分量に圧倒され、本来読み取るべき情報から意識がそらされていく。あるいは、情報が提示されていないことに気付かないまま、先入観によってそれを補い、知った気になるわけだ。本作での叙述の罠は、並み居る折原作品のなかでも、とりわけ巧妙に仕掛けられている。
毎作品であまりにも多種多様な叙述トリックが使われるため、トリック巧者のように評されることが多いが、折原一の重要な本質はサスペンス作家であることに尽きる。
本作のプロット面に見える大きな特徴は、複数の謎が矢継ぎ早に浮かび上がることである。新潮文庫版の解説で、茶木則雄が「挙げていけば切りがないほど、何故、何故、何故……?マークの連続なのだ。」と表現しているように、白骨死体の身元、淳の行方、そして正体不明の“異人”など、際限のない謎のオンパレード(ここでもパッチワークのような手法が使われている)。また、過去においても、前述のように淳の人生には謎が多く存在する。少しすると判明する小さな謎から、物語全体を貫く大きな謎までを次々に物語内――テキストに記載することで、読者の興味を絶えず引き付ける。しかも、大きな謎のほうは次第にその質を変化させていく。特に“異人”に顕著だ。謎めいた存在であることを超えて、もはや不安、いや恐怖の象徴となっていくのである。本書をホラー小説と受け取る方がいてもおかしくはない。
解ける、解けずに残る、解けたと思っていたら解けていなかった――いったい何が真実なのか? そんな違和感の奔流で読み手を翻弄し、途切れることなく次々と不安を芽生えさせる。恐怖を醸成する。いつしか、謎解きの興味を凌駕するほどのサスペンス=宙ぶらりんにされる不安と恐怖の感覚が、作品内に充満していくのである。文中の言葉を借りるなら「正気と狂気の間の境界線の上をおそるおそる歩いて、かろうじて正気を保っている気分」に、あなたは陥るはずだ。
謎めいた冒頭部と最終局面の思いも寄らぬ真相の提示をつなぐ中間部分こそ、折原のサスペンスの書き手としての力量が存分に発揮される見せ場であるが、本書の“中途のサスペンス”は常軌を逸するほどの不穏な空気をまとっているといえるだろう。
多重文体、現実にあったB級事件、叙述トリック、サスペンス――これらの要素はそれぞれが独立したものではない。各々が影響を与え合い、混然一体となり、ひとつの作品を形作っている。そのいずれもが度を越えて過剰なのは必然である。この大長編の目指すものが、ひとつの事件の解明ではなく、ひとりの人物の人生のすべてを辿ることだからだ。これほどまでに膨大な要素が盛り込まれていても作品が破綻せずに成立するのは、そういったテーマと技法が骨の髄まで絡み合っているからにほかならない。稀代のサスペンス作家が、その時点でのすべてを注ぎ込んだ一作限りの異形の大作。それこそが『異人たちの館』なのである。
あの“異人”同様、現在に甦った本書は、時を経てまた新たな読者を連れ去って行ってしまうに違いない――折原一の生み出す奇怪な物語の世界へ。