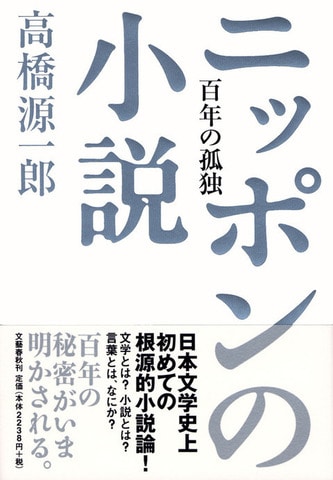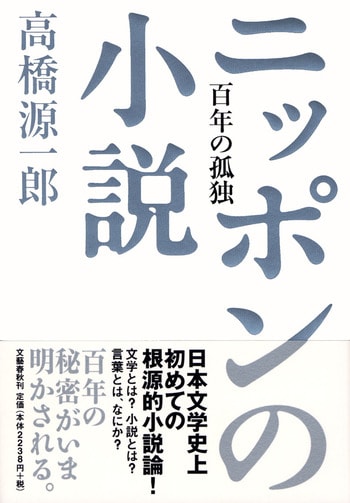文学もいいけどやっぱりまずは生活や社会が大事ですよね、という発言にも読めそうだがそうではない。この場合の「世界」もしくは「『外部』」とは、一言でいえば「わけのわからないもの」のことだ。言葉は、それらわけのわからないものを、わけのわかるものにしようとする。たとえば「死者」。我々は「死者」の思いなどほんとうはわからないのに、生者の都合で「死者」を語って、なんとなく「死者」に語らせたような気になってしまう。そういう意味で、言葉はいつもいくぶん暴力的だ。ところが文学は、そういう、本来はわけのわからないものをわけのわかるものにしてしまうはずである道具を使って、わけのわからないもののわけのわからなさをどうにかそのまま伝えようとする。もし高橋源一郎が、小説に何か「使命」があると考えているとすれば、それはまさに、そのようなややこしい役目を引き受けるということではないだろうか。
だから高橋源一郎はつねづね、二葉亭四迷の『平凡』、猫田道子の『うわさのベーコン』、中原昌也の諸作品など、「わけのわからなさ」をダイレクトに伝えるような「壊れた」作品に惹かれてきた。たとえば、肯定するにせよ否定するにせよひとまず「狂気の産物」と誰もがいいたくなるであろう『うわさのベーコン』について、それが“文学ではない”からこそ重要だとこの本で述べている。図式化すれば、「文学」と『うわさのベーコン』の関係は、世界のなかの「わけのわかる部分」と「わけのわからない部分」の関係に等しい。あるいは「生」と「死」の関係に。だから『うわさのベーコン』の「文章」について、そのわけのわからなさにおいて「『死者』に似ているといいたいのです」とすらいっている。
むろん、高橋源一郎自身は、そこまで徹底して「壊れる」ことはできない。わけのわからない部分に行きっぱなしでいることはできず、わけのわかる部分とわけのわからない部分をはてしなく往復しつづけるしかない。そこに高橋源一郎の栄光と悲惨がある、と断じることも可能だろうが、むろんその栄光と悲惨は、とりあえず生の側、正気の側にとどまりたく思う我々みんなが共有している。小説にせよ、人生にせよ、原理主義的に何かを全否定することは――『うわさのベーコン』のような稀有な、おそらくはきわめて大きな代償を伴う例外を除いて――何も生み出さない(これは高橋源一郎自身の発言の受け売り)。人生において我々がやることは、つねにどこか中途半端であらざるをえない。だとすれば、問題はどうやって“よりよく中途半端するか”だろう。小説とはもともと雑種的な、中途半端なジャンルであり、よい小説とはまさによい中途半端の実践例にほかならない。だが、べつに小説を書いたり読んだりせずとも、この本で高橋源一郎がやっているように言葉や制度の不自由さに敏感であろうとすることで(まあそこは、源一郎さんみたいにしなやかにやらないとアレなんですが)、我々は日々、よりよい中途半端を実践できるはずだ。その意味で、この『ニッポンの小説 百年の孤独』は、きわめて応用範囲の広い、大変に“実用的な”本なのである。