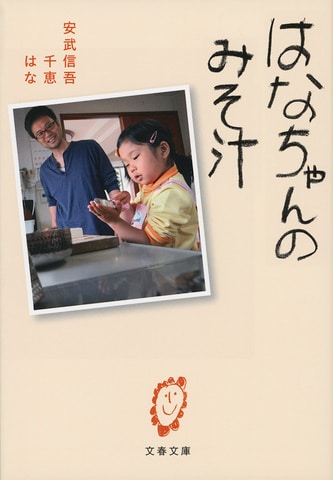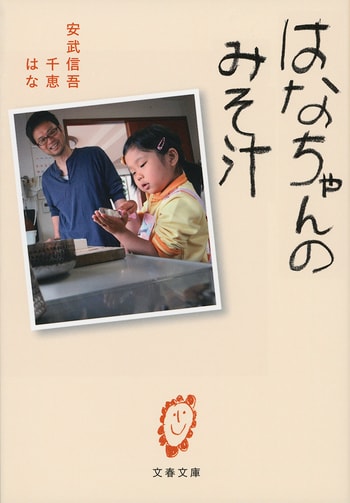仕事でトラブルがあった日は、励ましてくれた。
「きょうはむしゃくしゃする」と、夕食時、ぼくがビールを一気飲みすると、「はなだって、学校で嫌なことがあるんだよ。うちにはテレビやゲームがないから、クラスで友達の話題についていけない」
「そうか、すまんなあ」
「でも、大丈夫。ママの病気の苦しみに比べたら、どうってことないよ。パパもそれくらいのことでくじけたらいかん」
仲間たちが、本の出版を祝ってくれたときのことだ。
二次会で突然、腹痛が襲った。宴は夜遅くまで続いていたが、痛みは治まらず、はなも眠そうにしていたので、みんなに事情を説明して先に帰らせてもらった。自宅で布団に横になったが、痛みは激しさを増すばかりだった。徐々に意識が遠のいていった。それから先はよく覚えていない。気づいたときは、病院のベッドの上だった。病名は急性胆のう炎。
聞いた話によると、夜中、ぼくは七転八倒しながら「救急車を」と叫んでいたという。一一九番通報を受けた救急隊員に、はなが病状とこれまでの経過を細かく説明、はなが身内としてひとり救急車に同乗しての病院搬送となり、そして、ぼくはそのまま胆のう全摘出手術をしていた。それらすべてのことを知ったのは、手術を終えたあとだった。
ぼくが意識を取り戻したとき、ベッドの傍らにいたはなが、ワーッと泣き出した。
「独りぼっちになると思った」
ずっと不安だった気持ちを打ち明けた。
「ママみたいに、パパも死んじゃうかと思った。すごく心配した」
泣きながら、そう言って、怒った。
一夜明けた翌日、ぼくの意識が戻ったのを確認して、安心したのだろう。緊張から解き放たれたはなの涙だった。幼いはなにとっては想像できない“大事件”だったに違いない。
以前、雑誌の取材で我が家を訪れたノンフィクション作家の城戸久枝さんは、こんな父と娘の関係を「相棒のような親子」と表現した。ぼくに「生き直す力」を取り戻させるために、はながみそ汁をつくってくれた「あの夏の朝」から、父と娘は「相棒」になったのかもしれない。はなは、困難や悲しみを一緒に乗り越えていく相棒であり、ときには妻であり、命の恩人になってくれた。
ある日、本棚を整理していると、はなが小学四年生の冬休みに書いた作文が出てきた。作文の末尾は、「自分のいのちは自分で守る。それがママとの約束です」と結ばれていた。はなは、千恵が台所で伝えようとしたことの意味を、自分なりに理解していた。
「わたしは毎日、みそ汁とご飯を食べているので風邪をひかないし、重い病気にもなりません。ママ、わたしを産んでくれてありがとう。自分のいのちは自分で守る。それがママとの約束です」
たった五歳で母親と別れてしまったはなのために、「千恵と生きた証」を活字で残さなければならない――。そんな動機で本を執筆したのだが、作文を読み、肩の力がすーっと抜けていった。はなは、千恵と暮らした五年間のすべてを今も全身で感じながら生きている。この本を、そんなに慌てて読ませる必要はないような気がした。
読みたくなければ、読まなくていい。読みたくなったら、読めばいい。パパは、はなのおかげでおもしろい人生を送らせてもらっている。いま、生きていることが二人の幸せ。
千恵もきっと、そう思っている。
二〇一四年夏