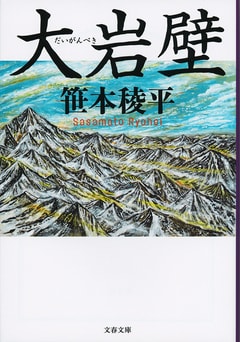新田次郎の小説を片っ端から読破していたのは、中学一、二年の頃だった。奥多摩の低山を中心に週末となると出かけて行き、登山のまねごとを楽しんでいた私にとって、気象や山の流儀を説いてくれる新田さんの小説は格好の教科書だった。
もっとも、私の登山熱は、わずか二、三年で冷め、次の興味関心へと移っていくのだが、そんな新田ワールドと登山に浸っていた時代の感覚はいまも体のどこかに残っていて、ふと、空を見上げたときに、あるいは地方の深山に入ったときにその匂いを思い出したりしている。
今回、笹本稜平さんの短篇連作を手にして、まず思い出したのは、その頃の山と自然の匂いだった。
もちろん、本小説には、新田次郎の時代にはなかった小道具がしばしば登場する。携帯電話である。携帯電話のGPS機能がストーリーの中で大事な役割を果たしたりするのだ。しかし言うまでもなく、それらはあくまでも小道具に過ぎず、笹本さんの小説の核をなすのは、やはり、山で生きる人の姿と自然である。
奥秩父の小さな山小屋「梓小屋」を父親から引き継いだ亨と、父親の古い友人で亨の右腕となって働くゴロさんが、「下界」から持ち込まれるさまざまな問題に直面し、そのたびに、自然の掟に問い、考え、解決していくというのがこの物語の軸だ。亨は、元電子機器メーカーの研究者で、一方のゴロさんは、バブル経済に踊らされ事業に失敗、還暦をすぎてもなおすすんでホームレス生活を送っている風変わりな老人である。
この物語の読みどころのひとつは、その二回り以上年上のゴロさんから、亨がさまざまなことを学んでいくことにある。ゴロさんの言動に亨はいたく刺激され、薫陶を受け続けるのである。
ゴロさんの言葉の裏には、常に「見てきた人」の諦観が潜んでいる。たとえば、ゴロさんは、こんなふうに語り落とす。
「そこがおれという人間の原点でね。人間だれでも素っ裸で生まれてきて、あの世へだって手ぶらでいくしかない。それが本来自然の姿で、金やら物やら名声やらを溜め込めば、それだけ人生が重荷になっていく」
だから、ゴロさんは、山小屋で働き出すようになっても、自由を満喫できるホームレスという生き方をやめようとしない。