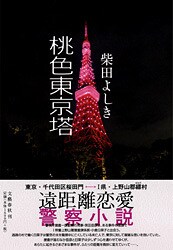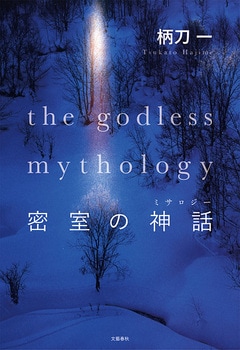作中では、二○○一年の九・一一テロがひとつのキーワードとなっている。今世紀最初の年にあのテロが起きてしまったという事実は、新しい時代に対する人々の希望を打ち砕くに充分だった。ノストラダムスの予言も取り敢えず外れ、終末論的な考え方は新世紀到来とともに廃れる筈だったのに、あの事件は余りにもヴィジュアル的に強烈すぎたということもあって、新世紀が絶望の時代であることを(恐らくは実行犯の本来の狙い以上に)象徴的に印象づけてしまったのである。実際、あの事件と、その結果として世界に拡大した戦乱とテロは、人間という生き物の不寛容と愚かさを露呈させた。
米国追従の姿勢を示しつつ、国土がテロに巻き込まれることからは何とか逃げ切った日本も、国力の衰退、格差社会の進行はもはや覆うべくもない。この書評を執筆している時期には、硫化水素を使った自殺が全国で流行していたが(本稿が活字になる頃には少しは収束しているだろうか?)、それが衝撃的だったのは、手軽な自殺の方法さえ見つかれば、躊躇なく死を選んでしまう人間がこんなにも多い――という事実を世間に思い知らせたからである。連鎖自殺そのものは二○世紀にもしばしば起こっていたけれども、例えばアイドル歌手の後追い自殺のような現象が、激流に身を投じるような一種のファナティックさを感じさせたのに対し、硫化水素自殺の流行は、もっと淡々としているぶん、人々と絶望のあいだの敷居が二○世紀よりも遥かに低くなっているのではないかと思わせる。たぶん人々は、アイドルの死のような物語や、世紀末的な終末論さえもはや必要とせずに自分の命を捨てられるのだ。
本書に登場するミステリアスな組織は、そういった絶望を糧にしている様子である。ここに描かれる絶望や、その温床となる社会的諸問題は、ふたつの世紀を架橋した世代が何とかしていれば手の施しようがあったかも知れないものばかりではないだろうか。リアリティがありすぎて怖い、と書いたのはまさにその点で、私たちが生きている現在という「因」と、作中の時代という「果」の照応は、「ならばどうやって未来を良い方向に変えられるのか?」という問いを、読者ひとりひとりに鋭く突きつけるのである。
第一話「秘密」が執筆されたのは一九九九年のことだが、長期に亘ってこの連作を書き継ぎながら、著者は自分の未来予想図が悪い方向に的中してゆくことに戦慄を覚えていたかも知れない。サラというヒロインは、そんな著者が絶望に陥りそうになりつつ、それでも未来の人間に託そうとする希望を象徴しているのだろう。