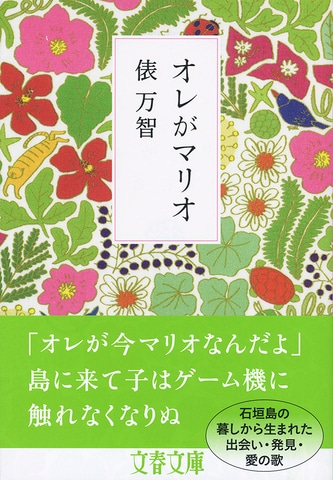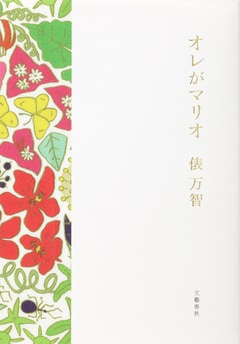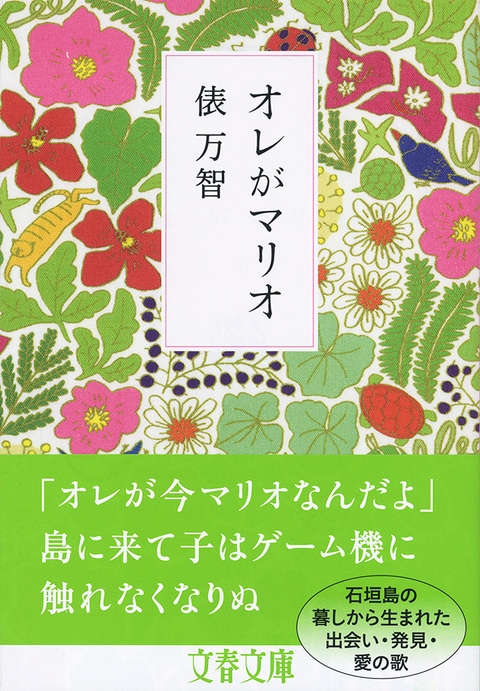
雨上がりの島は、生まれたばかりのように何もかも輝いて見える。その明るさは、俵万智さんの短歌を思わせる。
沖縄・石垣島に彼女がやってきたのは、東日本大震災の翌月、二〇一一年四月である。私はちょうどその一年前に移り住み、ようやく島の生活に慣れてきたころだった。仕事を通しての知人だった「俵さん」が、近所に住む「万智さん」になるなんて思ってもみなかった。
私が住んでいるのは、市街地から車で三十分ほどの小さな半島で、あちこちに牧草地やサトウキビ畑が広がる。集落には約五十世帯、百数十人が暮らす。おとなも子どもも姓でなく名前で呼びあい、地元の小中学校の行事には、保護者以外の人たちも参加するのが習わしだ。豊年祭や運動会など住民が顔をそろえる機会は多く、小学生の息子と二人暮らしの万智さんが地域の人たちと親しくなるのに、それほど時間はかからなかった。
とはいえ、戸惑うことも多かったはずだ。まず、子どもたちが前触れもなしにどっと家に遊びに来る。都会で子育てしていた万智さんは、ママ友同士で前もって「それじゃ、○日の○時に」「おやつは持たせるわね」といったやりとりをしたうえで子どもたちを遊ばせるのが常だったという。だから、アポなしの来訪に最初はかなり驚いたようだ(対策としては、カルピスを常備することが推奨される)。
それから、近所付きあいが濃密である。誰かの誕生日や記念日に飲み会が催されるのはもちろんだが、突発的な“持ち寄りパーティー”が頻繁に発生する。時には、イノシシやキジといった「島のジビエ」がふるまわれることもある。万智さんは誘われれば果敢に参加し、大いに楽しんだ。
こうした間柄なので、地域の人はよその子も真剣に叱る。初めてその光景を目にしたときには驚き、厳しい口調に滲む情愛に胸が熱くなった。「人の子を呼び捨てにして可愛がる島の緑に注ぐスコール」を読むたびに、それを思い出す。
自然に囲まれた生活は、「虫が大の苦手」「一日中、家から出なくても平気」という、根っからのインドア派だった万智さんを進化させた。そして、以前ならば「無理、無理~」と敬遠したに違いない、さまざまなアクティビティーに挑んだ歌も生まれた。
シュノーケリングした日は思う人間は地球の上半分の生き物
オヒルギの花ぼとぼとと落ちる午後 無言の川をカヤックで行く
遊んだあとの疲労感などではなく、ヒトが陸生動物であることや大自然の深い静寂が、大きな視点で捉えられている。作者自身が自然のなかへ飛び込んだ詠い方は、新境地といってもよいかもしれない。
万智さんが石垣島へ移り住んだとき、その決断の理由を聞いたことがある。彼女はずっと、子どもを育てるうえで二つのものが大切だと考えていたという。それは「豊かな自然」と「密接に関わりあう地域社会」である。石垣島を訪れたのはたまたまだったが、彼女は自分が求めていたものが二つともあることに心を動かされ、引っ越すことを決めたのだ。
旅人の目のあるうちに見ておかん朝ごと変わる海の青あお
この歌は、住み始めて比較的日の浅い時期に作られた。「旅人の目」には、見るものがすべて新鮮に映るが、その感激は時間の経過とともに失われてしまう。作者は、刻々と変わる海の美しさに深い喜びを覚え、「旅人の目」をできるだけ保とうと心に決める。つまり、この一首には、「旅人」として滞在するのではなく、しっかりと島で生活しようとする覚悟が詠まれているといえるだろう。エッセイ集『旅の人、島の人』(ハモニカブックス、二〇一四年)のあとがきには、「住んでみて初めてわかること、慣れてないからこそ驚けること。旅人でも島人でもない宙ぶらりんだから見えるもの」を綴った一冊であることが書かれている。