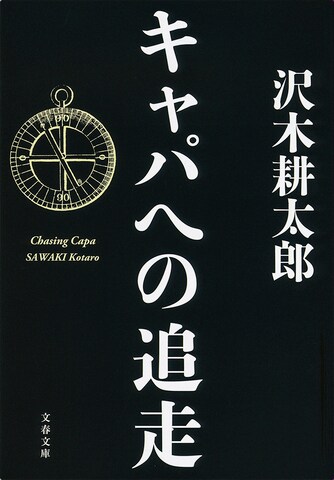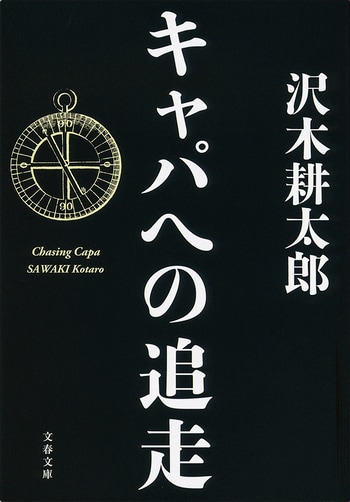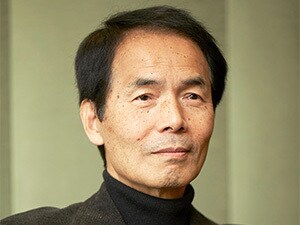小説そのものに私があまり信用をおかないのはそれが絵空事であるからだ。
彼はその街に3泊して次の街に出かけていったと言うのがフィクションであれば、それは作家の思いつきに過ぎない。
しかしリアルなドキュメントであればそれが真実だ。沢木を私が100パーセント信用していると言うのはそういう単純な背景によるのである。
私はもちろん、ロバート・キャパには会ったことがないが、彼がインドシナで地雷を踏んで死んだ瞬間に持っていたニコンのカメラは東京の写真展の会場で見たことがある。このカメラがもし手に入るならば私の持っている、数千のすべてのカメラと交換しても良いと思うようなそれは神々しいものだった。
キャパの弟さんであるコーネル・キャパにはやはり銀座の写真展の会場でお目にかかって、二言三言儀礼的な言葉を交わしたことがある。キャパとの付き合いとしてはこれで私は大満足だと思っている。
沢木がそれ以外のキャパの事は全部取材してくれているからだ。
観察した限りコーネルの奥さんは結構かかあ天下で、コーネルはちょっとかわいそうだなと言う気がした。
本書『キャパへの追走』最終章で、沢木が実際にキャパの墓所を訪問したときの挿話には私も心が痛むのである。雪の中を歩いて偶然というか、キャパの聖霊に導かれるように沢木はキャパの墓石に出会う。
文人墨客のお墓を展墓するのは文人墨客の趣味である。断腸亭・永井荷風なども晩年に近くなって、さまざまな人物の墓所をくまなくめぐっている。しかし沢木の場合はお墓巡りが趣味と言う風には見えない。
沢木はロバート・キャパと言う一つの星が生まれてから、流れ流れてインドシナで天国に登り、その遺骨が葬られた先のニューヨーク郊外まで極めてクールに追跡しているのである。
その意味で本書の最終章「ささやかな巡礼」は短いが手に汗握る活劇物語である。
そこで沢木は、コーネルも含めたキャパの家族までも、ユダヤ人の名前がありながら、キャパという通称の姓に改めている事について考えを巡らす。エンドレ・フリードマンという立派なユダヤ人の名前を持っていながら、いかにも軽佻浮薄なロバート・キャパというアメリカンの名前にしてしまったのは 、彼独特の広告代理店的活動の天才というところによるのであろう。その人間の名前と言うのは単に社会的にその時間空間を生きるためのかりそめの命名に過ぎなかったということを私は痛感する。
私は1970年代にオーストリアのウィーンに住んでいたが、こういう事は割とよくあった。ウィーンの中央墓地の一番市内に近いところの最初のエントランスはユダヤ人墓地である。当然ながら十字架のシンボルは見られない。
ここは最も人気のないところで、私は一人になるためによくこのユダヤ人墓地を訪れた。草むしてもう誰も手入れをすることのないような墓地には〈1945年アウシュビッツで死去〉といった文字列が無数に並んでいる。そこに遺骨があるかどうかはこの場合問うべきではないのだろう。