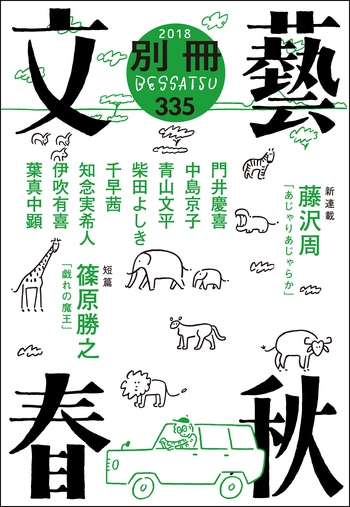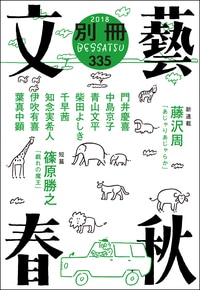
「おおい! ここだ!」
先に来て待っていた父が、大きな掌を挙げた。私は父よりずいぶん長生きして、おばあさんになった。もはや父の知る姿とはかけ離れている。なのに父は、迷わず私を見つけた。新生児室の前で、「あれが俺の子だ」と泣いたあの日のように。
「おまえはほんっと、よか人生ば送ったなあ」
天国の居酒屋で、私は父とお酒を呑む。乾杯のときは少し緊張した。父と呑むことなどもうないと思っていたから。
まずビール。つまみは鯨ベーコン、おばいけ、マカロニサラダ。煮豆腐も欠かせない。魚の煮汁で煮つけた豆腐は、口に入れた瞬間とろんと甘辛くとけていく。マヨネーズの添えられた鰯フライも、父はざくざく好い音を立てて食べる。生きているあいだもこうやっていっぱい食べてくれたらよかったのに。呑むばっかりじゃなくて。悲しくなる。いつだって父と会うと、気持ちが揺れてしまう。
父はにこにこして、夢の中の父みたいに優しい。
「文句なし、百点満点の人生やったろ?」
私は結局、死ぬまで父の写真を家に飾れなかった。父の思い出がいたるところにしがみついて痛かった。そう思うけれど言わない。
「うん、いい人生だった。お父さんのこと、嘘も本当もいっぱい書いてごめんね」
「そうだぞ。ハイ、モデル料百万円。はよ寄越さんか」
「なに言ってるの。書かずに私の頭がおかしくなったら、お父さんも困るでしょ」
「親を脅すなんてとんでもない野郎だ」
ワッハッハ、と父が笑う。
父が笑っているとうれしい。父の笑い声がまた聴けてうれしい。
父と私のいる席からは海が見える。どこまでも続く、凪いだ海。釣り人が糸を垂らし、子どもたちが浜辺で水遊びをしている。天国に海があるなんて知らなかったな。感心しながら私は、しめさばと芋焼酎を注文する。「さばは危険だぞ」と父が言う。「サーモンもだ。寄生虫がな……」何十年経っても同じことを言う。
生きている父と最後にお酒を呑んだのはいつだったろう。
亡くなる前の数年は、家族の誰もが父の飲酒に神経を尖らせていた。呑むか呑まないか、それが父の属性すべてになった。父が呑んでしまうと、皆が絶望し怯えた。呑まずにいられたとしてもハラハラしっぱなしで、再び呑んだら絶望だと怯え続けた。
父が呑まずにいられなかった理由に思い当たったときにはもう、父はこの世にいなかった。
天国の居酒屋。そこではいくら呑んでもほろ酔い程度、罵声も暴力も貧困もない。誰もが再会を悦び、愉しそうに語らっている。
〆は勿論、長浜ラーメンだ。運ばれてきた細麺を私は瞬く間に平らげる。そんな娘を父はまぶしそうに眺めている。
「ラストオーダーのお時間です」
店員さんが告げに来る。その場所を去らねばならぬときがやってきたのだ。
お腹いっぱい。けれど私は「硬い玉いっちょう!」と威勢よく替え玉をする。「よう食うなあ」と笑う父の顔が見たいから。
替え玉が運ばれてくるまでのあいだ、私は父にずっと訊きたかったことを訊く。
「私たちにしたことを、悔やんだ?」
短く答えた父の大きな掌を、私はそっと握る。私たちの手はとてもよく似ている。
もしも新しい命になることができたら。私はまた、父の子として生まれたい。次の人生ではもっとうまくやれると思う。
替え玉を汁まで味わい尽くし、私と父は天国の居酒屋を後にする。
いちき・けい/一九七九年、福岡県生まれ。東京都立大学卒。二〇一六年「西国疾走少女」で第一五回「女による女のためのR-18文学賞」読者賞を受賞。一八年一月、受賞作を含む単行本『1ミリの後悔もない、はずがない』を刊行しデビュー。現在、バンコク在住。