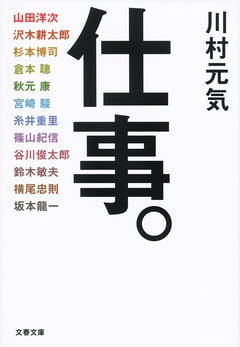川村元気の小説を読むたびに、居心地が悪くなる。というか、妙な胸騒ぎと焦燥感に似た(焦燥感そのものなのか、似て非なるものなのか、よくわからない)感情に揺さぶられて、落ち着かない心持ちになるのだ。だからといって、途中で閉じるわけでも、読みかけのまま本棚にしまい込むわけでもない。それはできない。よんどころない事情で読書を中断することはあっても、その事情から抜け出せればまた、急(せ)かされるように手を伸ばし、ページをめくっている。夢中になる。物語から触手が伸びて、わたしに絡みつく。絡みつかれれば、その世界に引きずり込まれてしまう。本読みにとって至福の一時だ。至福の時が流れ、読み終える。本を閉じる。現実に戻るためにしばらく時間を費やす。
ここまではいつもと変わらない。本はおもしろい。わくわくする。心に染みて、新しい世界を教えてくれる。少なくともわたしにとっては、凡庸なわたしの一日一日を輝かせてくれる、暗みに隠れていた諸々を照らし出してくれる光そのものだった。
川村作品もそういう作品群の一つのように感じられる。読んでいる間は、感じられるのだ。おもしろくて、わくわくして、心に染みて、未知のどこかに誘ってくれる、と。けれど、読み終えてしまうと、楽しいだけではない、高揚するだけではない、そんなものとは無縁の情動がゆっくりと頭をもたげる。読書の喜びや楽しさを、音を立てて砕いてしまう。何なんだ、こいつはと、わたしは目を剥(む)く。名がわからない。
胸騒ぎ、焦燥感、苛立ち、不安、恐怖……。どれも含んでいるようで、まるで違う気もする。自分の感情であるのに、言い表すことも制御することも難(かた)い。
不気味だ。得体のしれない異形(いぎょう)が立ち上がるように、不気味だ。怯えてしまうほどに。
小説家としての川村はいつも、人に向かい人を問い続ける。余命を告げられた男の死に様ではなく生き様を執拗に追い、金と人との関係を嗤(わら)うのではなく克明に刻もうとする(まったくの余談だが、昔、レタスという名の猫を飼っていた。人語はしゃべらなかったが、解している雰囲気はあった)。
『世界から猫が消えたなら』も『億男』も話題作となり、たいそうなヒット作となり、多くの人々に読まれた。読まれ続けている。
大丈夫なのかなと、思っていた。
川村作品に対する感動や称賛の声を聞き、書評を目にする度にわたしは妙な違和感を覚え、身を震わせていた。
みんな大丈夫なのかな、怖くないのかな。揺さぶられないのかな。読み終えた後、自分が当たり前だと信じ切っていたものがすっぽり抜け落ちる感覚を味わわないのかな。自分の奥底に開いた小さな穴に気付かないのかな。そこから何が零(こぼ)れ落ちているのか見ようとしない自分を気取(けど)らないのかな。
こんな物騒で厄介な小説を手放しで褒めていいのかと、妬心(としん)を差し引いても残る強い困惑をわたしは身を震わせて、顔を顰(しか)めて、生唾を吞み込んで……忘れることにした。わたしは君子ではないが、危ういものに近づかないだけの分別は持っている。この年になって、自分の足元を崩してしまうような存在――それが本であっても人であっても他の何かであっても――なんてまっぴらだ。わたしはもともと安定志向の強い人間だ。地位も名誉もお金も、人並外れて好きだけれど、平凡で退屈で、だからこそ揺るがない日々が何より好きなのだ。川村元気の小説は、そこに罅(ひび)を入れる。危ない、危ない、近づくな。
理屈ではなく勘が告げてくれた。
で、わたしは自らの勘に従った。川村作品を本棚の奥に、母校の『創立百周年記念誌』と『園芸百科』と並べて仕舞い込んだのだ。ちょっとだけ、安堵できた。
なのに、わたしはまた読んでしまった。
『四月になれば彼女は』。何という小説だろうか。
読み出したら止まらなくなった。けれど一気に読み通すこともできなかった。一気読みを許すような作品ではないのだ。何度もページをめくれなくなり、前に読み進めなくなり、それでも読むことから逃れられない。逃れたいと思わせないのだ。川村の小説の触手はさらに長く、強く、甘く、力を増していた。絡みつかれれば逃れる術はない。
九年ぶりの手紙から始まる。
いまわたしは、ボリビアのウユニにいます。
真っ白な塩の湖のほとりにある街。標高は三七〇〇メートル。空気はうすいけれども澄んでいて、水色の空にはぷっくりと膨らんだ雲が浮かんでいます。ここの塩湖は雨が降ると、水が浅く溜まり鏡のようになります。その鏡は天空を映し、世界すべてが空になるのです。
かつての恋人から届いた手紙は、異国の地を美しく描写していた。過ぎ去った時間、若いころの淡く苦い恋、見知らぬ国の情景、優しい言葉の数々。そんなものに騙されてはいけない。騙されて、これは切ない喪失と再生の物語などと思ってはいけない。これもやはり、異形の物語なのだ。飾り愛でるためのガラス細工ではなく、人の存在と関わりを切り裂くための刃(やいば)なのだ。ガラスも刃も光を弾き、輝きはするけれど、用途はまるで違う。
全てが空になった世界で、人はどこに立つのか。
本物の孤独とは、自分の立つ場所を見失うことではなく、見失うことに向かい合えないことではないのか。失ったところから始まる物語がゆっくりと動き出す。
恋人がなぜ手紙を書いたのか。受け取った男は思い出を手繰(たぐ)りながら、何を追いかけようとするのか。何に背を向けてしまうのか。読み進めていけば、音が聞こえる。人という生き物の手から零れ落ちるものの音だ。音が響くたびに、刃が突き刺さる。
ハルも藤代も弥生も、タスクも中河も大島もみんな切り裂かれ、彼ら彼女たちが刃そのものになる。わたしは息を詰め、おののくしかない。
川村自身はどうなのだろうか。
残酷な物語だ。腑分けするように、人の心を解き開いていく。かつて誰かを愛したはずの美しい記憶を解体していく。今、ここにある孤独を記憶の底から引きずり出す。そういう物語を生み出したうえで、なお、人と人が生きていく道を探ろうと川村は足掻(あが)いているのだろうか。ハルを完全に失った。それでも藤代は生きていく。生きていくために何が必要なのか、川村自身が掴もうと足掻き、指先に触れたものを何とか形にしようと、また足掻く。その軌跡がこの物語なのだろうか。川村はおそらく、自分の書く物が否応なく異形となると、十分に承知していたのだろう。人を癒し、涙を誘う物語など端(はな)から拒んでいたのだ。刃を内包しつつ、異形を示し、人に迫る。そういう書き方をする限り、刃はもっとも深く作者を斬り付けるとも承知していた。
読まない方がいいと思う。
軽やかに生きていきたいと望む人は、すてきな恋をしたいと願う人は、すてきな恋をしていると公言できる人は、誰かが愛して、幸せにしてくれると信じている人は、読書は楽しくてためになると口にする人は、この本を読まない方がいいと思う。残酷なシーンなど一つも出てこない最上等の残酷な物語、わたしの、あなたの、人間の正体に肉薄する物語。うん、やっぱり怖い。怖すぎる。
失いながら求め続ける者に容赦なく刃を向けながら、なお、人から離れず人のみが作り出す希望を捜す。川村元気という作家は深手を負ったまま、まだ、そこに向かって書き続けるのだろうか。わたしにはわからない。ただ、怖いから、わからないから知りたいとは思う。
川村の新作を、私は恐れながら待っているのだ。