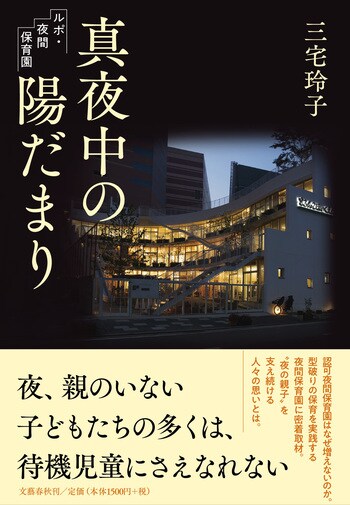「待っとったとよ」
夜間保育園に入る直前、母子寮を出た彼女は子どもとふたり、アパートに暮らしながらキャバクラで働いていた。
「キャバクラがね、託児所みたいなの、もってるんですよ。そこに子どもを預けてました。まだこの夜間保育園に入れるようになる前ですよ。1歳になってなかったですもんね。託児所っていっても、キャバクラを経営しとう会社の事務所みたいなとこでした。衝立ての後ろで5、6人、赤ちゃんが寝かされとうみたいな。おっぱいがパンパンに張るんですよね。それでお店が終わって託児所に飛び込んで、おっぱい飲ませて、はー、楽になった。そんな感じでしたよねえ」
夜間保育園に入園したての頃の真弓は、荒れに荒れていた。自転車を置き場に停める際のルールを守らず、それを注意されるとふくれる。登園時間を守らないし、そもそも毎日は登園しない。保育士の間からは「あのおかあさん、ベビーホテルと勘違いしとっちゃない?」と不満の声が上がった。
もつ鍋を皿にとりわけながら、真弓が話した。
「でもね、半年くらい経ったときやったかなあ、理事長先生から話しかけられたんですよ。『あなた、あのとき泣きながら電話してきたおかあさんやろ? いつ入園するかって、待っとったとよ』って。わたしなんかのこと、覚えてくれてたんやなあって、ありがたくて」

わずかひと言が、真弓の保育園への距離を縮めた。それ以来、真弓は時折事務室に立ち寄っては、生い立ちや夜の仕事のことなどをぽつりぽつりと話すようになった。
1年ほど中洲に勤めた真弓は、中洲を卒業して昼の仕事に切り替える決心をした。保育士から、子どもが小学校にあがったときのためにがんばって今のうちに、と励まされたのがきっかけだった。
「やっぱりね、子どものためにって思うやないですか。今の自分、最悪って思うし。だって、中洲でもわたしなんか、若くもないし、お店でママになれるわけでもないし、中途半端ですよ。なんか、客観的に見て、ヤバいなあって思うんですよね」
電話オペレーター、ベンチャーの投資会社のセールスなど、新しい仕事に就いては辞めることを繰り返し、短い場合は1週間、長くても半年続いたかどうか、だった。