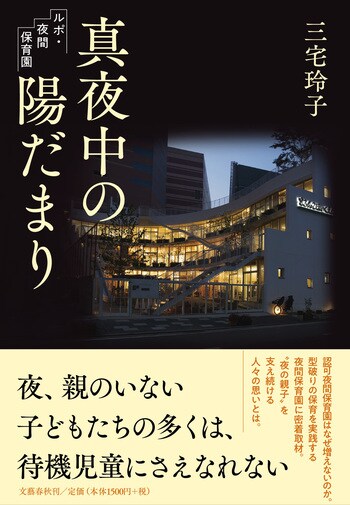「あのおかあさんはそういうやさしいところのある人なんですよね。ほんと、がんばってほしいなって思います」
そう職員はつぶやいた。
だが、収入が下がっても、家賃の高いマンションから市営住宅に移るのをためらったり、昼間の飲食店でのパートのような地道な仕事を避けたり、真弓はなかなか生活を軌道に乗せることができずにいた。
ある夜、保育園からの帰り道、息子を前かごに乗せた自転車を押しながら彼女がぽつりと言った。
「昨日、夢を見たんですよ。この子とふたり、切り立った山の崖っぷちみたいなところを自転車に乗ってるんですよ。ぐらぐらして、ちょっとでもバランス崩したら、崖から転がり落ちるみたいな。そんな夢やったんですよね。まるで今のわたしたちをあらわしとうみたいでしょう」
博多駅に続く大通りを車の行き交う音が遠くに聞こえる。地味なスーツの上に黒いコートを羽織った背中は、頼りなげだ。
「でもね、2年後にはうちの子も保育園を卒業するやないですか。それまでに、生活をちゃんとしたいんですよね。そうでないと、保育園から離れたら、わたし、もう、すごく困ると思うんですよね。この子を預けるためっていうより、自分が精神的に助けてもらっとうけん」