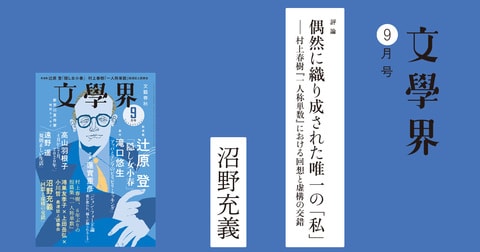1
「他には?」
「〈ギャル・イン・キャリコ〉の入ったマイルス・デイビス。」
今度は少し余分に時間がかかったが、彼女はやはりレコードを抱えて戻ってきた。(『風の歌を聴け』)
村上春樹という新人作家の『風の歌を聴け』という小説を読んだのは1979年、私が大学4年の秋だった。手元にある単行本の奥付を見ると「1979年7月25日第一刷発行 1979年10月16日第四刷発行」となっている。たしか「ポパイ」のブックレヴューで「ミントガムを噛みながらビールを飲んだような読後感」とかいう、今にして思えば笑っちゃうような形容で紹介されていて、それを読んで買った記憶がある。時代ですねえ。
『風の歌を聴け』のテーマ・ミュージックがビーチ・ボーイズの「カリフォルニア・ガールズ」だということは誰もが認めるだろうけど(大森一樹監督による映画のテーマ曲もこの曲だった)、ジャズについては、「僕」がレコード屋で「〈ギャル・イン・キャリコ〉の入ったマイルス・デイビス」を買うこのシーンが印象に残った。そのころの私はすでにいっぱしのジャズ・ファンを気取っていたのだけど、恥ずかしいことにそのアルバムを知らず、いろいろ調べてそれが『ザ・ミュージング・オブ・マイルス』という、1955年に録音されたワンホーン・カルテット作だということを知ったのだった。マイルスの作品の中ではあまり知られていないものの一つだけど、とてもチャーミングでキュートな演奏が聴ける愛すべきアルバムだ。
大学がある四谷から電車ですぐの千駄ヶ谷に「ピーターキャット」というとてもいい雰囲気のジャズバー(というにはけっこう広かったけど)があり、ジャズ・バンドの仲間に連れられて何度か行ったことがあった。その店は、髪の短いマスターと、奥さんらしき小柄で細い女性がやっていたのだが、そのマスターが「あの『風の歌を聴け』を書いた村上春樹」だ、という話を誰かに教えてもらったとき、私は驚きつつも深く深く納得した。なんだジャズのプロだったのか! そりゃあ『ザ・ミュージング・オブ・マイルス』だってよく知っているに決まってるよね。
そしてその翌年、村上春樹の2冊目の単行本『1973年のピンボール』が出る。私はさっそく単行本を買い求めて、そう長くない物語の中に、たくさんのジャズ、それも「古いジャズ」が登場することにびっくりした。引用してみよう。
僕たちは一時間ばかりバックギャモンをしてからゴルフ場の金網を乗り越え、誰も居なくなった夕暮のゴルフ・コースを歩いた。僕はミルドレッド・ベイリーの「イッツ・ソー・ピースフル・イン・ザ・カントリー」を口笛で二回吹いた。(『1973年のピンボール』)
カセット・テープで古いスタン・ゲッツを聴きながら昼まで働いた。スタン・ゲッツ、アル・ヘイグ、ジミー・レイニー、テディ・コティック、タイニー・カーン、最高のバンドだ。「ジャンピング・ウィズ・シンフォニー・シッド」のゲッツのソロをテープにあわせて全部口笛で吹いてしまうと気分はずっと良くなった。(同)
僕は窓を閉め、カセット・テープでチャーリー・パーカーの「ジャスト・フレンズ」を聴きながら、「渡り鳥はいつ眠る?」という項を訳し始めた。(同)
仕事は峠を越し、僕はカセット・テープでビックス・バイダーベックやウディ・ハーマン、バニー・ベリガンといった古いジャズを聴き、煙草を吸いながらのんびりと仕事を続け、一時間おきにウィスキーを飲み、クッキーを食べた。(同)