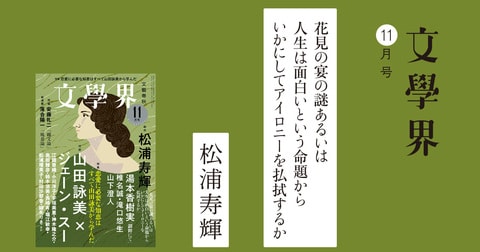序章 負い目から小説家の王位へ
「目じるしのない悪夢」
村上春樹には、自ら「一種のイグザイル(故郷離脱、という表現がいちばん近いだろうか)」と呼ぶ時期がある。文字どおり、日本を離れていた時期だ。一九八六年の秋に日本を出て、ギリシャ、イタリア、イギリスでの滞在を経て、プリンストン大学から客員研究員に呼ばれたことをきっかけに、四年ほどアメリカに滞在する合計「七年か八年のあいだ」にほかならない。じっさいに、この「イグザイル」を終えて村上春樹が帰国するのは一九九五年の五月であり、その直前に立てつづけに日本を襲う「阪神・淡路大震災」(九五年一月)と「地下鉄サリン事件」(九五年三月)が帰国にむけて小説家の背中を押したことは想像に難くない。とはいえ本人は、「そのイグザイルの最後の二年ばかりのあいだ、私は自分がかなり切実に「日本という国」について知りたがっていることを、いささかの驚きとともに発見した」と述べていて、それもまたウソではないと思われる。そして帰国後初めての大きな仕事が『アンダーグラウンド』(一九九七年)というインタビュー集として上梓された。
わたしがずっと理解できずにいたのは、村上春樹をして『アンダーグラウンド』に向かわせた動機である。表向きは、本人の言うとおり、長年にわたる「イグザイル」を経て、「日本という国」について知りたいという気持が高まったからだろうと思う。インタビューを通じて、じっさいに何が起こったかに向き合えば、かなり特殊な角度からではあるが、「日本という国」についてアプローチすることになるだろう。あるいは、大江健三郎に「戦後文学者たちの《能動的な姿勢》をとらぬという覚悟からなりたってい」ると批判されたことにも、いくらかは関係しているのかもしれない。だがそれらは、もっともらしい理由にはなり得ても、わたしには、この小説家を『アンダーグラウンド』に向けて突き動かした深い動機には思われなかった。
それが腑に落ちたのは、『アンダーグラウンド』をはさんで、特に長篇小説が変わったように感じられたこと、そして『アンダーグラウンド』が小説家としての負い目の表明になっていて、そのふたつが関連しているのではないかと思い至ったときである。『アンダーグラウンド』の巻末に付された「目じるしのない悪夢」をていねいに読むことからはじめるのは、そのためにほかならない。