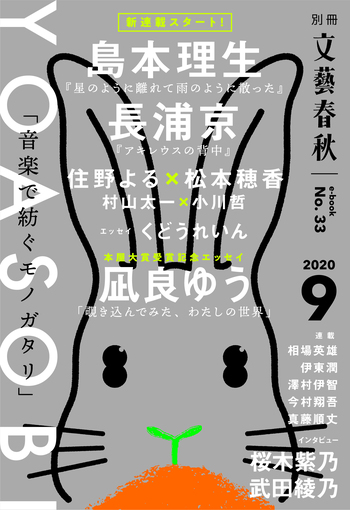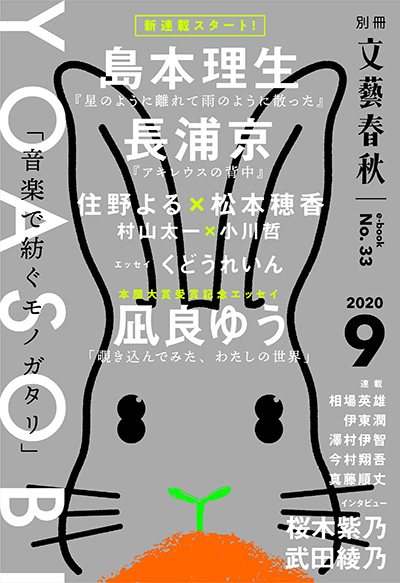
1
「しもみながれ? したつる?」
スーツ姿の警視正が、タブレットの名簿にある下水流悠宇の名を見ている。
「いや、おりだな」
警視正が視線を上げた。
「はい。おりづるゆうと申します」
悠宇は頷いた。
「よくご存じですね」
「大学時代の友人が鹿児島出身でね。そいつの実家に遊びに行ったとき、店の看板や通り沿いの表札にこの名を見かけたんですよ。もう二十年以上前のことだけれど。君の親御さんもそちらの出身ですか?」
「祖父が鹿児島県出水郡の出身です」
「そうですか。警視庁捜査三課七係、下水流主任。確認しました。きれいな響きの、いい名字ですね」
警視正が笑う。
「ありがとうございます」
悠宇も大きな目を細め、微笑みを浮かべると小さく頭を下げた。
「私は――」
悠宇の隣の四十過ぎの男も口を開く。
「わかるよ、間明係長」
警視正はあっさりいうと、タブレットに映っていた名簿を閉じた。
「定刻通り来ていただいたのに申し訳ないが、担当者が準備に少し手間取っているようでね、そこのミーティングルームで待っていてもらえますか」
悠宇と男は頷きドアを開いた。
警視正が去ってゆく。部屋は狭く、小さな窓がひとつ。折りたたみ式の長テーブルと椅子が並び、さながら取調室のようでもあった。
警察官のふたりは殺風景なこんな場所には慣れている。
千代田区霞が関二丁目、中央合同庁舎第2号館内。警視庁本庁の裏手にある警察庁庁舎。
「本庁も薄汚れていますけど、ここもかなりのものですね」
ベージュのコートを脱ぎ、悠宇は低い天井を見上げた。
節電のため廊下は薄暗く、この部屋もLED電球とは思えないほど照明がぼんやりしている。エアコンの送風口から生ぬるい風は出ているものの、薄ら寒い。
「ここはじめてじゃないだろ?」
間明も年季の入ったトレンチコートを脱ぎながらいった。
「私? 三回目くらいですかね? 地検には呼ばれますけど、こっちは特に用はないですから。係長は最近よく課長と一緒に呼び出されてますよね」
「いろいろプレッシャーかけられることが多くてさ。でも、驚いたよ」
「何がですか?」
「おまえも愛想笑いができるんだな」
間明がさっきの警視正とのやり取りを皮肉る。
-
『圧勝の創業経営』
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募締切 2025/07/26 00:00 終了 賞品 『圧勝の創業経営』5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。