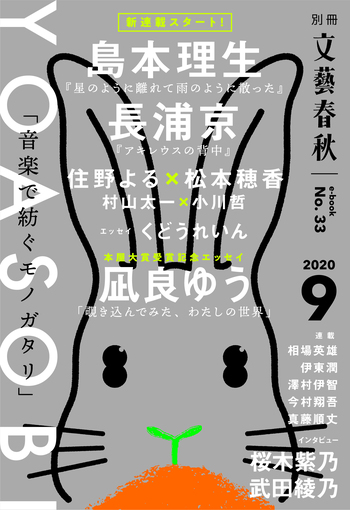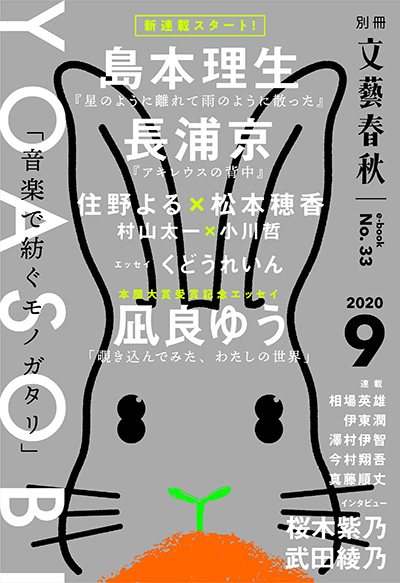
(10)
「管内にこんなウマい店があるとは知りませんでした」
仲村の目の前で、関が二枚目のせいろから勢いよく蕎麦をたぐった。
「死んだ親父が機嫌の良いときに連れてきてくれた」
「たしかに、富丘団地からすぐですね」
恵比寿にある環の会社から牛込署に戻る途中、仲村は関を伴って大久保通りに面した若松町の蕎麦屋に立ち寄った。
その古い店は富丘団地の東側にある。かつて仲村が住んでいた三三号棟から歩いて一〇分程度の距離だ。
数年ぶりに店の前まで来ると出汁の香りが漂い、仲村の食欲を刺激した。
「今度はセット物をオーダーしますよ」
忙しなく蕎麦をすすり、関が言った。中堅刑事の視線の先には、手描きのイラストとランチのメニュー表がある。
〈ミニ丼(カツ、親子、海老天)& たぬき蕎麦・もり蕎麦 八七〇円〉
「俺の場合、両方大盛りにしますけどね」
口元に付いた蕎麦つゆを手の甲で拭い、関が笑った。
「それじゃセットの意味ないだろ。カツ丼とたぬき蕎麦、二品注文するのと同じだ」
「それもそうっすね」
仲村は天もりを平らげ、蕎麦猪口に蕎麦湯を注いだ。
周囲のテーブル席には、近所の国立病院の医師や看護師がいる。病院から一分もかからぬ距離にあるため、昔から関係者が頻繁に利用していた。ほかのテーブルは、町内の年寄り連中で混み合っていた。何の変哲もない街場の蕎麦屋だが、手打ち蕎麦と揚げ物、柔らかい出汁巻き卵は昔から仲村にとってのごちそうだった。
「化石みたいな店だが、居心地はいいし安い。よかったら署の連中と使ってくれ」
濃い目の蕎麦湯を一口飲み、言った。
仲村は厨房に目をやった。仲村の知る先代店主は数年前に亡くなり、今は二代目が毎日蕎麦を打ち、夫人が天ぷらや丼物を作り、二人のパートが接客している。
「せいろが二〇〇〇円もする高級店じゃおちおちお代りもできないからな。この店は昔から貧乏人の味方だよ」
-
『圧勝の創業経営』
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募締切 2025/07/26 00:00 終了 賞品 『圧勝の創業経営』5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。