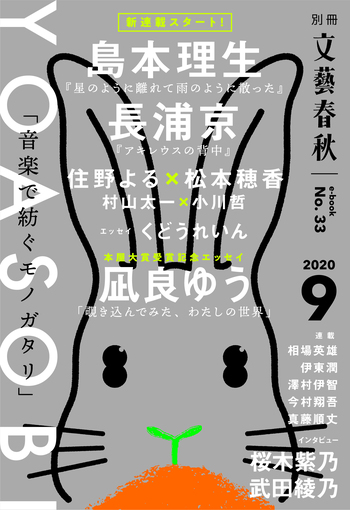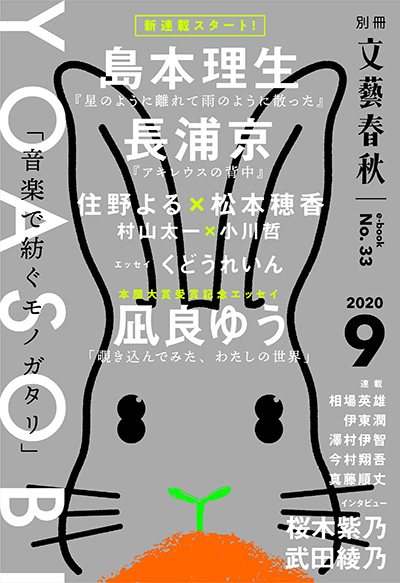
仲村が注文した天もりは、季節の野菜と大振りのエビが山盛りで一〇〇〇円だ。麻布や神田辺りの名店に行けば、確実に三〇〇〇円以上は取られる。
子供の頃、父は給料日のあとや競馬で勝ったときに、母と仲村をこの店に連れて来てくれた。この蕎麦屋で板わさ、天ぷらの盛り合わせをアテに酒を飲むことを楽しみにしていた。
あの頃は、仲村と同年代の子供たちも大勢いた。外食自体が贅沢な時代だった。大して広くない店では、どのテーブルでも家族連れが食事を楽しんでいた。
だが、今は様子が一変した。病院のスタッフを除けば、客の大半が老人だ。若松町は、江戸時代には柳生但馬守宗矩の邸宅があった武家屋敷の一帯で、当時の地割の名残りを留めつつ、今は住宅地となっている。ただ、都心ということでマンションやアパートの家賃は高く、残っているのは古くからの住人である年寄りばかりだ。働き盛りの現役世代はほとんどおらず、街の交流場所として蕎麦屋は老人たちの昼の憩いの場に様変わりした。
「カッちゃん、久しぶりじゃない」
突然、名前を呼ばれた。年老いた女将が厨房で笑みを浮かべていた。
「ご無沙汰しています」
「あんた、刑事さんよね。この辺りも物騒なんだから、なんとかしてよ」
耳が遠くなったのか、女将は存外に声が大きい。刑事という言葉に反応し、周囲の客たちの視線が集まる。口の前に指を立て、仲村は女将のいる厨房に向かった。
「刑事は嫌われ者なんだ。大っぴらに言わないでよ」
厨房の入り口まで行くと、仲村は女将の耳元で告げた。
「あんたはちゃんとした警察官になった。でもねえ……」
女将が顔をしかめ、厨房の棚にある新聞を手に取った。折り畳まれた朝刊の社会面には、富丘団地殺人事件に関する記事がある。仲村は声のトーンを落とし、女将に尋ねた。
「藤原さん、この店にも来ていたよね?」
被害者の名を出すと、女将の顔が曇った。
「月に、二、三度かな。ガラの悪い人たちといつも一緒にね」