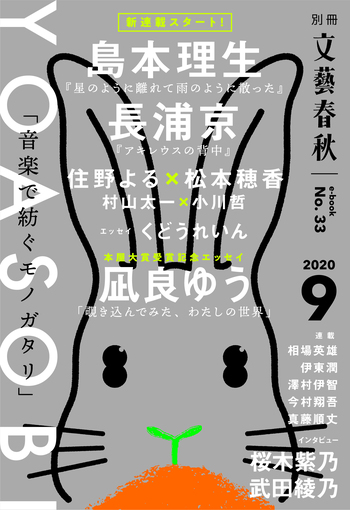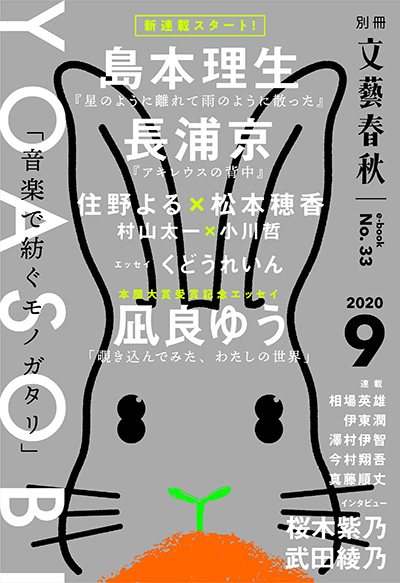
女将は自らの頰を人差し指でなぞり、顔をしかめた。顔に傷のある連中、つまりヤクザ者ということだ。やはり藤原はずっとマル暴との付き合いがあったのだ。
「喧嘩していた? それとも和気藹々だった?」
「和気藹々ね。いつも偉そうな顔して、若い人たちにお酒飲ませていたから」
「わかった。ありがとう」
厨房脇からテーブル席に戻る。
「なんかありました?」
「被害者はこの店の常連、それにマル暴と一緒だった」
関の眉根が寄る。
「マル暴絡みの怨恨ですかね?」
「和気藹々、楽しく飲んでいたそうだ。まあ、その辺りは他の鑑取りの連中に任せよう」
蕎麦湯を猪口に注ぎ足しながら言ったとき、テーブルに置いたスマホが振動した。
「若様だ」
「野沢管理官ですね」
液晶画面にキャリア警視・野沢の名前と番号が表示された。
「蕎麦湯くらいゆっくり飲ませろ」
鈍い音を立てるスマホを横目に、仲村は猪口を傾け続けた。
「では再生します」
紺色のウインドブレーカーを羽織った捜査支援分析センターの若手捜査員がパソコンのエンターキーを叩いた。
仲村は牛込署会議室の壁に目をやった。小さなプロジェクターから青白い光が放たれ、スクリーン代わりの白壁に喫茶店の様子が映し出された。
「窓際の奥にいるのが被害者の藤原さん、背中は松島氏です」
若い捜査員が告げる。一方、仲村の右隣に陣取る野沢管理官は長い足を組み、不機嫌そうにスクリーンを見つめる。
捜査本部に入るなり、連絡が遅いと野沢に怒鳴られた。警察組織に年齢の上下は関係なく、階級がものをいう。巨大なピラミッドの底辺にいるのが仲村や関、頂上付近の限られた層に属するのが野沢だ。ずっと年下の上司だが、連絡には即座に応えるよう求められる。
左隣に座る関が目線で大丈夫かと尋ねると、仲村は鷹揚に頷いてみせた。
「ここからです」
若手捜査員の声に、仲村は壁の映像に目を凝らした。画面奥に座る藤原が口元を歪め、不敵な笑みを浮かべた直後だった。対面の環が立ち上がった。