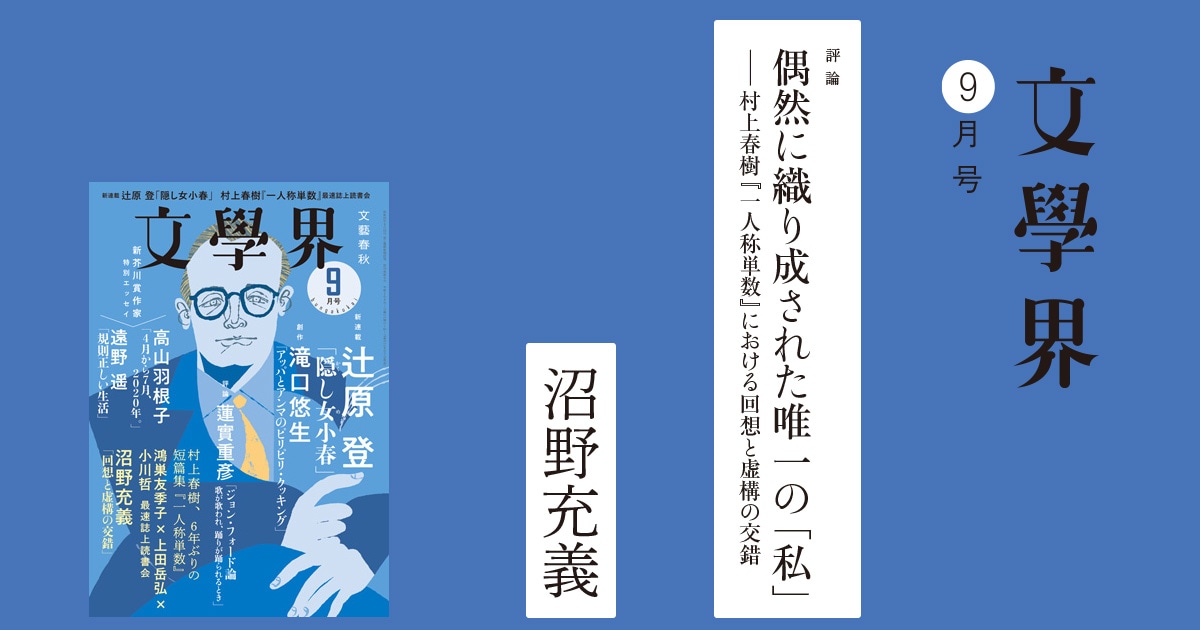

『一人称単数』でまず目につくのは、その表題がすでに宣言しているように、収録されたすべての短篇が一人称単数(最初の七篇は「僕」あるいは「ぼく」、最後の一編のみ「私」)で語られていることである。ただ、それだけでない。現在の自分の時点から過去を回想するという姿勢が強いうえ、その一人称単数が作家=村上春樹自身を強く思わせる、いわば自伝的な装いになっていることで、読者はとりあえずフィクションだと思って読みながらも、明らかに作家自身の伝記的事実と一致するディテールもかなり出てくるため、時折、作家が実際に体験したことを書いている、つまり一種の「私小説」に近いものではないか、と錯覚しそうになる。
一人称単数の語りと作品の「私小説性」の問題については後でまた考えるとして、まずこれらの作品で鮮やかに現れる「回想モード」とでもいうべきものを、一つ一つの短篇に即して少し丁寧に見ていきたい。
「僕」が「古代史」を自伝的に回想する
最初の「石のまくらに」は、「僕」がまだ十九歳のとき、周囲に小説家志望の同級生がたくさんいるという大学(早稲田大学を思わせる)の文学部に通っていた頃の回想である。「僕」はアルバイト先で知りあった「一人の女性」と一晩を一緒に過ごすことになる。しかしそれは、たまたま成り行き上そうなったのであって、恋人どうしだったわけではない。そもそも、「彼女についての知識を、僕は“まったく”と言っていいくらい持ち合わせていない。名前だって顔だって思い出せない」。そして小説の最後に「僕」は、その後二度と会うことがなかった彼女の運命について思いをめぐらす――「もう彼女は生きていないかもしれない」「僕らは二本の直線が交わり合うように、ある地点でいっときの出会いを持ち、そのまま離れていった」。そして「あれから長い歳月が過ぎ去ってしまった。(……)瞬く間に人は老いてしまう」「あとに残されているのはささやかな記憶だけだ」といった感慨が続く。しかし、それでも「吹き荒れる時間の風」をうまくやり過ごして残るものがある、とも「僕」は言う――それは「いくつかの言葉」だというのである。文学の言葉への信頼の表明ともいえるだろうか。
次の「クリーム」は、「石のまくらに」よりもさらに過去にさかのぼり、「ぼく」が十八歳で、大学受験に失敗し浪人生であったころの出来事を振り返る。それは今の「ぼく」から見れば、「ほとんど古代史みたい」に遠い過去である。しかもその話には「結論がない」と最初から断りを入れている。人工的に構成したフィクションではなく、事実をそのまま回想したものなので、謎はあってもその解決も結論もないのだ、と説明することによって、この一人称の語りが主人公の身の上に実際に起こったのだ、と読者に印象づけることになる。
その年の秋、「ぼく」は一学年下の、いっしょにピアノを習っていた女の子から、演奏会への招待状を受け取る。「ぼく」は彼女とは特に親しかったわけでもないので怪訝に思うのだが、どうして自分が招待されたのか知りたいという好奇心に駆られて、演奏会に行くことにした……。バスに乗って神戸の山の上のコンサート会場に行ってみれば、建物の入り口は固く閉ざされ、ホールには誰もいなかった。「ぼく」はいったいどういうことかと不思議に思いながらとぼとぼと帰路につくのだが、その途中、公園のベンチに腰を下ろしていると、ストレス性の過呼吸の発作のようなものに襲われ、発作が去ったとき、気づくと向かいに一人の老人が座っていて、唐突に「中心がいくつもあって」「しかも外周を持たない円」を「きみは思い浮かべられるか?」と問いかけてくる。老人は、そのような難しいことを、時間をかけて成し遂げたとき、それが人生のクリーム(フランス語でいう、クレム・ド・ラ・クレム)になるのだ、と言うのである。気が付くと、老人は消えていた。
-

【第94回アカデミー賞 国際長編映画賞受賞記念全文公開】対談 濱口竜介×野崎歓 異界へと誘う、声と沈黙<映画『ドライブ・マイ・カー』をめぐって>
2022.03.28インタビュー・対談 -
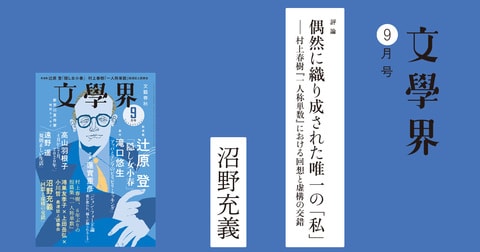
偶然に織り成された唯一の「私」――村上春樹『一人称単数』における回想と虚構の交錯(後篇)
-

驚きの展開と謎を秘めた短篇集、『一人称単数』の魅力
-

村上春樹さん6年ぶりの短篇小説集『一人称単数』の収録作が公開されました
-

映画づくりの中で僕の欲は出せたかな 映画『ミッドナイトスワン』内田英治(映画監督)
2020.10.09インタビュー・対談 -

話題作が待望の文庫化! 村上春樹『猫を棄てる 父親について語るとき』特設サイト
2022.11.08特設サイト
-
『リボンちゃん』寺地はるな・著
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募期間 2025/06/27~2025/07/04 賞品 『リボンちゃん』寺地はるな・著 5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。












