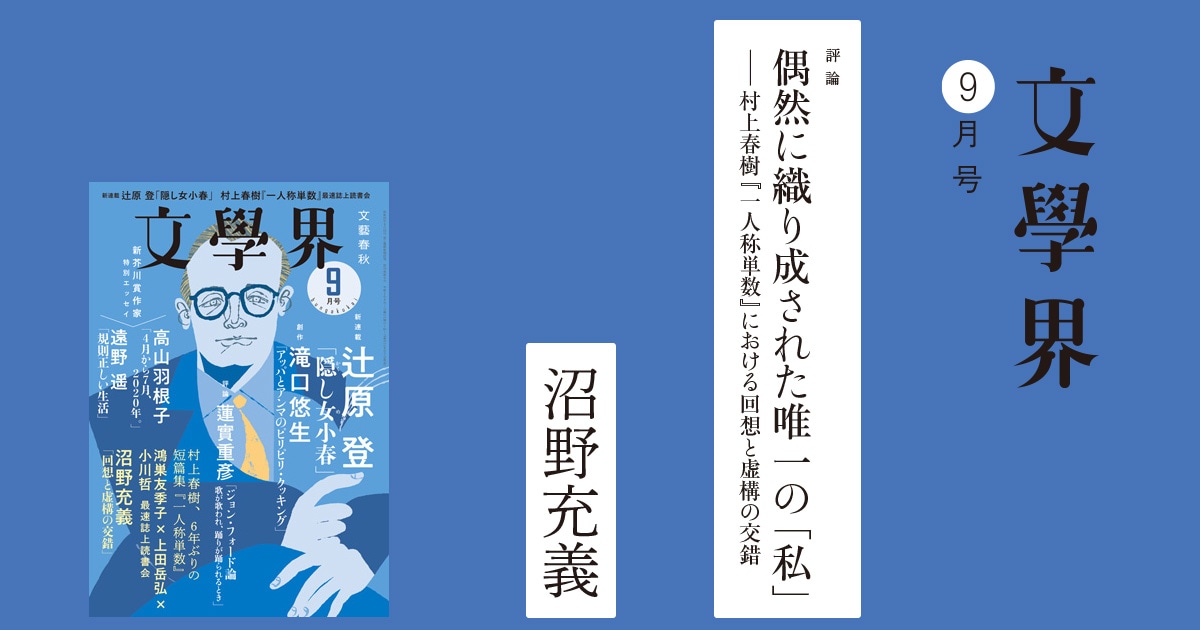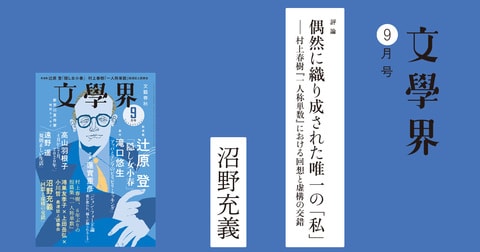時は一九六四年、ビートルズ旋風が世界中を吹き荒れていたころ。「神戸の山の上にあるかなり規模の大きな公立の高校」(村上春樹が通った兵庫県立神戸高等学校に一致する)の廊下で、「僕」は「ウィズ・ザ・ビートルズ」のLPを持つ、素敵な匂いのする、美しい少女とすれ違い、心臓が素速く脈打ち、耳の奥で小さな鈴の音が聞こえるという経験をする。その姿は「僕」の「人生における大事な出来事」として記憶され、その後も「憧憬の水準器」としての役割を果たすことになった。このような記憶は、「僕にとっての最も貴重な感情的資産のひとつとなり、生きていくための“よすが”ともなった」と、語り手は言う。
不思議なことにその女の子の姿は二度と見ることがなかったのだが、「僕」には、一人のガールフレンドができ、「僕」は彼女と親密な時を過ごした夏から秋のことを思い出し、たまたま彼女の家で出会った、引きこもり気味だったらしい彼女の「お兄さん」との出会いを語る。そして話はその十八年後に飛び、僕は三十五歳になっている。ある日、「僕」は渋谷で「お兄さん」に突然呼び止められ、彼の妹のその後の運命を聞かされる。「お兄さん」は、「こんな大きな都会でばったり君とすれ違うなんて、ほんとに不思議な気がするよ。何かの引きあわせだとしか、ぼくには思えない」と言い、「僕」も「我々は偶然に導かれるまま、二度顔を合わせた」「そこには何かを――僕らが生きていくという行為に含まれた意味らしきものを――示唆するものがあった。でもそれは結局のところ、偶然によってたまたま実現されたただの示唆に過ぎない」と述懐するのである。
ここまで見てきたことからも分かるように、『一人称単数』では随所に、村上春樹本人の伝記的事実に一致する設定が使われていて、読者はおのずから「僕」=村上春樹という印象を受けるのだが、とりわけそういった印象が強いのが「「ヤクルト・スワローズ詩集」」である。これはヤクルト・スワローズというあまり人気のない球団のファンになった「僕」の、野球との関係をめぐる一種の自伝になっている。「どのような宇宙を横切った末に、そのような儚く薄暗い星を(……)自らの守護星とすることになったのだろう?」「わりに長い話になる。(……)それは、僕という人間の簡潔な伝記みたいになるかもしれない」。
その一方で、ここには、いちおう事実として信じられる範囲内ではあるが、やはり不思議な偶然や物語的なエピソードも盛り込まれている。一九七八年、ヤクルト・スワローズは創設後二十九年目にして初優勝を果たすのだが、「僕」(=村上春樹)もこの年に(ヤクルトの試合を観戦中に小説を書くことを思い立ち――これはこの小説の中ではなく、村上春樹が別のところですでに言っていることだが)、初めての小説を書いた。その時彼は二十九歳だったのである。また最後に挿入される球場のビールの売り子とのやりとりも面白い。黒ビールの売り子の、高校生のアルバイトとおぼしき男の子は、「僕」に呼び止められて、まず「すみません。あの、これ黒ビールなんですが」と謝ったのだという。そして、「僕」はこうコメントするのだ。「僕も小説を書いていて、彼(黒ビールの売り子――沼野注)と同じような気持ちを味わうことがしばしばある。そして世界中の人々に向かって、片端から謝りたくなってしまう。「すみません。あの、これ黒ビールなんですが」と」。自分にお門違いのものを求められてしばしば不当に批判されてきたと苦い自覚を持つ作家の姿勢を鮮明に表すものだろう。