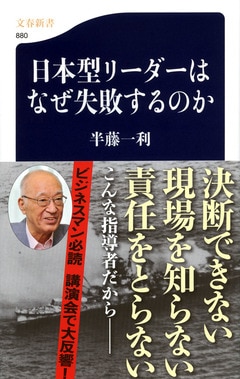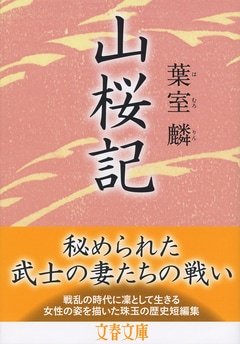『大獄 西郷青嵐賦』は、明治維新から百五十年を迎える二〇一八年の前年十一月に刊行された。九州出身の作家、葉室麟にとって、西郷隆盛は書かねばならない人物だった。
常々口にしていた「明治維新の総括をする必要がある」という構想に、いよいよ乗り出したことを宣言する一冊でもあった。なんとなれば、これもよく話していたが、明治維新を最初から最後まで体験したのは西郷隆盛しかいなかったからだ。
新作が矢継ぎ早に刊行されていた一三年のことになるが、なぜそんなに書き急ぐのか葉室さんに聞いたことがある。「(年齢的に)残り時間を意識して自分の世界を作っておかないと、その後の展開ができないから」との答えだった。「その後の展開」とは、「欧米化の波や、太平洋戦争の敗戦で否定された日本の歴史を取り戻すこと。現代の日本が失っているものは何かを書くこと」だった。当時は高杉晋作に迫った『春風伝』を上梓した直後。「これで下準備は整った」とうれしそうにうなずいていたのを思い出す。
西郷隆盛については、これまでいろいろな作品が執筆されてきた。征韓論から西南戦争の終結までを描く司馬遼太郎の『翔ぶが如く』や、海音寺潮五郎の大長編『西郷隆盛』が代表的だ。
この二作について矢部明洋さんとの共著『日本人の肖像』(一六年・講談社)で、葉室さんは次のように述べている。
〈『翔ぶが如く』は結局、「西郷は謎」で終わってしまいます。鹿児島出身の海音寺潮五郎さんも大長編史伝で西郷に迫りますが、未完に終わりました。その浮沈の激しい生涯やスケールの大きい人格に、大作家たちもなかなか西郷像をとらえきれません〉
そのうえでこう語っている。
〈九州育ちの私は、西郷タイプのリーダーに出会った経験が割とあります。修羅場で決断力があり、カリスマ性ゆえ人望がある。それでいて寡黙。九州独特かどうかは分かりませんが、司馬さんのように謎とは思わない〉
明治維新の読み直し、西郷のとらえ直しに挑み始めた葉室さんは、何か感得した境地があったに違いない。見つめていた先に何があったのか。
『大獄』は、島津斉彬に見いだされ、安政の大獄から逃れて奄美大島に潜居し、呼び戻されるまでの若き西郷を描く。物語はまだ緒についたばかりだが、若き日々には後の姿を形作る萌芽がたくさん見つかる。そこに込められた作家の視線を追ってみたい。
近海に外国船がたびたび姿を見せるようになった時代、海防問題に直面した老中首座、阿部正弘が頼りとする島津斉彬が薩摩に帰国した。父である藩主、斉興とは折り合いが悪く、三十八歳になりながらいまだ世子のままだが、正弘と共に国難に対峙するのに、「仁勇の者」を求めていた。それは〈仁を行う勇を持った者〉のことで、他の登場人物の言によれば、〈仁とはひととひととを結びつける心〉なのだという。
一方、郡方書役という平凡な役人だった西郷吉之助の仲間内での位置はこんなだった。〈吉之助は常に理由を言わず、結論だけを言う。そんなとき、日ごろ、平凡で茫洋としているとしか見えない吉之助のひと言にずしりとした重みが加わる。/そして吉之助がひと言を発すれば誰もわけを問おうとはしない〉。覚悟をもって正しい道を踏み行い、強さと同時に優しさも知る若者だった。
やがて、家中の争いなどは些事だとして、日本の国難にあたり人柱になろうという斉彬の覚悟に胸を突かれた吉之助は股肱の臣となっていく。ところが斉彬が急逝してしまい、失意の吉之助は奄美大島で見る景色が変わる回心の機会に遭遇する。斉彬はわが国一国のことだけを考えていたのではなく、世界に対峙する国づくりを視野に入れていたと感得したのだ。
〈吉之助の胸に、孔孟の教えのままに、古代の聖王の堯や舜が治めたような道義に基づく国を造りたいという思いが湧いた〉。胸に去来したのは〈(力により、弱き者を虐げる異国は不義の国じゃ。わが国は道義の国でなけりゃ、ならん。さもなければ異国に負けるとじゃ)〉という思い。
ああ、そうかとその志がこちらの胸に落ちる、説得力を持つクライマックスシーンだ。葉室さんが見据えていた西郷の核はこれなのだろう。こう思い至ることになる吉之助だからこそ、「正義の戦い」を誓い合った大久保一蔵との間にきしみが徐々に醸されていく。
奄美大島への島流しを前に、諸藩工作の最大の武器だった人脈を悪びれることもなく教えろと要求する一蔵と、寂寥を感じながらも率直に明かす吉之助。打算によってつながる久光と一蔵に対し、斉彬と吉之助の心情が通った交わり。いったん決めたことに関しては聞く耳持たない一蔵の鋼のような強さと、それを案じる吉之助の優しさ――。将来の訣別の予感を吉之助に語らせてもいる。
この国づくりの展望は、本書に続く『天翔ける』(一七年十二月刊)でも引き継がれていく。幕末四賢侯の一人、松平春嶽を描く物語である。『大獄』にも〈強国を目指すのではなく、仁義の大道を世界に広める国になるべきだ〉とその一端が紹介されているが、『天翔ける』では、春嶽が登用した横井小楠が唱えたその説が詳細に解かれていく。技術を取り入れ経済的進歩を遂げるばかりでなく、〈儒教を極め、道義国家を造り上げようというのだ〉。さらに、明治になってからの勝海舟のこんな言葉を紹介している。
〈横井の思想を西郷の手で行われたら、もはやそれまでだと心配していた〉
残念ながら横井は春嶽のもとを去らざるを得なくなり、西郷も大久保とたもとを分かち西南戦争で没する。
日本は富国強兵、経済成長一辺倒で突き進んだ。道義は顧みられなかった。我々にとって、大切なのはなんといっても経済成長だった。そして現在、地球環境を搾取しすぎた資本主義は存続の危機を迎えている。世界はデマゴーグ(扇動政治家)であふれている。このままでは到底人類が立ちゆかない。その時、立ち返るべきポイントを葉室さんはこの二作で示しているように思う。地球環境の危機を訴えるスウェーデンの環境活動家、グレタ・トゥーンベリさんや、脱成長経済を提唱する大阪市立大学准教授の斎藤幸平さんら、今、従来の資本主義に待ったをかける議論が盛んだ。葉室さんがいたら、この議論に有益な視点を加えることができたのではないか。
『大獄』の単行本が刊行された直後の一七年十二月二十三日、六十六歳で葉室さんはこの世を去ってしまった。今のこの時代にとって、葉室さんによる明治維新の見直しがどれほど重要な仕事だったか、今更ながらに思い知らされる。「道義の国」について、葉室さんの肉声でもっと説明を聞きたかった。改めてその不在が惜しまれてならない。
最後に、明治維新のとらえ方をながめてみよう。
維新といえば薩摩藩と長州藩だが、『大獄』は安政の大獄の前から始まる。まだ長州藩は姿を見せない。葉室さんはこの頃から維新につながると見ていたわけだ。
将軍継嗣問題とアメリカとの通商条約締結を絡めた一橋派と南紀派の暗闘は、手に汗握る緊張感だ。斉彬と吉之助、春嶽と橋本左内に敵対するは井伊直弼と長野主膳、水野忠央。いずれ劣らぬ実力と見識を持つ人々の対立が端的につづられ、尊皇攘夷派、佐幕派、開国派入り乱れた複雑な情勢が、すんなりと読める手際は見事としか言いようがない。
そして安政の大獄で保守的な開国派の直弼が、開明的な開国派の斉彬、春嶽らをつぶした構造を繰り返し述べている。戊辰戦争をしないですんだかもしれないいくつかのターニングポイントが、かかわる人物のめぐりあわせや、ボタンの掛け違いなどで潰えていく。この歯がゆさも幕末物の真骨頂ではあるまいか。
『天翔ける』は、維新を幕府の要人側から描いたものだ。彼らが果たした役割は決して小さくない。しかし、後に矮小化される。そのことを重ねて糾弾する。
〈大政奉還、王政復古にいたる流れでは、実権は島津久光を始めとする春嶽や容堂らいわゆる賢侯にあったが、新政府成立後、志士上がりの官僚たちが、すべては自分たちの功績であったかのように主張していく〉
〈いずれにしても明治初年に尊攘派以外の政府要人はしだいに遠ざけられ、その後、明治維新は尊攘派による革命であったかのように喧伝されていくのである〉
正史に埋もれた歴史を語るのは、小説の大切な役割だ。こぼれたところを正当に位置づけることによって、今の世に欠けていた観点をすくいとってみせる。
さて、『大獄』は「西郷青嵐賦」とあるように、まだまだ青春時代の西郷さんだ。続編を考えていたであろう。長州藩が出てくるのはこれからだ。指針を示す斉彬を失った西郷の行く末の物語は、読みたかったとは思うが、西南戦争での最期を知るだけに読むのがつらくなっていたかもしれない。
しかし、こうも考えられる。後の維新の経緯は『天翔ける』で述べられている。西郷隆盛について書くべき肝は、『大獄』に凝縮されていると言っても過言ではない。両作で忘れられていた国づくりの指針も示した。とすると、急ぎ過ぎたけれど、葉室さんは書くべきことは最低限書いたと言ってもいいのかもしれない。後はわれわれが何をくみ取るかだ。
そう考えると、『大獄』と続く『天翔ける』は、葉室麟という作家の遺志を宿す、誠に重要な作品だということがよくわかるのである。