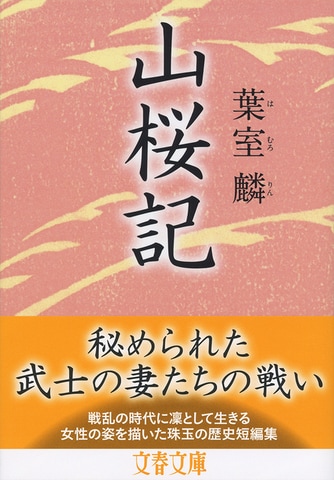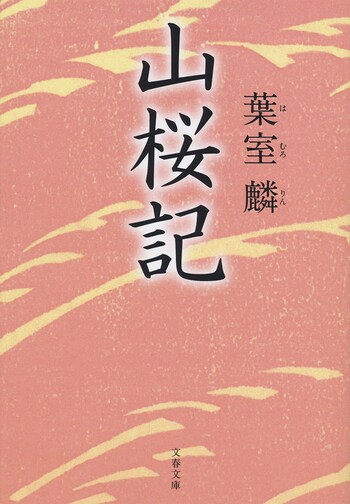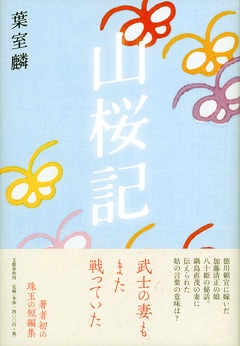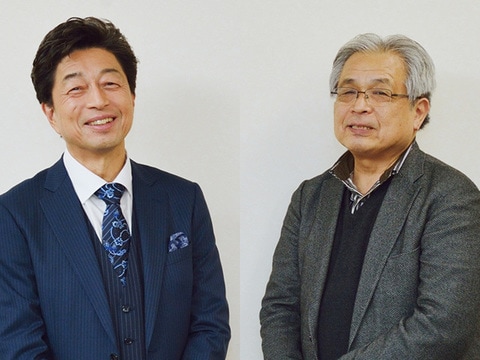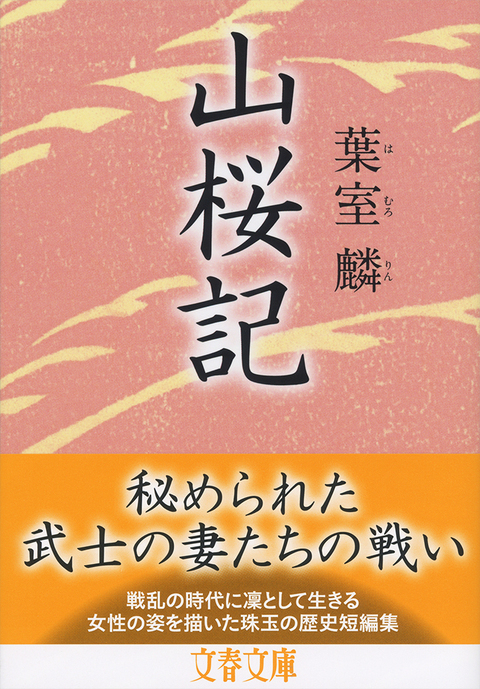
人間は小説を読み終わった瞬間、どんな感想を抱くのか。
無論それは作品によっても、また読者によっても異なろうが、〈面白かった〉〈感動した〉といった褒詞の他には、〈泣けた〉〈ユーモラスだった〉などという感想が多いに違いない。
しかし私はいつも、葉室さんの作品を読み終わった瞬間、胸の中で呟く言葉がある。
それはいわゆる感想ではなく、
――ああ、美しいなあ。
という詠嘆である。
本作を紐解いてまず心に残るのは、〈ぎんぎんじょ〉、〈くのないように〉、〈牡丹の存ぜず候様に〉といった数々の言葉。さりながら葉室作品の美しさは、作中にちりばめられた言葉のみによって作り上げられたものではない。
登場人物たちの潤いに満ちた心の動き、その生き様……彼らの純真な精神は研ぎ澄まされた語句と混然一体となって、独自の世界を形成する。その澄み切った小説世界のあまりの美しさに、私は思わず感嘆の声を漏らしてしまうのだ。
『山桜記』は戦国時代から江戸初期にかけての九州各地を舞台に、武家社会の「妻」の生き方を描いた短編集。豊臣秀吉の命で朝鮮に渡った夫に恋文を送る妻、キリシタンとしての生き方を巡って、夫と哀しくすれ違う公家の女など、七組の「愛」の形がここにはある。
しかし愛と一口に言っても、その形は実に様々。ましてや戦乱の時代を生きた武家の夫婦ともなれば、御家騒動や相次ぐ戦、更には信仰などの外的要因により、その絆が揺らぐことも多かろう。
だが図らずも作中の一篇「ぎんぎんじょ」の中で、葉室氏はヒロインの姑・慶誾の口を借りて、「この世で夫婦のつながりほど強いものは、ほかにありませぬ」と語らせている。
「夫婦となると、もともと他人ゆえ心が通わねば共に暮らすのは無理でございましょう。いずれかが力を失うたからと見捨てるのは夫婦とは申せませぬ。ひたすら心の結びつきに頼って世の荒波を渡らねばならぬのですから、夫婦ほど強いつながりはないのです」
この逆説的とも言える夫婦観は、形のない信頼に依拠しているがゆえに、硬質の玉の如く美しい。そんなどんな世の荒波にも共に挑む男女の有り方こそ、本作において葉室氏が理想とした夫婦像と言えよう。
「花の陰」において、三十九万石の大名になることよりも、夫婦が共に生きることこそ喜びと考えた細川忠隆と妻・千世は、最終的には二人の間に生まれた娘たちの行く末を思い、遂には離縁に至る。互いを愛おしむ思いを貫いた末、別の道を歩み始める二人。満開の花が風に誘われて散るが如きその別離は、凛然として美しく、そして一点曇りのない青天を思わせる澄んだ真情に満たされているではないか。ちりぬべき時、という言葉の重みが、じわじわと胸に迫ってくる。
ところでフリードリヒ・エンゲルスが『家族・私有財産・国家の起源』で言及した如く、女性の男性への従属は、家父長制家族の成立によって始まると考えるのが一般的である。日本における家父長制の確立をどの時代に置くのかは、現在も様々な議論があるが、女性の財産所有権が衰退し、妻が夫の家の姓を名乗る「家名」が成立する中世後期と考える説が主流であるようだ。
だが実のところ日本では、江戸時代に至っても夫婦は異なる財産を所有し続けており、女性が完全に男性に従属していたとは見なし難い。
事実、諸藩大名家の奥方は家内の紛争解決や近隣諸家との交流を一手に担い、「内政」を預かることで、自藩と夫を支えていた。それは商家や富農においても似たり寄ったりであったし、おそらく「内」を支える女性たちはみな、現代女性にも劣らぬほど気丈だったに違いない。
しかし今日、日本人は武家社会における女性像を画一化し、御家のためであれば我が身を惜しまぬ従順な女性しかいなかったかのように考えがちである。こういった女性像は明治期以降に広まった資本主義的家父長制によって蔓延したとも言え、葉室氏の作品に見られる気骨のある女性たちは、当時においては決して珍しくなかったことを、我々は認識しておかねばならない。
とはいえもちろん葉室氏は、作中でこんなややこしい女性論を振りかざしたりはしない。だが『山桜記』に登場する女性たちは、時代の激しいうねりの中でもまっすぐに顔を上げ、自らが信じる道を突き進む。
そんな端然たる女たちを描くことで、葉室氏は我々が知らず知らずのうちに信じてきた女性像の転換を迫るとともに、いつの世も変わらぬ人の心の美しさを現代に問うておられるのではなかろうか。
昨今、時代・歴史小説の分野では、江戸や京都といった当時の「中央」を舞台とする作品が増えており、たとえば戦国という群雄割拠の時代を扱った作品でも、どこかに「中央」への眼差しを留めた作品が大半である。
そんな中で北九州小倉出身の葉室氏は、豊後・羽根藩を舞台とする直木賞受賞作『蜩ノ記』を筆頭に、テレビドラマにもなった『銀漢の賦』、平安時代、壱岐・対馬を蹂躙した異民族との戦いを描いた『刀伊入寇 藤原隆家の闘い』など、九州を舞台とした作品を多く発表し続けておられる。
山口県在住の作家・古川薫氏は、かつて福岡県在住の白石一郎と佐賀県在住の滝口康彦、それに古川氏を併せた三人を東京の編集者が「西国三人衆」と呼んだのは、遅咲きの小説家に対する揶揄と哀れみと親しみを込めた「尊称」だったと述べる。さりながら私は三人の作家に与えられたその呼称には、郷土愛というものを宿命的に持たぬ「中央」の人間の自嘲と羨望が、ありありと沁み出している気がしてならない。
かつて吉川英治は随想の中で、日本の国民性は郷土愛と歴史性なくしては成り立たないと主張し、
「少なくとも大衆文学の稍々(やや)優れたものと、常に心懸けのいい作家というものは、郷土性、所謂郷土文学というものには、関心を多分に持っていると思っている。そこにも僕は大衆文学の特殊性があると思っている。要するに、今日の大衆文学というものは一方、反省の文学であると同時に、郷土的なものでありたいという事を僕は望んでいるものである」
と、時代小説における「地方」の重要性を説いた。
きっと直接、葉室氏にこんなことを聞けば、氏ははにかんで「そんなことはないですよ」と仰るだろう。
しかし吉川英治のこの一文に触れる都度、わたしは葉室氏は日本人が歴史の中で見失った人間の実像を追うために、あえて「地方」を描き続けておられるのではないかと考えてしまう。そう、「武家社会」という言葉に埋もれた女性たちの姿を、美しい物語の中に鮮やかに甦らせたように。
「ぎんぎんじょ」において、慶誾は嫁である彦鶴に穏やかで慎み深くあれと教え諭す。きっと今、我々読者は本作を通じ、葉室氏から歴史に埋もれた人々の真情を知れと静かに諭されているのに違いない。