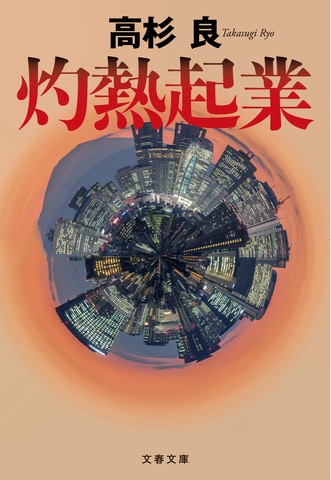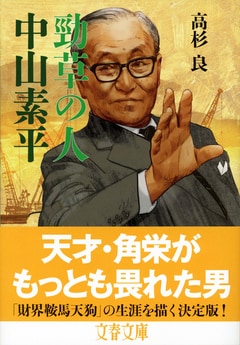この小説は、ラジオ放送会社の記者から営業マンを経て独立、自転車の組み立て・販売で年商百億を超す企業を起こし育てた男のノンフィクション物語である。読者をひきつけるのは、なんといっても主人公、武田光司が放つ男臭さだろう。
放送局では、出演者にも上司にもずけずけものを言い、それが可愛がられるきっかけになる。嫌う上司もいるが意に介さず、営業マンとしては、熱心さと誠実さで大きな番組スポンサーを獲得していく。そして、「このままうすっぺらな人生を積み重ねていいのか」と自問して、会社を辞めて、新たなビジネスをはじめる。行きつけのクラブでは、いつのまにかマダムと懇(ねんご)ろになり、家庭を捨てて、この女性と暮らす。
会社勤めを経験した人なら、職場や家庭で大っぴらには言えないが、こんなことを言ってみたい、してみたいと思うことを主人公はやってみせる。フィクションなら絵空事の「男のロマン」だが、シティサイクルのマルキン、スポーツサイクルのコーダーブルームなどのブランドを持つホダカの創業者の実話といわれると、読むうちに日ごろのうっぷんのカタルシス(浄化)となる度合いも高まるのではないか。
この会社が急成長したのは、武田が持つ天性の営業センスと努力もあるが、自転車業界で「第三ルート」と呼ばれてきた流通の新しい流れをつかんだことが大きい。自転車の流通は、フレームやサドル、チェーン、タイヤなどの部品を完成車メーカーが組み立て、それを専門の問屋が町の自転車店に卸すことで成り立っていた。第三ルートとは、スーパーマーケットなどが既存の流通ルートを通さずに仕入れる流れのことで、「正規ルート」ではない裏街道的な意味合いもあった。
そこに切り込んだのが武田で、台湾のメーカーから自転車を輸入してイトーヨーカ堂に卸すルートを開拓した。一九七一年のことだ。ところが、カタログ販売で世界最大の小売業者になった米国のシアーズ・ローバックに卸しているというのが自慢だった台湾製は、品質にうるさい日本の市場には合わなかった。そこで、武田は大阪府堺市の完成車メーカーから仕入れるルートを確保する。
国産車の第三ルートを確保することで、武田は自転車業界の流通革命を押し進めることになるが、この流れを支流から主流に変えたのは、小売業の「価格破壊」を進めたスーパーマーケットの急成長だった。ダイエー、イトーヨーカ堂、西友、ジャスコなどがしのぎを削ったスーパーの拡張戦争で、自転車はその目玉商品のひとつになった。量販店にとって自転車が魅力のある商品だったのはなぜか、作者はその秘密を書いている。
スーパーなどの大型店は大きな前カゴの付いた自転車を量販することによって、来客に便利な足を提供することにもなるのだから、いわば一石二鳥である。
いかつい黒のフレームで後ろに荷台のある「実用車」に代わって、カラーのフレームで前にカゴを付けた日本独特の「軽快車」が人気を得るようになったのは一九六〇年代半ばだ。やがてこのシティサイクルは「ママチャリ」の名で親しまれ、主婦層の生活必需品になる。量販店にとっては、特売といっても単価の高いこの商品を売れば、売り上げは上がるし、遠方からの顧客をふやし商圏を広げることにもつながった。専門紙の記者だった作者の目は、主人公の人間ドラマを追う一方で、自転車業界や流通業界の構造変化もしっかり見据えている。
ホダカにとってイトーヨーカ堂は最大の取引先で、ヨーカ堂の店舗の拡大と歩調を合わせてホダカは売り上げを伸ばしてきた。武田のような出入り業者にとってヨーカ堂の伊藤雅俊社長(現名誉会長)は神様のような存在で、ヨーカ堂が新年に開く賀詞交歓会は年に一度、出入り業者が「神様に拝顔の栄に浴する」機会だった。その交歓会で武田が伊藤から声をかけられる場面がある。
「おめでとうございます」
武田は深々と頭を下げた。
伊藤は表情をがらっと変え、恐いくらいひきしめた。そして、まっすぐ武田をとらえた。
武田は背筋がぞくっとした。
「ブリヂストンや宮田やナショナル自転車の勉強をきちっとやりなさい」
伊藤の厳しい表情と強い口調に武田は返事が一拍遅れた。
「はい」
次の瞬間、元の優しい表情を取り戻した伊藤は、別の業者の挨拶を受けていた。
自転車をセールの目玉商品にするが、品質では大手に負けないものを出すようにと、業者を叱咤激励する。その後、ダイエーや西友が脱落するなかで、流通戦争を勝ち抜いたヨーカ堂指揮官の鋭さを示すエピソードだろう。
量販店の非情さを垣間見せる逸話もある。一九七四年にヨーカ堂は神奈川県藤沢駅前に店を開き、既に進出していたダイエーとの間で熾烈(しれつ)な「藤沢戦争」を展開する。自転車も開店の目玉商品になっていたため、武田は通常価格よりも安値での納品を覚悟して、在庫をふやして待っていたが、発注は来なかった。より安値での納入が見込まれたのか、ライバル会社に発注していたのだ。
商売にはよくあることかもしれないが、この業界のすごいところは、出入り業者は自分の商品が扱われなくても開店時の販売応援に駆け付けるのが「責務」になっていることだ。「他社の自転車を販売するために手伝わされる身の切なさ、やりきれなさ、といったらない」という武田の気持ちに同情を禁じ得ない場面だ。
「いらっしゃいませ」
武田はいつもどおり明るくふるまい、大声を張り上げて、来客と応対した。顔で笑って心で哭(な)いていたのである。
成功話だけでは、ドラマは面白くない。武田も大きな失敗を重ねている。ひとつは米国進出だ。ホダカは一九八三年に米国ニュージャージー州に現地法人を設立、全米で本格的にスポーツ車の販売を始める。しかし、円高でドル建ての輸入価格が高くなり、台湾製などとの競争条件が悪化したり、現地のマネジメントが武田の期待通りに動かなかったりで、三年後には米国での事業を清算することになる。
また、一九九〇年には、新会社をつくってスポーツウェアに進出するが、会社をまかせた経営者たちの放漫経営もあって、一九九三年には、事業の中核会社を倒産させる形で撤退するしかなかった。事業の失敗が明らかになったところで、武田が副社長に心情を吐露する場面がある。
「わたしは事業の手を広げたいと常々考えてました。(筆者注――新事業を持ち込んだ)大木に惚れ込み、のぼせ上がった不明を恥じるばかりです。人に惚れ込むと、見境がなくなってしまうんです」
イトーヨーカ堂に依存するだけでは、これ以上の発展は望めないという武田の思いと、新事業には不可欠の新たな人材の発掘で、相手に惚れ込みすぎて失敗してしまう人柄がにじみ出ている言葉だ。
『金融腐蝕列島』に代表されるように、巨大産業や企業のドラマを得意としてきた高杉良が、なぜそれほど目立たない分野の中小企業の創業者を小説にしようと思ったのか。高杉に尋ねたら、次のような答えが返ってきた。
「もともと中小企業の経営者が集う小さな会合に呼ばれたときに、もっとも熱心に質問したのが武田さんで、そこで意気投合した。その後、お会いする機会があって、武田さんの話を聞くうちに、飾らない人柄に惚れ込んで、あなたを小説にしたいということになった。小説にするため、いろいろな関係者に取材したが、彼の悪口を言う人はひとりもいなかった」
武田が熱心に質問したのは、もともとは新聞記者になりたかったという社会的な好奇心の強さもあるだろうが、このままでは終わりたくない、という事業家としての意欲が何かのヒントを求めていたのではないか。高杉良がこの作品を世に出したのは、一九九六年三月から刊行された「高杉良経済小説全集」(全一五巻)の月報での連載で、九八年に『勇気凜々』のタイトルで単行本化されたのち、文庫版にもなっている。読者は、主人公が新たな事業展開をすることを期待して続編を読みたかったにちがいないが、武田は二〇〇一年、中国で客死する。六三歳の若さだった。
自転車業界は、一九九〇年代から中国などからの輸入が拡大し、それにつれて国内での生産は急速に減少した。二〇一九年の国内生産比率は一二.四%までに落ち込み、国産の六五%は、日本独自の法規制が輸入を抑えている電動アシスト車だ。子どもを前と後ろに乗せてさっそうと走るママチャリのサドルの下を見ると、バッテリーが付いているのをよく見かけるようになった。自転車は進化しているのだ。
これからの移動手段としての交通の主流はMaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)だといわれている。自家用車以外のすべての交通手段を情報通信技術で、予約や決済を含めひとつのサービスとして使えるようにする仕組みだ。公共交通機関で最寄駅に着いたあと、最終目的地までのラストワンマイルと呼ばれる近距離の移動は、だれでも利用できるシェアサービスの電動自転車が主力になると期待されている。武田が生きていれば、自転車の未来にどんな夢を描いたことだろう。
武田は、ホダカ創立二〇周年の一九九二年、記念行事の一環として、およそ一〇年間かけて集めた駒井哲郎(一九二〇~一九七六)の版画九五点をホダカの本拠地である埼玉県の県立近代美術館に寄贈することを決め、翌年、実行に移した。旅先の岩手県で偶然、目にした駒井の作品に胸を打たれ、折に触れて蒐集してきたものだ。
放送局を辞めるときに、常務だった人が激励の葉書を寄こした。武田は感激して、この葉書を額に入れて心の支えにしてきたという。そのなかにこんなくだりがあった。
存分にやってくれ。始めはわが為に、やがて社会公共の為に。武田光司は男でござる。
独立して二〇年、会社が百人を超える企業に成長したところで、武田は尊敬する大先輩の言いつけを守ったことになる。
県立美術館によると、武田はコレクションを寄贈したあとも一九九九年に四点、二〇〇一年に二点の駒井作品をこの美術館に寄贈している。最後の二点のタイトルは「夢の始まり」と「夢の終り」だったという。
武田の見果てぬ夢を私たちはこの作品を通じていつでも見ることができるし、武田のエネルギッシュな活躍を心の糧にすることもできる。この灼熱起業の物語は、私たちの胸のなかで、勇気凜々のベルを鳴り響かせてくれる。