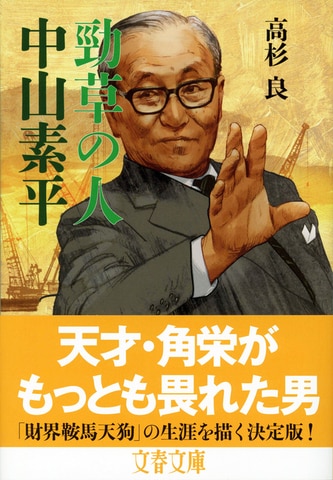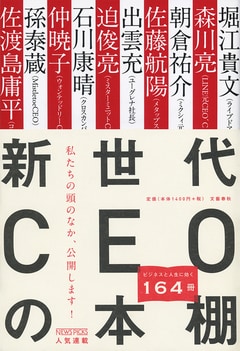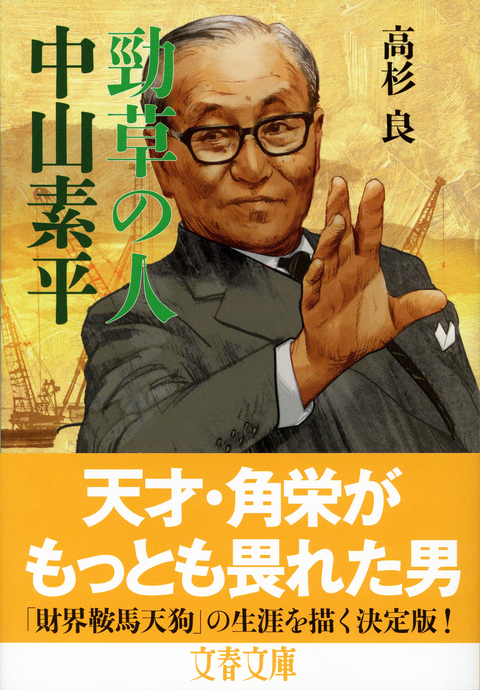
「レクイエムとまでは言わないけど、興銀と中山さんのことを書くのはこれが最後……」。二〇一四年九月、単行本で『勁草(けいそう)の人 戦後日本を築いた財界人』が出た際のインタビューで高杉良は愛惜の表情を見せた。
中山素平(そへい)(一九〇六~二〇〇五年)。日本興業銀行(現みずほフィナンシャルグループ)頭取、会長、経済同友会代表幹事を歴任した。「財界鞍馬天狗」と呼ばれた異色の経営者は、バンカーの枠を超えて常に公共的な視点で行動した。権力に媚びず、叙勲や褒章を拒み、自伝の類いも残さなかった。
高杉は四〇年に及ぶ作家活動で八〇を超す経済小説を生み出した。数多くの経営者に会う中で最も深く敬愛するのが中山だろう。戦後産業史のエポックをインダストリアル・バンクの視点で描いた長編『小説 日本興業銀行』(一九八六~八八年)で興銀と中山を余すところなく描き切った。
二人の交流は取材をきっかけに始まり、年の差を越えた友情が終生続いた。「今日はあなたに会いたいな。」朝八時に高杉の自宅に電話をかけてくる中山。人事の相談を受けるまで信頼される高杉。本作は『小説 日本興業銀行』の続編の位置づけだが、中山の素顔を知るからこそ書けた追想のメモリアルであるとともに、経済記者もうなる秘史が随所に刻まれている。
細川護熙首相の退陣、リクルート事件で揺れたNTTのトップ人事、ディズニーランドの建設……。ここでも中山の際立った行動力があったことが分かるが、この作品の白眉は、晩年を描いた後半にある。だれにも老いはやってくる。鞍馬天狗とまで呼ばれた「大老人」はどう生き切ったのか。時代の荒波にもまれ、混迷を極める社会を達観した目でどう見ていたのか。
中山は、忍び寄る老いをものともせず、新潟に日本初の大学院大学を新設するプロジェクトに心血を注ぎ、募金集めにかけずり回る。百歳を前にしても大学の運営にリーダーシップを発揮する。「苦労のし甲斐がある」「さして苦にはならない」。そんな感懐を紹介して高杉はつづる。「国際大学は、中山にとってユートピア、理想郷だった」
市場原理主義批判
本体の興銀は産業金融の雄として名をはせた時代は過ぎ去り、バブル崩壊後、苦境に陥る。乱脈金融の象徴ともなった大阪・ミナミの元料亭女将の預金証書偽造事件。巨額の融資をしていた興銀の経営は揺らぐ。「信頼を勝ち取るのは難しいが、失われた信頼を取り戻すのはもっともっと大変なのだ。」だれが責任を取るのか。首脳たちに引導を渡す中山。それぞれの本性がにじみ出る緊迫の会話劇は本文に譲るが、ディテールを知る高杉ならではの迫真力に満ちたやりとりに息をのむ。その後、曲折を経て、第一勧業銀行、富士銀行との三行統合に至る。栄光の時代を知る中山の目を通して興銀の幕引きが描写される。
バブル崩壊後の激動を経て日本の経済社会は再生に向かっているのだろうか。人差し指をピストルのように相手に突きつけて「どうなんです」と迫る中山の表情が行間から垣間見えるようだ。安倍晋三政権の経済政策「アベノミクス」の裏側で広がる格差と貧困。市場原理主義を批判してきた高杉は中山に語らせる。
「全人口の八割が中産階級の意識を持ち、貧富の格差が小さいのは日本の財産だ。これを守る方向で税制、社会保障などの政策転換が必要だ」
これは日本社会への中山の遺言だろう。疾風に勁草を知る。勁(つよ)く温かいリーダーが今ほど切実に待たれるときはないだろう。
金融の光と影
高杉作品のリアリティーの源泉は精力的な取材にあるが、その人生の歩みと作品のモチーフがリンクしていることも大きい。
まずは石油化学新聞の記者、編集長の経験だ。若い頃から相手の懐に飛び込み、経営者の行動をつぶさに見てきたことが作品に深みを与えている。デビュー作の『虚構の城』のモデルは出光興産、名作『炎の経営者』は日本触媒、ドラマ化された『生命燃ゆ』は昭和電工といった具合に、深く取材した化学工業の世界は名作の「培地」となった。
「素材産業ですから、決して表に派手には出ないけれども、実に幅広い業種と関連がありました」。繊維、プラスチック、ゴム、自動車、家電、銀行、商社……。その後の高杉作品の広がりを予感させる。
その延長線上で『小説 日本興業銀行』が生まれる。前述の通り、興銀は日本の経済復興、産業復興を使命として重厚長大産業を始め数々の企業を育成してきた。
「産業の血液」である資金を経済社会の隅々にまで健全に行き渡らせるのが金融の正しいあり方だ。経済活動の中でとりわけ人間的なのが金融の世界であり、信用をベースにお金が動く。そこでは企業と人をきちんと審査できるかどうかが死命を決する。担保にとらわれない、目利きの力こそがバンカーの最大の武器なのだ。「本当のラストバンカー(最後の銀行家)というのは、中山さんみたいな人のことを言うのでしょうね」。真贋を見抜く眼力を指してのことだ。
高杉の金融小説の到達点を示すのがシリーズ『金融腐蝕(ふしょく)列島』である。この国の銀行の変遷を見据え、二〇〇八年の第四作『消失』で十余年にわたる物語を終えた。金融の光の物語が『小説 日本興業銀行』とすれば、いまも経済社会を覆い続ける「影」の世界に迫ったのがこの『金融腐蝕列島』である。「護送船団として守られてきた“金融村”の腐敗と崩壊の歴史そのもの。嵐の中で銀行はのたうち苦しんできた」。総会屋への利益供与事件、住専(住宅金融専門会社)への公的資金投入、破たんと再編、不良債権処理、貸し渋り・貸しはがし、金融庁の厳格査定……。バブル崩壊後の日本経済の激動を切り取った出色の作品である。
シリーズで登場した銀行は、大手行すべてといっていい。第一勧業銀行(現みずほフィナンシャルグループ)であったり、三和銀行(現三菱UFJフィナンシャル・グループ)であったり。読み進むと、あの銀行のあの事件が次々と思い起こされる。
そこで警鐘を鳴らしたのは、市場主義一辺倒の政治経済のありようだ。「日本はどれほど傷んだことか。格差が広がり、東京一極集中が進み、地方はとことん疲弊した」と状況を深く憂う。高杉作品に流れる通奏低音として聞こえてくるだろう。