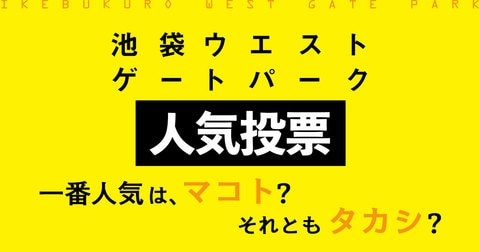「亡くなった九歳の女の子と同じように、あの少年Aの兄も奥ノ山事件の被害者だった」
加害者家族も、被害者である。本書が単行本で刊行された一九九九年当時、この一文を書くには、相当の覚悟が必要だったのではないかと想像する。九〇年代後半と聞いてピンときた方もいるはずだが、二年前の一九九七年に、名実ともに少年犯罪史に大きな影響を与えた、神戸市連続児童殺傷事件(酒鬼薔薇事件)が起きているからだ。
本書で中心的に描かれる殺人事件と、神戸市連続児童殺傷事件の間には、被害児童や加害児童の特性、犯行態様、犯行後のパフォーマンスといった多くの点で類似性が認められる。もちろん、偶然に似通ったわけではない。“あの事件を別の角度から見ることはできないだろうか?”という思いで本書を書き上げたと、著者はインタビューで答えている。
著者が見せようとしたのは、どの角度から照らした光景だったのか。
事件当時、私は小学校低学年だったので、リアルタイムで社会の反応をうかがうことはできなかった。だが、加害者家族側に焦点を当てながら、さらに彼らを被害者として扱おうとする報道は皆無に近かったはずだ。なぜ、そのように言えるのか。答えは単純で、事件から二十年以上が経過し、個々人の人権意識が高まった現在においても、加害者家族──特に少年事件の加害者家族は、社会の厳しい視線に晒され続けているからである。
本書を読み進めれば、加害者家族から見た事件の光景が、克明に描かれていることに気付くだろう。そして、その観測者を親ではなく、少年Aと同じ目線に立つ中学生の兄に設定することで、物語に青春小説としての深みがもたらされている。
前置きはこれくらいにして、内容について触れていきたい。
本書において舞台とされているのは、日本の科学技術振興の中心として、国家プロジェクトで生まれた『科学の街』。豊かな自然環境と多数の研究施設が併存するニュータウンで、失踪していた九歳の少女の凄惨な遺体が発見される。
死因は窒息死。遺体はロープで吊り下げられ、両乳頭部に咬傷が認められた。そして現場には、スプレー塗料を用いたサインと、さらなる犯行を仄(ほの)めかすメッセージが残されていた。
ニュータウンを騒然とさせた殺人事件は、男子中学生──三村和枝の補導によって一応の決着を迎える。事件当時十三歳であった和枝は、刑事未成年者として刑罰を科されず、少年院送致も免れて、児童自立支援施設送致という軽微な保護処分が下される。
少年法の限界を露わにするかのような犯行と、生じた結果と釣り合わない処分。
衝撃が、恐怖が、怒りが、憎しみが。地域を越えて、社会全体を駆け巡る。そして、行き場を失った負の感情が、加害者家族に容赦なく襲い掛かっていく。
なお、先にも述べたとおり、本書の単行本は一九九九年に刊行された。そこで、二十年以上が経過した現在において、仮に同様の事件が起きた場合の処遇を、若干補足しておく。
神戸市連続児童殺傷事件の発生をきっかけに、少年法は厳罰化の一途を辿っている。二〇〇〇年に刑罰の対象年齢が十六歳以上から十四歳以上に引き下げられ、また、二〇〇七年には少年院に送致できる年齢の下限が十四歳からおおむね十二歳に引き下げられた。したがって、事件当時十三歳の少年には、現在においても刑罰を科すことはできないが、少年院送致は認められる。
話を戻そう。本書では、本文の四分の一程度で、犯人の名前や犯行態様の大部分が読者に明かされる。加害者家族から見た事件の光景を深掘りするために、犯人当てというミステリーの装飾を早々に切り離しているのだ。その潔い決断によって、本書における謎解きの主眼は、十三歳の少年Aが殺人を犯した動機の解明に収斂される。
整った顔立ちの和枝は、モデル事務所に所属する九歳の妹と共に、“うつくしい子ども”として裕福な家庭で育てられてきた。そのような“恵まれた”環境にいる少年Aが、どうして妹と同い年の少女の命を奪い、社会を恐怖に陥れたのか?
そんな少年Aの心の闇を解き明かしていくのは、一つ上の兄──三村幹生である。
容姿端麗な弟や妹とは異なり、幹生の顔立ちは地味で頬のニキビが目立ち、学校ではジャガとあだ名で呼ばれている。植物観察が趣味で、物事を冷静に客観視できる。これらの人物設定が巧みに描写され、真相を模索する忍耐力や洞察力が説得力を帯びている。
私は本書を読み進めている途中、和枝が凶行に走った理由を幹生が探ろうとするのは、不安をかき消すためだと思っていた。
容貌に違いはあっても、幹生と和枝は一歳しか年齢が変わらず、家庭も学校も共通する環境で育ってきた。一歩間違えれば、自分も弟と同じ過ちを犯してしまうのではないか。そう不安になったのではないかと想像したのだ。
しかし、幹生は次のように考える。
「カズシはこれからもずっとぼくの弟なんだから、いくら時間をかけたってかまわない。すくなくとも自分で納得できるまで、カズシの気持ちや心の動きを調べてみよう。それが最悪のおこないでも、誰かがわかってやる必要があるのではないか。そうでなければ、犯罪をおかした人は一生ひとりぼっちになってしまう。最低の人間だって、誰かがそばに寄り添ってあげてもいいはずだ。それがぼくの弟ならなおさらじゃないか」
寄り添うために、ひとりぼっちにさせないために、罪を犯した弟の気持ちを理解したい……。ひたむきな決意に胸を締め付けられた。
和枝が事件を起こしたことで、父親と母親は離婚し、引っ越さざるを得なくなり、周囲から心無い言葉を向けられ、あらゆる環境が一変した。
十四歳の少年が背負うには、あまりに重すぎる。それでも幹生は、自らの不幸を嘆くのではなく、友人や家族に降りかかる悲しみに心を痛めながら、事件について調べていく。ページを捲るほどに、幹生を応援する気持ちが強くなる。
ここまで健気な探偵が、かつていただろうか。
作中では、少年を取り巻く多くの大人が登場する。その中でも特に重要な役割を担っているのが、童顔の新聞記者──山崎邦昭である。幹生の一人称と山崎の三人称を切り替えながら描くことで、事件の全体像が多角的に明らかになっていく。
山崎は新聞記者として被害者に寄り添い、幹生は少年Aの兄として加害者に寄り添う。そんな対立構図が浮かび上がりそうになるが、著者の思惑とはおそらく異なる。なぜなら、冒頭で引用した少年Aの兄を被害者とみなす考え方は、山崎の視点で描かれたものだからだ。
報復被害をもたらす過剰な報道に疑問を抱く山崎、被害児童の墓前に野山で見繕った花束を手向ける幹生。行動の端々に、彼らの人間味が滲み出ている。
物語の終盤。山崎と幹生は、それぞれ重大な決断を迫られる。彼らが選択するのは、置かれた立場とは相容(あいい)れないはずの結論だった。それなのに私は納得するしかなかった。決断に至るまでの過程や考え方が、二人の視点でしっかり描き切られているからだろう。
「いつか灰色の港に着く日まで、灰色の世界を力の限り漕ぎ続けよう」
幹生が物語の中盤でした決心を、読者は本を閉じる直前に改めて振り返ることになる。家族のために、少年Aになった弟のために、命を奪われた少女のために、自分にできることはないか。考え続ける中で、幹生の目に映る世界は灰色に染まってしまう。
それから幹生は、灰色の船を力の限り漕ぎ続ける。最初は、幹生一人しか乗っていなかった。けれど、苦難の航海になると分かっていながら、自らの意思で乗り込んでくる友人がいた。学級委員の少年、図書委員の少女、車椅子に乗る少年……。ただ幹生に手を差し伸べるのではなく、彼ら自身も秘密を抱えていて、時に傷つき時に笑い合いながら灰色の船を共に進めていく。
これだけ重い事件を扱っているのに、爽やかに思い悩み、無鉄砲に動き回る彼らを見ていると、その眩しさに目がくらむ。くすんだ灰色の世界でも、確かに青春の色合いが感じ取れるのだ。
丁寧な筆致で紡がれていく微(かす)かな希望に、何度も心を奪われた。
もちろん、希望だけが描かれているわけではない。少年Aの心の闇に触れた幹生は、ある人物と対峙して、灰色の世界すら失ってしまいそうになる。想像もしていなかった終着点に辿り着いた読者は、ミステリーとしての驚きと切なさを同時に味わうことになるだろう。
一連の事件を経て成長した幹生は、少年Aになった弟と対面する。そこを灰色の港とみなしてもよかったはずだ。しかし幹生は、「あの灰色の海を力の限り漕ぎ続ける」と改めて決心する。弟を海に投げ捨てるわけにはいかないのだと。幹生の心のうつくしさに、言葉を失った。
本書の単行本刊行から二十年以上が経ち、少年を取り巻く情勢は大きく変わった。何が変わり、何が変わっていないのか。何を変えなければならないのか。
令和という新たな時代を迎えた今だからこそ、少年にも、かつて少年だった大人にも、手に取っていただきたい一冊である。