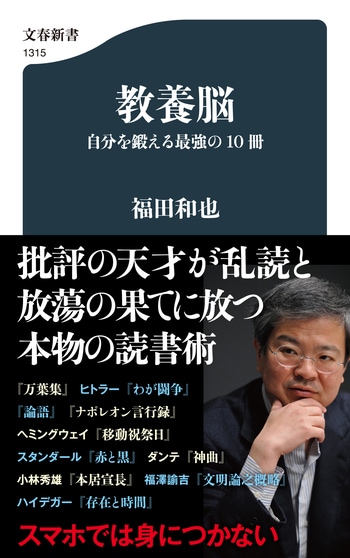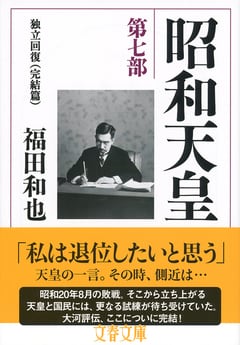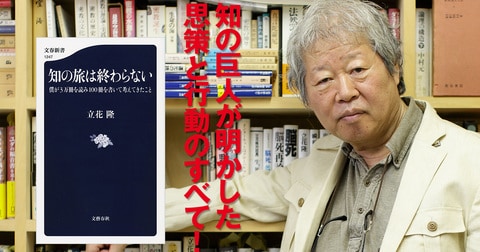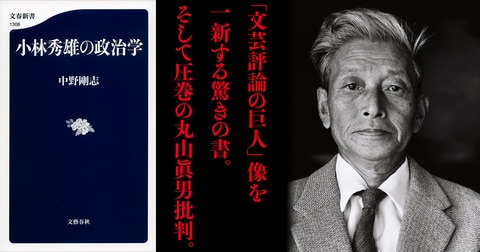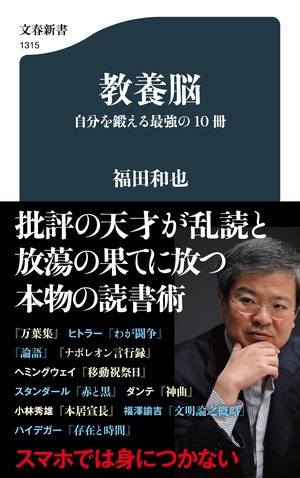
教養とは何だろう。
親に養われている子供の頃は、自分の興味の趣くままに世界を拡げていくことができるけれど、大人になって自分で生計を立てなければならなくなると、日々の仕事に追われ、自分の職業や専門的知識に心を奪われ、世界がせばまっていく。
一人一人が個々の世界に閉じこもってしまったのでは、社会は発展していかない。よりよく社会を発展させるためには、人が広く学問、芸術、宗教に触れて自分の人格を養い育てていくことが必要であり、そうした努力や成果がそもそも「教養」の意味であって、語源はラテン語の「cultura(耕す)」である。
ところが現代社会においては、その目的が置き去りにされ、「一般教養」という言葉が象徴するように、文化に関する広い知識ととらえられるようになった。
肝腎の目的を忘れてしまっては、いくら美術館を回って絵を見ても、オペラの公演を見ても、漢文の本を読んでも、教養は身につくものではない。
しかも今やインターネットの発達で、美術館やコンサート会場に行く人も少なくなった。ネットを利用すれば有名絵画のほとんどは見ることができるし、様々な音源に接することもできるからだ。
「だいたいインターネットで瞬時に世界とつながる時代に自分の世界がせばまることなんてあり得ないのだから、別に教養なんて必要ないよ」と思う人もいるだろう。
果たしてそうだろうか。
二〇二〇年の春、新型コロナウイルスの感染が拡大したとき、まず始めにとられた政策は、国境の封鎖だった。国という概念が薄らいでいた二十一世紀の世界に、くっきりとした国境線が引かれたのである。
国境線ばかりではない。同じ国の中でも分断があった。日本の場合、まず都道府県をまたぐ移動の自粛が呼びかけられ、同じ県でも、同じ市でも、同じ町でも、同じマンションでも、果ては同じ家族の間にも、境界線が現れた。
つながっていると思っていた世界は実は幻想に過ぎなかったのである。
自分以外の他人には興味がない。
これが本来の人間なのだ。
そうした人間が、個々の、地方の、国の、人種の境界を超え、つながるために必要なものが教養なのである。
「だからといって、どうして小難しい本を読まなければならないんだ。スマホで調べれば十分じゃないか」と思うかもしれない。
確かにスマホで調べれば、この本で取り上げた十冊の本の内容はすぐ分かるだろう。しかし、そこで得られるのは情報に過ぎない。しかも数分後には忘れられている。そんなものは何の役にも立ちはしない。
難しい本と長い時間をかけて対峙した結果、自分の中に生じる共感や反発は、他人に対する想像力につながる。これこそが教養の要なのだ。
新型コロナウイルスの感染拡大で世界が分断された今、人間が自分のことしか考えられなくなっている今こそ、教養は必要だ。
この本がそれについて考えるきっかけになってくれたら、うれしい。
(「まえがき」より)