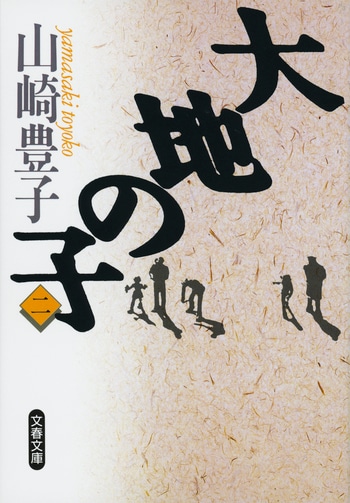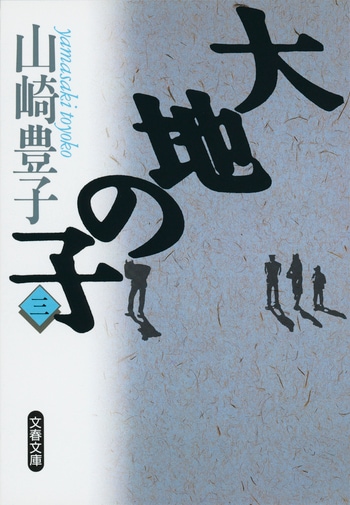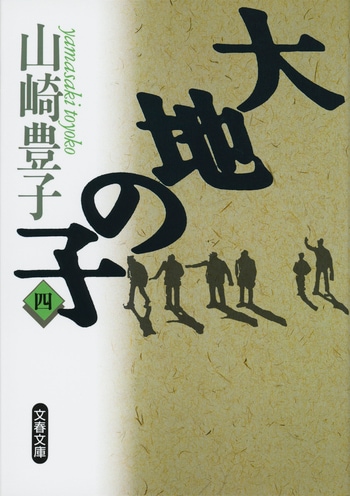山崎豊子の会心作『大地の子』が、ついに文庫化されることとなった。日本人の中国残留孤児を主人公にその迫害と苦闘の歩みをたどり、日中戦争、文化大革命、日中国交の正常化、日中共同の製鉄所建設プロジェクト、中国共産党上層部の政権抗争などといった、戦中から戦後、そして現在に至るまでの流動の波に翻弄される人々の運命をも描き出した大河小説である。
一九八七年五月号から一九九一年四月号まで「文藝春秋」に長期連載され、一九九一年の一月から四月にかけて上・中・下巻の三巻構成で文藝春秋より刊行された。連載期間だけでも丸四年間、足かけ五年にもわたり、それ以前の取材期間三年を含めると、取材から完結まで実に八年がかりの大作である。上・中・下巻が出揃った段階で、新聞の書評欄でこの問題作を取り上げる機会を得た私は、次のように結んだものである。
「残留孤児の戦後の苦難の道のりを中国の戦後状況とからませて赤裸々に描き切った作品だけに、日本人にはつらくて重いものがある。だが、作者が取材を通してそれを直視してきたのと同様に、読者もこの問題から目をそらすことはできないだろう。多くの人々に読んでもらいたい作品である」(「毎日新聞」一九九一・五・二〇)
多くの人々に読んでもらいたい――この気持ちに今も変わりはなく、今回、この解説稿執筆のために再度、全巻を読み直して、ますます強くなった。その意味で、さらに多くの人々に読んでもらう機会が増える今回の文庫化を喜んでいる一人である。
山崎豊子の取材が綿密なことと徹底していることは、これまでの発表作品を通してよく知られているところだが、この『大地の子』でも、「あとがき」にもあるように三年間の現地取材を重ねている。厳冬と炎熱の季節以外はずっと中国に滞在して、初めは“点”から取材し、それを“線”につないでいった。この“点と線”に細かなディテールを加えて“面”にしていったという。「小説は自分で取材し、自分の言葉で書かないと実感が出ない」を信条とする山崎豊子は、取材の最中と執筆時に過労で倒れるほどの打ち込みようであった。
「あとがき」にも記されているように、「政治体制、生活環境を異にする国での三年間にわたる現地取材は、ひたすら忍耐と努力を重ねるほかなかった」のだが、故胡耀邦総書記の「日本の一作家に対する理解と英断」で、それまで外国人が立ち入ることができなかった地区や場所の取材が許可された。この現地取材の苦労に関して、週刊誌の著者インタビューの中で、次のように答えている。
「取材の壁が厚いとよくいいますが、厚くて、高くて、険しいものでした。官僚主義、教条主義の壁、壁で、取材申請をし、許可が出て大勢の人に会っても、成果はなし。疲労と忍耐が万里の長城のように続きました」(「週刊現代」一九九一・六・二二)
このインタビュー記事のうち、「大勢の人に会っても、成果はなし」に関する具体的な事例を、別の雑誌インタビューに見出すことができる。ざっと、こんな具合である。
「取材するには、実に難しい国ですね。肝心なことになると官僚的で責任を逃れて誰もしゃべらない。しかたないから、別な人にさりげなく聞いて、つなぎ合わせてゆく。まさに“点と線”でした」(「SAPIO」一九九一・一一・一四)
この“点と線”が先ほど述べた“面”になっていくわけなのだが、「SAPIO」では、現地取材の三年間を振り返って、こうも述べている。
「本当にたくさんの本や資料も読みましたが、この滞在の際にじかに取材できたということが一番でしたね。(中略)その三年間が、民主の星と仰がれた胡耀邦総書記のピークと退陣までの束の間のはざまだった。これはもう私には強運だったと思いますね」
本書の「あとがき」にも、胡耀邦の取材協力の約束は「信じられないほどの僥倖(ぎょうこう)であった」と記されている。だが、こうした「強運」「僥倖」は、山崎豊子のひたすら忍耐と努力を重ねていく取材態度がもたらしたものであって、タナボタ式の「強運」「僥倖」であったわけではない。
“点と線”から“面”へといった取材に関して、こんなインタビュー記事もある。
「もう一年取材できれば、より完璧になったと思います。(中略)面にしていくときにディテールにしてももっと細かくすることができたと思うのです。取材ができていればそれがいっそうリアルにできます。そこでもう一年といったら、知り合いに欲ばりだといわれましたが」(「サンサーラ」一九九一・九)
この発言に、山崎豊子の真骨頂がうかがえる。とりわけ、「もう一年取材できれば、より完璧になった」という言には、徹底取材を常に目指す作家の執念が感じられた。「SAPIO」のインタビューの中で述べている「本当にたくさんの本や資料」云々の一端については、本書巻末に付された「参考文献」の一覧からも知ることができる。「文革関係」二十四冊、「現代中国・政治、経済」十冊、「満洲開拓団、逃避行、残留孤児」二十六冊、「評伝」十五冊、「紀行、生活」十冊、「小説」(注・中国の小説)十五冊、「鉄鋼」六冊といった内訳で、その総数は百六冊にものぼる。
これだけの参考文献を読めば、誰もが小説に仕立て上げることができるというわけでもない。こうした参考文献をこなした上で、「中国の僻地から、中南海といわれる要人が居住する地域まで、それこそ現代中国を駆け足でめぐりました」(「サンサーラ」)という精力的な行動、中国人と日本人を合わせて千人以上もの人々に会って聞き書きを取ったという驚異的な行為が加わって、そして、これはもう少しあとで触れることになる山崎豊子の内的な原動力に裏打ちされて、この大作が完成したのである。血と汗と涙の結晶と言えば安っぽい表現になってしまうのだが、山崎豊子が自分の全存在をかけて完成させ、世に問う力作である。
取材から完結まで八年の間に、山崎豊子は、製鉄のことを半年間ほどかけて勉強したり、製鉄所の建設現場に泊り込んだり、外国人未開放地区の農村にホームステイしたり、内モンゴル自治区の労働改造所で囚人たちと一緒に畑を耕したり話をしたり、戦争孤児と養父母の家を直接訪問したりと、徹底した取材・調査を敢行。こうした取材秘話の数々をドキュメント・タッチでまとめるだけで一冊の本が出来上がってしまうほどと思われるのだが、その丹念さと執念のありようは、小説作品の中にありありとうかがえる。
これだけの大作を、しかも二度も病いで倒れながらも書き上げた山崎豊子の原動力について見ていくことにしよう。あるインタビューに答えて、山崎豊子はこの原動力について語っている。
「やっぱり私は戦中派で、私たちと同じ年ごろの男性は全部学徒動員で死んでいきました。私は軍需工場で弾磨きをやり、大学を出たといっても、正規の教育は二年までしか受けていません。そのときから戦争って一体何だろうと思いました。自分は動員されて弾を磨いているけど、これが敵も味方もない、人間を殺す。そして戦争が終わってからの日本のあり方。戦争を始めた首脳部の責任だけでなくて、国民自身の戦争に対する健忘症。自分の祖国というのは一体どんな体質を持った国か。今でも私はそれを考え続けています」(「新刊ニュース」一九九一・六)
これとは別のインタビューでの言も挙げておこう。
「テーマは、戦争が個人に与える運命とでもいいましょうか。私は学生時代に軍需工場で弾研(みが)きをさせられた。これが人を殺すのかと思ったら手が震えました。戦争の非人間性も身体で感じている。『二つの祖国』も『不毛地帯』も戦争体験がもとになった。陸一心は戦争と文化大革命の二重の犠牲になったけれど、戦争さえなければこんなめにはあわなかった。戦争は個人を虐殺するのです」(「Do Book」一九九一・四)
これらの言からも分かるように、山崎豊子の原動力とは、戦争に対する激しい怒りである。『二つの祖国』は、日米開戦によって日米どちらの人間として生きるべきかという残酷な問いを突きつけられた日系二世たちの愛と祖国を模索する悲劇を描いた長篇作であり、『不毛地帯』は、シベリア収容所での強制労働に耐えて生き抜いた元大本営参謀が商社マンとしてイランの石油開発などの国際経済戦争の中で苦悩する姿を浮き彫りにした長篇作であった。これらの作品で、山崎豊子は、国際的視野を持つ重厚な社会派作家としての定評をかち取った。この『大地の子』も、『二つの祖国』『不毛地帯』に連なる系譜のものとしてある。そして、いずれの作品にも共通して存在するのは、戦争に対する怒りであり、権力の告発である。それが山崎豊子の原動力なのだ。
山崎豊子の怒りは、この『大地の子』の中の随所に見られる。もちろん、登場人物を介してである。たとえば「三十六年目の旅路」の章では、満洲開拓団の悲劇について触れ、次のようにも綴っている。
「しかも関東軍は、ソ連軍の追撃を阻(はば)むために、橋や道路を破壊して、老幼婦女子の開拓団員が南下する退路を断ち、関係者のうち、八万人もの死亡、行方不明者を出したのだった。戦争終結にあたって、国家が全力を挙げて救わねばならぬ同胞、それも最も弱者である開拓団の老幼婦女子を見殺しにしてしまったのだ。
その上、戦後三十五年目を迎えても、それらの人々の屍は大陸の荒野に野曝しのままであり、辛うじて生き残った子供たちは、戦争孤児として、日本政府から放置されたままである。開拓団員とは、当時の日本国内の人口、食糧問題の解決のために満洲へ送り出された貧しい小作農民とその家族たちで、国家の政策に騙(だま)されて、大陸の荒野に打ち捨てられた棄民(きみん)以外の何ものでもなかった。
松本耕次の眼から、憤りの涙が滴り落ちた」
長い引用になってしまったが、ここには戦争を遂行した政府、軍部への激しい怒りがある。松本耕次の「憤りの涙」は、中国の大地を駆けめぐってつらい取材を重ねてきた山崎豊子のそれでもある。
一心やその妹に、残留孤児の問題が象徴されているのだが、山崎豊子はこの“残留孤児”という言葉は使わない。その理由を「サンサーラ」のインタビューの中で、こう語っている。
「残留という言葉には、意志があるでしょう。彼らには残留しようという意志はないのです。日本政府が国家としての責任を回避したずるい名称の書き換えです。“戦争犠牲孤児”というのが正しい。そう思いませんか」
ここにも山崎豊子の怒りがうかがえる。このあとに、山崎豊子は戦争孤児に実際に会って話を聞いた取材の模様を語り、こうも述べていた。
「『大地の子』の主人公の逃避行は、何人もの孤児に会って、彼ら彼女らの体験をつなぎ合わせてつくったものですが、本当にあったことばかりです。
私は日本人として、どうすれば彼らに贖罪(しょくざい)ができるのか、そればかり考えてこの本を書いていました」
戦争への怒りは、権力機構の告発、そして贖罪意識へとつながっていくことがよく分かる。その戦争孤児の取材の模様が、一九九一年五月号の「オール讀物」に「『大地の子』取材日記」として掲載されている。一九八四年十月二十三日、二十四日、二十七日の三日分である。この取材日記から、主人公の陸一心や実父の松本耕次の人物像が創造されていったプロセスがつかめた思いがした。
この「オール讀物」五月号は、“山崎豊子と「大地の子」”特集でもあり、他にも上海の宝山製鉄所で取材中の写真や中国の作家巴金氏を上海の自宅に訪ねた折の写真などが並ぶグラビア頁に、『新・新東洋事情』で現代中国を解剖した深田祐介氏との対談“最新中国事情――「大地の子」が描いた不思議なる国――”が載っている。その対談の中で、戦争孤児の問題に触れた山崎豊子は、こう述べている。
「今日の日本の平和というのは、そういう孤児たちを戦後四十年近くも捨てておいた犠牲の上で成り立っていることを反省したいです。
日本人はみんな健忘症なんでしょうか。それとも人道主義欠如症なんでしょうか」
こうした問題も含めて、前にも記したように、本書が語りかけてくる問題には、つらくて重いものがある。それだけに、中国の大地を最後に選択する主人公の心情が胸に迫ってくるのである。
深田祐介氏との対談で、山崎豊子は『大地の子』執筆のきっかけについても語っている。山崎豊子が初めて訪中したのは一九八三年の十月、中国作家協会の招待であったという。その翌年に、中国社会科学院外国文学研究所の日本文学研究組が『華麗なる一族』の作者として招待してくれた。その折、北京人民文学出版社の幹部の人から、孫文と結婚した宋慶齢について書いてくれませんかと頼まれ、「私にはとても中国人は書けません」と答えると、「あなたは『二つの祖国』でアメリカを書いたじゃないですか。アメリカが書けて、どうして中国が書けないんですか」と突っ込まれたという。
この突っ込みに対して、「あれはアメリカじゃなくて、日系アメリカ人を書いたんですよ」と答えて、中国には戦争孤児がいるじゃないかと、パッとひらめいたともいう。あとは山崎豊子自身の言葉を紹介しておきたい。
「そうだ、戦争孤児を主人公にすれば書ける、と思ったんです。でも戦争孤児そのものについては、手記や体験記がたくさん出ている。これだけでは戦争孤児物語になる、何か大きなテーマに繋がっていかないと……。あ、そうだ、いま日中の間で宝山製鉄所のプロジェクトが進行している。この宝山を舞台に、父は日本の企業を背負い、子は党と国家を背負って相まみえる。そのテーマがひらめいたのです」
こうした「ひらめき」が、丹念な取材を経て、物語の中にどんな形で表れているかを、じっくりと感じ取っていただきたい。この「ひらめき」だけで、総枚数二千二百枚もの大作が書けたわけではないのだ。そこには山崎豊子が作家として長年培ってきた技量の全てが投入されていることが分かるだろう。
一心が妹と再会する場面や仕事で日本を訪れた時に実父の家で母親の写真を見て号泣する場面などは、単なる小説のヤマ場という以上の感動がある。丹念な取材の積み重ねがこうした場面に底力となって生きており、ドラマチックな構成を、無理なく読ませる迫力につながっている。そして、日本人の血を引きながらも中国人として育った一心と実父との関係や合作プロジェクトの現場サイドでの問題などを通して、日中それぞれの物の考え方の違いなどが明確にされていく。日本人の目から現代中国の諸相に迫った点でも、この『大地の子』は問題作として存在するのである。
山崎豊子は、毎日新聞大阪本社の学芸部にいた頃の一九五七年に処女作『暖簾』を出し、翌年には『花のれん』で第三十九回直木賞を受賞した。こうした大阪商人のど根性を描いた作品、女の生き方を追求した作品から、しだいに社会性の強いものへと変わっていった。この『大地の子』には、こうした山崎豊子の作家としての歩みの全て、そこで得た蓄積の全てがにじみ出ている。
ソ満国境近くの日本人開拓村で生まれ育った陸一心とその妹の「小日本鬼子(シアオリーペンクイツ)」としての運命の変転のさまを、山崎豊子は自在の筆で描き出して小説の趣向を整えると共に、自分の祖国は日本か中国かと思い悩む一心を通して、戦争孤児の問題などさまざまな問題を問いかけている。そして、棄民となった満洲開拓団の悲劇と国家や軍隊の冷酷さ、狂気をはらんだ文化大革命の嵐と労働改造所の実態、日中共同プロジェクトの製鉄所建設をめぐる日中双方のすれ違いや葛藤、製鉄所を政争の道具とする中国首脳部の内紛など、戦中・戦後の大きな社会問題が重なってくる。これに一心をめぐる養父陸徳志(ルートウチ)と実父松本耕次の親子愛、一心と妹との兄妹愛が太い軸として貫かれている。
いや、まだ、あった。一心の大学時代の初恋の相手で、一心が日本人であると知るや去って行った趙丹青(ツァオタンチン)との屈折した愛、内蒙古の労働改造所で知り合い、のちに妻となって一心を支えてくれた江月梅(チアンユエメイ)との純愛という恋愛心理も、物語の展開に沿って重要な要素として配されている。さらに言えば、親子愛には、一心の娘に対する愛情も含まれているのだ。
言ってみれば、この『大地の子』は、社会派小説、告発小説、国際ビジネス小説、恋愛小説、家庭小説、日中の庶民像を描いた市井小説でもあるのだ。読者はそれぞれに関心のあるジャンルからアプローチしていくうち、日中問題について考えさせられることだろう。どこからアプローチしても、その部分が光りを放ち、物語の深淵部へと誘ってくれるはずだ。この『大地の子』は、山崎豊子の集大成といってよく、どこを切り取ってみても、そこには長年蓄積した読者を飽きさせない迫力があり、山崎豊子の主張がある。まことに稀有なスケールの作家である。
『大地の子』三巻が次々と刊行された一九九一年という年は、湾岸戦争に始まってソ連邦の消滅に終わった国際情勢、バブル経済の破綻と証券・銀行界の相次ぐ不祥事に揺れ動いた国内情勢、と総括される年であった。そして、太平洋戦争勃発から五十年目にあたる年でもあった。そうした年に、戦争がもたらした日中の戦後状況を真正面から見据えたこのような大作が世に出た意義は大きい。
そして、この一九九一年という年は、山崎豊子にとっても、忘れられない年となった。『大地の子』刊行の反響ということもあるが、ほかにも、この年の一月二十九日に、「あなたはいつもテーマがいい」と励ましてくれた毎日新聞時代の先輩・井上靖が八十三歳で亡くなった。同じ年の十二月、山崎豊子は、“『白い巨塔』『不毛地帯』『大地の子』――綿密果敢な取材と豊かな構成力で多数の読者を魅了した”ことが評価されて、第三十九回菊池寛賞を受賞した。その前年の十二月、『大地の子』は、第五十二回文藝春秋読者賞を受賞しており、読者を大事にする作家としては何よりうれしい賞だと語っていた。菊池寛賞は、プロ中のプロ、職人中の職人に与えられる賞の感があり、「綿密果敢な取材と豊かな構成力」という授賞理由は、山崎豊子にぴったりの形容句である。
「あとがき」の冒頭部で、山崎豊子は「現代中国を背景にした『大地の子』のような作品は、私の生涯で二度と書けない作品である」と記した。そして、この大作を書き上げたあと、各種のインタビューの中で、必ず、こうも語っていた。「胡耀邦さんの墓前にこの本を捧げなければ、『大地の子』は完結したことになりません」(「サンサーラ」)と……。苦心して情報を集めた結果、胡耀邦のお墓は江西省の首都南昌から車で三時間も行った「共青城」(共産主義青年団の町)という墾殖場にあることが分かった。一九五五年に上海から学生を含む青年たちが入植して耕地にしたところで、胡耀邦自身も訪れて若者たちと寝泊まりしたところでもあるという。
「ここに違いないと、私と秘書の女性二人で参りました。飛行機や車を乗り継いでついにたどり着き、墓前に三巻を捧げましたが、今はもうおそらく強烈な太陽の下、そして風雨でばらばらになり、中国の大地に還っていることでしょう。私は炎天の霊前で思わず慟哭(どうこく)しました。じかにお手渡ししたかった。なぜもっと生きていてくださらなかったのかと――」(「SAPIO」)
胡耀邦の顔がレリーフになっている立派なお墓だったという。一九九一年六月二十八日のことであった。
山崎豊子が八年の間、心血を注いで書き上げた『大地の子』は、取材の道を拓いてくれた胡耀邦の墓前に捧げられ、ゆっくりと中国の大地に還ることで、完結した。
壮大な叙事詩ともいうべきこの物語は、一九六六年に起こった中国の文化大革命の嵐、造反派によるすさまじいリンチの描写に始まり、一九八五年十一月に陸一心と松本耕次の二人が船で長江下りをする場面で終わる。束の間の父子旅行となった長江下りは間もなく終わるが、二人の人生の旅はこのあとも続いていくことが暗示されてもいる。大河小説にふさわしい、見事なエンディングといえよう。そして、物語同様に、胡耀邦の墓前での献本も感動的なエンディングである。その背後には、山崎豊子の日本への、そして中国への思いがある。多くの人に読んでもらいたいと記したゆえんである。