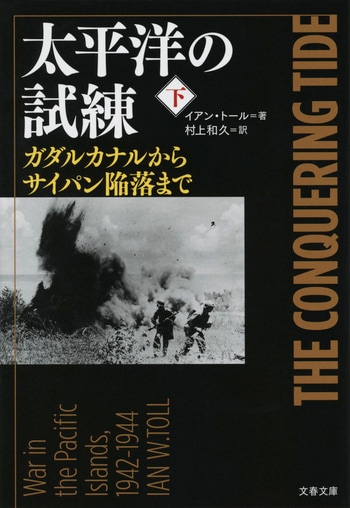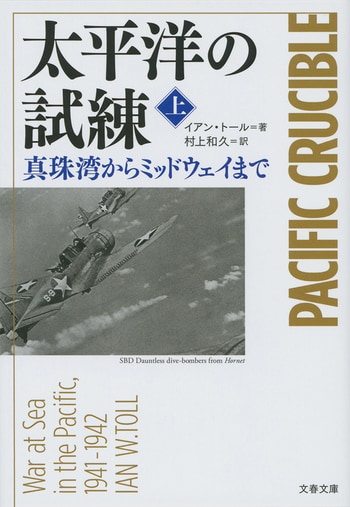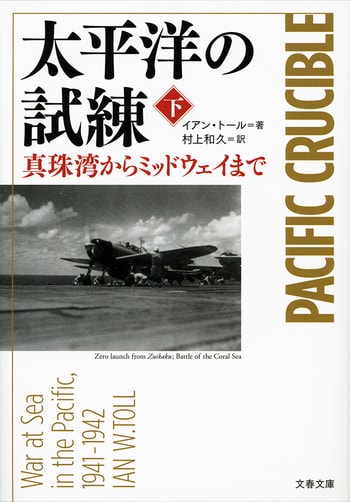ハワイの真珠湾への奇襲攻撃で幕を開けた太平洋戦争の緒戦。日本は勝利につぐ勝利を重ねた。実際、勝ちすぎるほど勝っていた。そのせいで、次段の作戦計画が間に合わないほどに。
南方の資源獲得という開戦の目的を予想より早く達成してしまった日本海軍は、アメリカ艦隊の早期撃滅を期する一方で、アメリカ本土とオーストラリアとの連絡線の分断をはかった。そこで急遽浮上したのが、それまで日米のほとんど誰もが知らなかったソロモン諸島のある島――ガダルカナルである。
真珠湾攻撃からミッドウェイ海戦までの日米両海軍の激突を、当事者の証言や最新の研究結果を基にダイナミックに描きあげ、日米の書評子から絶賛されたノンフィクション作家イアン・W・トールの『太平洋の試練 真珠湾からミッドウェイまで』。アメリカの若き海軍史家が、古典的名著から当時の戦闘報告、公刊戦史、手記、口述史など、さまざまな資料や文献を駆使して、日米の視点から太平洋戦争を重層的に描く三部作の第二部となる本書は、前作のあとを引きつぎ、太平洋戦争の転換点となったガダルカナルの戦いで幕を開ける。そして、一度は日本にかたむきかけた勝機がしだいに連合軍側に移り、ついには敗北を決定づける一九四二年八月から一九四四年七月までのおよそ二年間を描いている。
一九四二年六月のミッドウェイ海戦で空母四隻と全母艦艦載機を失い、海戦史上最大の大敗を喫した日本海軍。しかし、中部太平洋からフィリピン、ビルマにまたがる広大な日本の占領地はいまだ無傷で、海軍自慢の強力な戦艦戦隊をふくむ水上艦艇部隊や、熟練の搭乗員をそろえた航空部隊は健在であり、米英連合軍にとって依然として脅威であることに変わりはなかった。
……海戦は太平洋戦争の「バランスを変えた」が、形勢を変えてはいなかった。日本海軍は空母飛龍、蒼龍、加賀、赤城とその全艦載機を失い、三千名以上の熟練士官、下士官兵、飛行士が戦死した。たとえそうでも、日本は展開する海軍力と航空戦力の大半の分野で数的な優位をたもっていた。連合艦隊はアメリカの四隻にたいして依然として空母五隻を招集できた。……恐るべき戦艦や潜水艦、駆逐艦、兵員輸送船、あるいは飛行艇はまったく失われていなかったし、陸上を基地とする有能な中型爆撃機もそれと同様だった。……ミッドウェイ海戦は南太平洋における日本の攻勢の激しさもエネルギーもほとんど衰えさせてはいなかった。ニューブリテン島のラバウルを基地とする海軍部隊、地上部隊、そして航空部隊は南と東へ侵攻し、現地の連合軍を綱渡りの守勢に立たせていた。(第一章)
日本海軍は、第二段作戦として、アメリカ本土とオーストラリアとの連絡線の分断をもくろむ。米軍が太平洋のはるか彼方のハワイを拠点とするかぎり、その脅威は恐るるに足りない。しかし、オーストラリアを反攻の基地として、ニューギニアから島づたいにフィリピンへと北上してくれば、これは脅威たり得る。そのためには、アメリカ本土およびハワイとオーストラリアとの海上交通路を遮断して、アメリカが兵力や物資を送りこめないようにする必要があった。
その作戦の一環として、海軍はソロモン諸島の大きな島ガダルカナルに目をつけた。ここに飛行場を建設し、日本の誇る足の長い零戦や一式陸上攻撃機の飛行隊を送りこめば、オーストラリア東方の海上ルートである珊瑚海に睨みをきかすことができるからだ。
しかし、アメリカ側も考えることは同じだった。アメリカ海軍のトップであるキング提督は、太平洋で早期に反攻を開始することが重要だと考えていた。そして、その起点として、ガダルカナルに建設中の日本軍の飛行場を選んだのである。日本軍はまさかミッドウェイ海戦のわずか二カ月後にこうした反攻がはじまるとは予想しておらず、アメリカ軍の無血上陸を許してしまった。
ガダルカナル島の戦いが、最終的に日本の悲惨な敗北に終わったことはいうまでもない。アメリカ軍など恐るるに足らずという思い上がりに起因する作戦のまずさ、情報分析の軽視、物資補給計画のずさんさ、兵力の分散投入など、その敗因はビジネス書のロングセラー『失敗の本質』でも分析されている。
しかし、本書を読めば、アメリカ側もまた、物量にまかせた一方的な勝利ではなく、一時はかなり追い詰められていたことがおわかりになるだろう。
日本軍と同様、アメリカ軍側もまた物資の補給が思うにまかせず、海兵隊員たちはやせ衰えていった。戦艦金剛と榛名によるヘンダーソン飛行場の夜間砲撃では、一時、飛行可能な米軍機の数が十数機にまで落ちこんでいる。さらに、伊号潜水艦の雷撃によって、アメリカ側の空母は一時期、ホーネットただ一隻になってしまうのである。