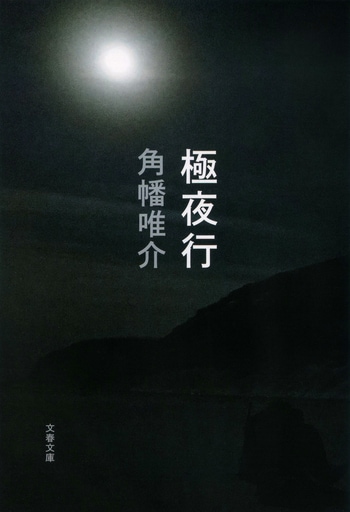長い間、人類の夢は漆黒の夜と氷の世界を制することだった。人類の最初の祖先はアフリカの熱帯雨林で生まれ、700万年間にわたって20種以上の人類が登場して新しい環境に挑んできた。人類が最初にアフリカ大陸を出たのが約200万年前、火を用いて夜を制したのが約80万年前である。しかし、雪と氷の世界は人類の行く手を阻み、シベリアに到達したのは2~3万年前に過ぎない。そして、ピアリーによる北極点到達は1909年、アムンゼンによる南極点到達は1911年と20世紀になってからのことだった。
もうひとつの極点である世界最高峰エベレストの登頂はずっと遅れ、1953年になってやっとヒラリーとテンジンによって成し遂げられた。雪と氷に加え、険しい氷壁と高山病、酸素不足を克服するのに長い時間がかかったからである。
さて、本書はこの人類の二つの夢を同時に叶えようとした冒険の記録である。極夜というのは太陽が地平線から姿を見せない漆黒の夜である。北極の極端な場所ではその状態が半年続く。月と星が唯一の明かりだが、新月ともなれば何も見えなくなる。今まで誰も、その闇の中で極地をめざした冒険家はいなかった。太陽が出なければあたりを見渡せないし、太陽熱の暖も取れない。すべてが凍り付く闇の中で、氷の割れ目に気を配りながら手探りで極点を目指すのは危険極まりない。そんなとんでもない冒険をなぜ、著者の角幡唯介は企てたのだろうか。
極夜の世界へ行けば、真の闇を体験し、本物の太陽を見られるのではないか。そう考え続けてきたと角幡は言う。古来、太陽は万物をそこにあらしめる究極の光であり、私たち人間の肉体と精神に規律と脈動を与えるダイナミックな光であった。地球上の多くの場所で、人々は太陽を神として崇め、生きる力と喜びを得てきた。ところが、科学技術によるエネルギーを手に入れた現代の人々は自然から距離を置くようになり、まともに太陽を見なくなった。太陽と同じく、月も星も、そして闇さえも喪ったと角幡は言う。
極夜の旅は、現代に残された数少ない未知に挑む冒険である。実は、エベレストを含む地球の三つの極点への到達は国の威信をかけた国際的な競争だった。日本も1910年に白瀬中尉を南極に派遣したが、アムンゼンに先を越された。その後も未踏の高峰の初登頂を目指し、各国のアルピニストが挑む時代が続いた。エベレスト登頂後もより困難な登頂ルート、単独行、無酸素登頂など、方法を変えて世界初を目指す試みが続いた。しかし、国を背負って冒険に挑む風潮はしだいに影を潜め、日本でも堀江謙一のヨットによる単独太平洋横断によって終止符を打つことになる。国ではなく、自分のための冒険が始まったのである。その中で最も輝かしい業績を上げたのは、世界初の五大陸最高峰登頂者となり、犬ぞり単独行で初めて北極点に到達した植村直己であろう。光栄にも私は植村直己冒険賞の選考委員を務めているが、その定義に「冒険とは、周到に用意された計画に基づき、不撓不屈の精神によって未知の世界を切り拓くとともに、人々に夢と希望そして勇気を与えてくれた創造的な行動」と記されている。
植村と同じく、角幡も犬ぞりで極夜に挑んだ。国を背負うことなく、自分のために未知の世界に分け入った。しかし、極点を目指した多くの冒険家と違い、角幡の目的はあくまで極夜を自分の身体で知覚し、その本質を見極めることだった。単独行で頼りになるのは犬だけ。荷物を積んだ橇を見失い、六分儀を無くし、ぐるぐるまわりを強いられ、想定外の出来事が続く。私もアフリカのジャングルでゴリラを追っていて道を見失い、ひとりで夜を明かしたことがある。その時、自分が同じ場所をぐるぐる回っていたことに気づき、唖然としたものだ。人間の方向感覚は実にあてにならないものなのだ。しかし、ジャングルは昼も夜も多様な生き物たちの生気に満ち溢れている。食べられそうなフルーツや、シロアリなどの美味な虫も見つかる。私は片時も一人でいる寂しさや不安を味わうことがなかった。しかし、テントの中に閉じこもった角幡にとって外はブリザードの吹き荒れる氷の世界だ。時折聞こえるのはオオカミの吠え声で、襲われる危険がひしひしと迫る。私は同世代の冒険家である星野道夫がテントで就寝中、ヒグマに襲われて命を落としたことを思い出した。
そんな中で角幡と犬たちとの交流は実に温かい。用足しをする角幡の肛門に犬が鼻面をつけて糞を食べだす光景は思わず笑ってしまう。ゴリラだって自分や仲間の糞を食べることがある。屋久島では数が増えて食物が不足したシカたちが、サルの後をついて歩き糞を食べている。糞を汚いと思うのは人間だけなのだ。氷原で最も困難を極めるのが食料の確保である。自分だけでなく犬にも食べさせねばならない。手持ちの食料がつきた角幡は力尽きた犬の首を絞めて殺し、その肉を食らうことさえ想像した。もはや銃で獲物を撃つしか望みはなく、キツネと間違えてオオカミを撃ちそこない、麝香牛の死骸に出くわして九死に一生を得る。犬と争って死肉をむさぼり、最終的には犬の死肉を食えば生き延びられると想像した角幡は、それが犬と人間との原始融合状態だったかもしれないと言う。後をつけてくるオオカミとの戦いはまさに原始の頃を思わせる。こうした記述を読むと、人間と犬の絆の深さにつくづく感心する。人類が氷の世界を突破できたのは犬のおかげではないかと思えてくる。
漆黒の闇の中では自分の身体を見失う。それを私はジャングルで体験した。自分の手も見えない闇の中では、足を地につけていてもまるで身体が宙に浮かんだように感じる。角幡は闇の中で、光は空間だけでなく時間領域でも力を発揮し、未来を見通す力と心の平安を与えてくれることを見出した。月の動きの自在さを女性が持つ儚さ、しとやかさに見立て幻惑されながら闇を歩く。そのとき、角幡の頭をよぎったのは本書の冒頭に登場する妻の出産シーンだったのではなかろうか。難産で絶叫する妻の出産に立ち会った彼は、肉体の内側で胎児という自然をかかえこみ、自然と融合して一体化する行為に比べれば、自身の冒険がいかにも皮相なものに見えたのだ。出産の現場で男にできることなど何もない。そう感じた角幡は、自分一人で自然に向き合える機会をひたすら求めた。そのためには人間界というシステムの外へ出ることが必要であり、極夜行はその絶好の手段だったのだ。
帰路に嵐の真っただ中で、角幡は妻の体から出てきた子供を思う。闇から出ようとしてもがいている自分はあの時の子供と同じ状態なのではないか。人間にとって光とは出生経験の再来であり、不安と恐怖からの解放であり、だからこそ希望の象徴になっているのだと。もう一つ、私は付け加えておこう。冒険とは帰還してこそ意味のある挑戦となる。システムの外に出た人間が、その体験と新しく得た視点を自ら語り継がねば、それは生きた知識とならないのだ。角幡が生還できたのは妻と子供の存在が大きかっただろうが、私たちにとっても未来につながる大きな宝であり、本書はその道標になるだろう。