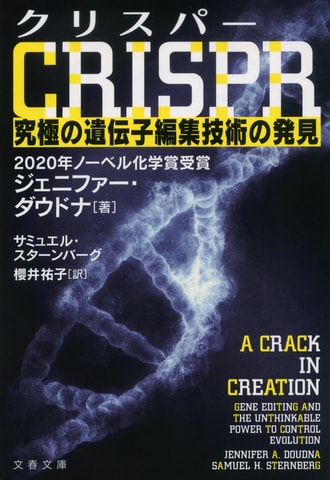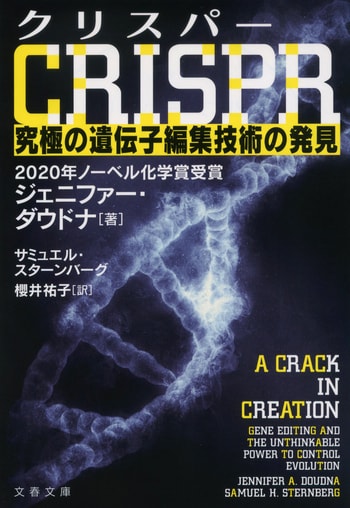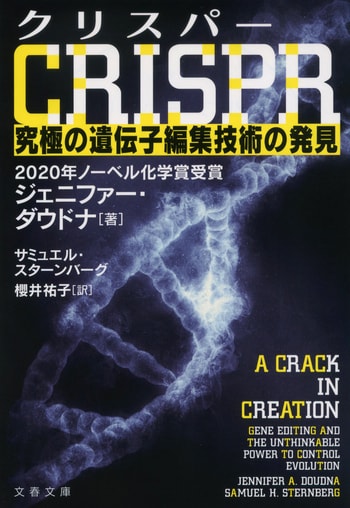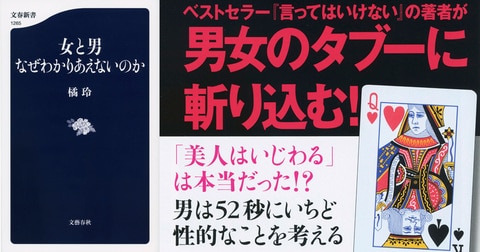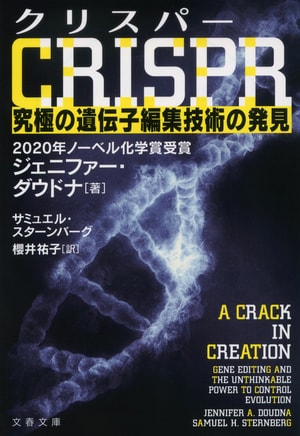
一九九七年の米SF映画『ガタカ』は、ヒトの遺伝子操作が当たり前になった近未来を舞台に、人間の自由意志の強さを描く美しい映画だ。序盤にこんなシーンがある。
自然妊娠によって生まれた主人公は、生後すぐに、三〇代前半で心臓病によって死ぬ運命にあると宣告される。両親は次の子を「普通のやり方」で得ようと決める。体外受精ののち、確実に健康に育つ受精卵を選別して子宮に戻す方法だ。主な遺伝病の可能性がなく、目や髪の色もあらかじめ指定した通りの幾つかの受精卵が候補になる。
遺伝学者は、両親に性別を選ばせると、さりげなく付け加える。「勝手ながら、早期脱毛、近視、アルコール中毒、中毒に対する脆弱性、暴力や肥満の傾向など、潜在的に有害な条件も取り除きました」。ひとたび遺伝子操作が普及すれば、「個性」にあたるような特徴や体質すらも、簡単に改変の対象になってしまうことを示す場面だ。
遺伝子操作で生まれながらに優れた知力・体力が約束された「適正者」とそうでない者が区別され、「不適正者」には職業を選ぶ権利すらない――。『ガタカ』の世界は、公開当時はまさしくフィクションだったが、二〇年以上が経った今、そうとも言い切れなくなっている。
本書の第8章でも書かれているように、二〇一五年四月、中国の研究チームが世界に先駆け、最新の遺伝子編集技術(「ゲノム編集」とも呼ばれる)によるヒト胚(受精卵)の改変を試みたという論文を発表した。用いられたのは「CRISPR-Cas9(以下CRISPR)」。生物の全遺伝情報(ゲノム)は、細胞一つひとつの核に収められた二重らせん構造のDNAに保存されている。CRISPRは、DNAにA、T、C、Gの四種類の塩基で書かれたゲノムを、狙い通りに書き換えることができる魔法のようなツールだ。
やや皮肉なことだが、物議を醸した中国のチームの報告は、CRISPRの名が全世界に知れわたり、関心を集める機会を作った。取材した私は、この技術がすでに、生命科学の広範な分野に普及しているのを目の当たりにした。遺伝子編集技術はそれまでにもあったが、使い勝手が悪く、高額だった。「第三世代」の編集技術として登場したCRISPRは、はるかに簡単かつ低コストで、瞬く間に大半の動植物の細胞に使えるようになった。
動物の受精卵を直接、編集できるのも、CRISPRの大きな利点だ。たとえば新しい遺伝子改変マウスを作るには、まず、ガイドRNAとCas9のセットを受精卵と一緒に電極付きのシャーレに入れ、装置のボタンを押して電気パルスをかければいい。すると、細胞膜に空いた微小な穴からゲノム編集のセットが受精卵に入り、目的の遺伝子が改変される。改変済みの受精卵を偽妊娠状態にしたメスのマウスの子宮に移植すれば、二〇日後には改変マウスが誕生する。ES細胞(胚性幹細胞)を用いた従来の方法では数年かかっていたことが、一カ月足らずの短期間で実現できるのだ。
ある研究者の言葉を借りれば、CRISPRは、遺伝子改変を伴う研究の「裾野を広げて」もいた。つまり、旧来の遺伝子組み換え技術に縁のなかった研究者までもが、CRISPRの登場を機に、こぞって生物のゲノムを「編集」し始めていたのだ。
本書は、そのCRISPRをエマニュエル・シャルパンティエ博士らとともに開発し、シャルパンティエとともに二〇二〇年のノーベル化学賞に輝いた科学者、ジェニファー・ダウドナ博士による二部構成の手記である。第一部では、一見、無関係に思える細菌の基礎研究が、画期的な遺伝子編集方法に結びつくまでの物語が生き生きと描かれる。
そもそもCRISPRは、細菌のDNA配列にみられる奇妙な繰り返し配列を指す。数十文字の全く同じ配列(リピート)が繰り返し現れ、その間に同程度の長さのそれぞれ異なる配列(スペーサー)が挟まれた構造だ。しかもリピート配列は、前から読んでも後ろから読んでも同じ、回文のように見えるというから面白い。本書には原注にその論文が言及されているだけ(第2章の(13)文献)だが、一九八七年に大腸菌のDNA中で初めてCRISPR配列を発見したのは、日本の石野良純博士(現・九州大学教授)らだった。
一方、ダウドナは元々、細胞内で働くRNAについて研究していた。RNAは、細胞の中でタンパク質が作られるとき、必要な情報をDNAからコピーして、核の外側に伝える分子だ。CRISPR配列は、細菌の体の中でどんな役割を担っているのか。シャルパンティエら二人の女性科学者との幸運な出会いが、ダウドナをこの謎解きに引き込む。
細菌が外部から侵入してくるウイルスを撃退する仕組みに関わっているのではないか――という最新の仮説を証明するため、ダウドナは、DNA上で必ずCRISPR配列の近くにあるcasという遺伝子のグループに着目し、研究をスタートさせた。やがて全体像が姿を見せ始める。細菌は、かつて感染したウイルスのDNAを取り込んでスペーサー配列に記憶する。再び侵入されたときは、スペーサー配列をコピーしたRNAがガイド役となってCasタンパク質を導き、ウイルスのDNAを破壊するという仕組みだ。
二〇一一年、当時スウェーデンの大学に所属していたシャルパンティエと、米国西海岸に研究室を構えるダウドナとの、スカイプや電子メールを駆使した共同研究が始まる。わずか一年ほどで、パズルの最後のピース、さまざまなCasタンパク質の中で最も重要とみられていたCas9の役割が突き止められる。Cas9は、ガイドRNAの指示通りにウイルスのDNAを正確に素早く切断する、細菌にとって文字通りの「最終兵器」だった。二〇一二年六月に発表した歴史に残る論文で、ダウドナたちは、この仕組みが革新的な遺伝子編集技術としても利用できることを示した。ガイド役のRNAを思い通りに設計し、ハサミ役のCas9タンパク質にDNAの目的の場所を切らせるのだ。CRISPRの誕生である。
ダウドナが、自然への好奇心を原動力に、研究室のメンバーや共同研究者とともに緻密な推理と実験を積み重ね、一歩ずつ真理に近づいていく様子はスリリングで感動的だ。単細胞である細菌が、ウイルスから身を守る戦略の巧みさ、複雑さにも驚かされる。
現代科学が具体的にどのように営まれているかが垣間見えるのも、本書の面白さの一つだろう。たとえば、ダウドナは魅力的な共同研究の提案を受けるたびに、身を乗り出しつつも、頭の中では冷静に研究室にとっての利益と負担をてんびんにかけ、プロジェクトを任せられる人材がいるかを思案する。ダウドナ自身も述べているように、科学の原動力は冒険心と好奇心といえども、研究室を維持しながら着実に成果を出すには、理想と現実の間でうまくバランスをとる経営センスが欠かせないことがよく分かる。
続く第二部では、CRISPRの利用の広がりと研究の劇的な進展が紹介される。農作物や家畜の改良から医療、さらには絶滅動物の復活まで、研究の幅広さには圧倒されるばかりだが、実はもっともそのスピードと広がりに動揺したのは、技術を開発したダウドナ自身だった。
CRISPRに限らず、すべての科学技術は善悪両方の目的に利用されうる。量子物理学と核兵器の関係が最たる例だ。デュアルユースと呼ばれるこの二面性は、二〇一六年九月からの一年間、米国に留学していた私の研究テーマの一つだった。
CRISPRで想定される深刻な悪用の一つは、新たな生物兵器の開発への利用だろう。旧ソ連が冷戦時代、核兵器と平行して極秘に、生物兵器を開発・生産していた事実は有名だ。長らく開発研究に携わり、ソ連崩壊後に米国に亡命したある研究者はインタビューに応じ、細菌に有害な物質を作らせるため新たなDNA配列を組み込んだり、二つの病原体を合体させたりして新規の兵器を作ろうとしていたことを話してくれた。そうした研究は、もしCRISPRを使えばずっと容易にできるに違いない。第5章に登場する遺伝子ドライブも、生物兵器への転用の可能性が懸念されている。
ダウドナが本書の中で最も心配するのは、リスクや適切さについての議論がなされないうちに、ヒトの生殖細胞が改変されることだ。精子や卵子、受精卵の遺伝子を書き換えることは、その生殖細胞から生まれてくる子どもだけでなく、その子孫にまで影響を及ぼす。未来の人間のDNAを永久的に書き換える準備が、私たちにできているのだろうか。それは、一歩間違えれば、『ガタカ』で描かれたような、より「優れた」人間を作るための操作、さらにはナチスドイツが信奉し、ユダヤ人や同性愛者・精神疾患患者・身体障害者らのホロコーストを引き起こした優生学の復活につながりかねない。さらに、不用意な改変は、この技術に対する社会の信頼を一気に失わせ、病気の新しい治療への道すらも閉ざしてしまうだろう。
予測しがたい濫用や悪用の恐れにさいなまれるダウドナが、不気味なブタの顔をしたヒトラーに協力を求められる悪夢を見る場面は暗示的だ。紙とペンを用意して待ち構えていたヒトラーは言う。「君が開発したすばらしい技術の利用法や意義をぜひとも知りたいのだよ」。
こうした負の可能性に気付いたダウドナは、自ら考察を深めるとともに、他の科学者や生命倫理の専門家と提言を発表し、一般の市民とも積極的に対話を重ねていく。それまでの研究室に閉じこもる人生から、社会に飛び出し、発言する科学者へと変貌を遂げていく姿は、第二部の白眉だ。
細菌が長い時間をかけて編み出してきた複雑で多様な免疫の仕組みが、やはり四十億年の進化の歴史を経て紡がれてきた地球上のあらゆる生命の設計図を、いとも簡単に書き換える手段に生まれ変わった。
ダウドナは、この技術の革新性を一九一〇年代から始まった量子物理学の切り開いた地平と対比し、核兵器開発に携わった科学者が何を語っていたかに注目する。自らが勤めるカリフォルニア大学バークレー校の教授でもあったロバート・オッペンハイマーは、マンハッタン計画を主導したが、原爆の投下後、「科学者は罪を知った」という悔恨の言葉を残した。戦後、より破壊力の大きい水爆の開発への意見を議会で求められ、次のように反対したという。
「(科学者は)技術的に甘美なものを見つけたら、まずやってみる、それをどう使うかなどということは、成功した後の議論だ、と考えるものです。原爆では、まさにそうでした。原爆の製造自体に反対した人は誰もいなかったように思います」
本書の単行本が出版されたのは二〇一七年だが、翌年の夏、来日したダウドナにインタビューする機会に恵まれた。ダウドナは、最近はヒトラーの悪夢はもう見ない、と明かす一方、「社会の反発を引き起こすような応用」への強い懸念を口にし、その例の一つとして、両親が好む外見や能力を持つようにゲノム編集された「デザイナーベビー」の誕生を挙げた。
残念ながらこの年の一一月、彼女の懸念は現実となる。中国の南方科技大学の賀建奎副教授(当時)が、CRISPRを使って遺伝子改変したヒト受精卵から双子の女児を誕生させたことが明らかになったのだ。双子の父親はエイズウイルス(HIV)の感染者で、遺伝子改変の目的はHIVにかかりにくくすることだった。
安全性が確保されず、もちろん国際的な合意もない中での暴挙は、世界に衝撃を与えた。
CRISPRがいかに精度がよいとは言っても、技術はまだ未成熟で、目的外の遺伝子が誤って改変される「オフターゲット変異」などのリスクがある。そもそも、父親がHIV陽性の際、子への感染を防ぐ方法はすでにある。医学的な妥当性がないため、ある種のデザイナーベビーをつくる試みとも指摘される。さらには前述のように、生まれた子だけではなく、その子の子孫にも影響を及ぼす。
賀は報道直後、香港で開かれた国際会議で、自ら双子の誕生を発表した。皮肉なことにその会議は、ダウドナも発起人の一人として準備に携わり、本書でも初回の開催の経緯が紹介されている「ヒト遺伝子編集国際サミット」の二回目だった。生殖細胞の遺伝子改変のリスクを洗い出し、その是非を議論するための場が、誰も望まない形での「ゲノム編集ベビーの誕生」を目撃する場に変わってしまったのだ。会場にいたダウドナの心境は察するに余りある。
「まずやってみて」からの議論では遅すぎることを、広島・長崎の惨禍は示した。同じ轍を踏まないために、そしてCRISPRを「善のツール」とするために、何ができるのか。ダウドナは苦悩しながらも行動し、この技術を誰よりもよく知る科学者として、わかりやすい言葉で伝える本書を綴った。その裏にあるのは、技術の使い道を決めるのは、社会であり、一般市民であるという揺るぎない信念だ。
ゲノム編集ベビーの誕生に見るように、現実の進展はあまりに速い。遺伝子編集技術の拙速な応用を防ぎ、技術をよりよく使うためのルール作りを急がなければ、医療に限らないさまざまな応用分野で、第二、第三の賀が必ず現れるだろう。私たちが議論を始めるための最適なガイドブックとしても、本書の重要性はますます高まっている。