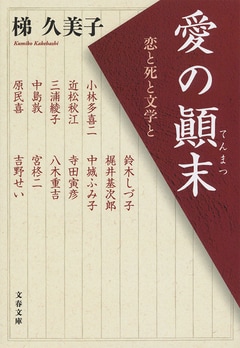二〇一八年に刊行された本書『選べなかった命』は、翌二〇一九年に、第五十回大宅壮一ノンフィクション賞と第十八回新潮ドキュメント賞を受賞した。両方で選考委員をつとめた私は、どちらの選考会でもこの作品を強く推した。
読むに値するノンフィクション作品の条件は、「取材が尽くされていること」「構成や文章などの表現がすぐれていること」「(なぜいま書かれなければならないのかという)現代性があること」だと私は考えている。これに加え、優れたノンフィクションには、その作品だけが持つ圧倒的な「何か」がある。
本書におけるその「何か」とは、「問い」だ。その問いの大きさと切実さに、一人の読者として、また同じノンフィクションの書き手として、打たれるものがあった。
本書の軸となっているのは、二〇一三年に始まった、ある裁判のゆくえである。
四十一歳の母親が、胎児の染色体異常を調べる羊水検査を受けた。ダウン症という結果が出たが、医師は誤って異常なしと伝えてしまう。母親が出産した男児はダウン症による肺化膿症や敗血症のため、壮絶な闘病をへて、生後三か月半で亡くなった。
両親は医師と医院に対して裁判を起こす。この裁判が注目を集め、その経緯が報道されることになったのは、両親が、自分たち夫婦に対する損害賠償だけではなく、子に対する賠償も請求したからだ。
両親への賠償には、もし誤診がなかったら、胎児を中絶できたという前提がある。産むか産まないかを自己決定する機会を奪われたことへの賠償を求めるこうした訴訟を、ロングフルバース訴訟という。ロングフル=wrongful。悪い、不当な、不法な、といった意味をもつ語だ。
一方、子への賠償を求める根拠となるのは「生まれてこない権利」があるという考え方だ。子自身を主体とし、誤診がなければ苦痛に満ちた自分の生は回避できたとする訴えである。これをロングフルライフ訴訟という。本書で著者が追いかけた訴訟は、ロングフルバース訴訟であるとともに、日本初のロングフルライフ訴訟だった。
ロングフルバースとロングフルライフ。このふたつの概念も、実際にそれをもとにした訴訟が行われていることも、私は本書を読むまで知らなかった。おそらく読者の多くもそうだろう。男児の両親もまたそれを知らなかったという。亡くなった子への賠償は求めたが、その提訴が「生まれてきたこと自体が損害である」という考え方にもとづくものになるとは思っていなかったのだ。
母親は、苦痛に耐えるだけの短い生を終えた子に対して、医師に謝ってもらいたかっただけだと話す。著者の取材によって明らかにされる、誤診から出産、息子の死に至る経緯を見れば、これは正直な思いだろう。だがそれは司法の場では通用せず、障害は不幸なのか、障害のある子は中絶されても仕方がないのか、という批判にさらされることになる。
この訴訟を追いかけていくうちに、著者の中には多くの疑問が生まれ、それは「命」と「選択」についての大きな問いへと育っていく。
五年間にわたって、これでもかというほど取材を重ねながら、「結末のある物語」として事実を組み立てることを著者は拒む。語られるエピソードを美談にすることもない。本稿の冒頭に書いたように、ただひたすら、本質的な問いを問うために、この本は書かれているのだ。