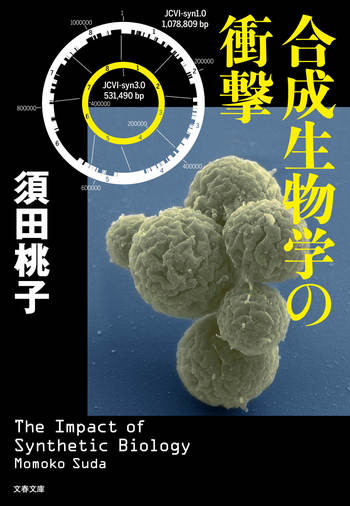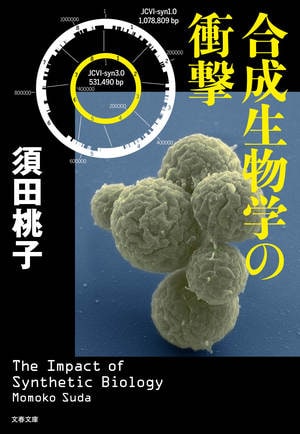
「ペイル・ブルー・ドット」という名で知られる一枚の写真がある。暗闇に数本の光の筋のようなものがあり、その中に「青白い点」がぽつんと写っている。
その薄暗い小さな点は、地球だ。今は太陽圏の外へ出て星間空間を飛行しているNASAの宇宙探査機「ボイジャー1号」が、一九九〇年に太陽系の縁から我々のほうを振り返るようにして撮影した。その距離、約六〇億キロメートル。現在のところ、もっとも遠い場所から撮られた地球のポートレートである。
撮影を提案したのは、NASAの惑星探査計画において指導的役割を果たした惑星科学者、カール・セーガン(一九三四~一九九六)。彼はこの写真を引き合いに出しながら、天文学は人に謙虚さを教える学問である、と説いた。広大な宇宙の片隅に浮かぶこのちっぽけな点の上で、人類は自分たちを何か特別な存在だと思い込み、際限のない欲望に駆られて争いを続けてきたのだ、と。
天文学が謙虚さを学ばせる学問ならば、生命科学は人間の傲慢さについて考えさせる学問かもしれない。本書はその最良のテキストであると同時に、素晴らしくスリリングな読み物でもあるという、稀有な科学ノンフィクションである。
タイトルにある「衝撃」の二文字は、決して大袈裟ではない。「合成生物学」という研究分野は、遺伝子の工学的な改変だけにとどまらず、人間が一から合成したゲノムを持つ新しい生命体を作り出すという驚くべき試みまでをもすでに成功させているのだ。その「ミニマル・セル」なる生命体がチューブの中で増殖していくさまに、著者の須田桃子氏は「驚嘆と同時に、かすかな戦慄も覚えずにはいられない」と述べている。私を含む読者の多くが本作を通じて抱く感想は、この言葉に尽きるのではないだろうか。
本書では、「ミニマル・セル」の誕生を一応のゴールに据え、一九九〇年代初頭から加速度的に進展してきた合成生物学の成果を追っている。舞台はおもにアメリカだ。須田氏は客員研究員としてノースカロライナ州立大学に約一年間滞在し、その最前線を取材したという。この分野の立役者やキーパーソンへのインタビューがふんだんに盛り込まれていることが、本作を緊迫感にあふれたルポルタージュにしているのだろう。彼らの生の声、そこに須田氏が読み取る感情の数々は、科学者のもつ「人間くささ」を見事に浮き彫りにしている。
大宅壮一ノンフィクション賞などを受賞した『捏造の科学者』を拝読したときも感じたことだが、的確で淀みない科学的記述に、生々しく臨場感にあふれた取材時の描写が良質なサスペンスのように織り混ざり、ページをめくる手を止めさせない。読者は知らぬ間に研究の「現場」へといざなわれているのだ。科学が人間の営みであることをこれほど強く再認識させてくれる書き手は、須田桃子氏をおいて他にないと思う。
さて、そろそろ中身に踏み入っていこう。まず押さえておかなければならないのは、合成生物学の研究者たちに通底する(であろう)精神だ。それを象徴するスローガンが、作中で何度か引かれている。「自分で作れないものを、私は理解していない」。二〇世紀を代表する物理学者の一人、リチャード・ファインマンの言葉である。つまり、彼らの目的はあくまで「生命を理解する」ことであって、「生命を作り出す」ことはその手段に過ぎないというわけだ。