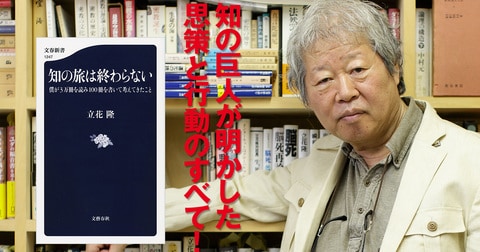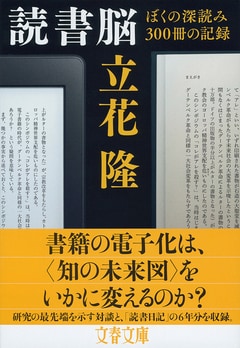本書は、故・立花隆氏が、2010年6月に文藝春秋で立花ゼミ生に向けて行った講義録である。
立花ゼミは、東京大学教養学部(1~2年生)の「全学自由研究ゼミナール~調べて書く」として、1996年冬学期に始まった。
有名・無名に限らず様々な人物に、20歳の頃の話を聞いてまとめることがこのゼミのテーマとなった。97年の駒場祭までに計4冊の小冊子を制作、単行本『二十歳のころ』として新潮社からも出版された。教養学部でのゼミは97年度で終了したが、その後も自主ゼミとして継続し、2005年に復活、ウェブサイト「SCI(サイ)」を立ち上げた。ウェブ上に影響力のあるサイエンスメディアを作ることが第2期立花ゼミの目的だった。このゼミは、06年冬学期まで続いた。
そして、07年夏学期以降に始まったのが、第3期立花ゼミだ。コンテンツを科学技術に限らないこととし、サイト名を「KEN BUN DEN(見聞伝)」と変えて再出発した。
「調べて書く、発信する」というテーマは一貫して変わらなかった。
立花さんから、ゼミ生と一緒に本を作らないか、と提案があったのは、10年の春だった。ゼミ生に「調べて書く、発信する」すべてを本作りの現場で経験させたいというものだった。要するに、取材、執筆、編集までを学生にやらせるということ。これが、編集者の私にとって、楽な仕事なのか、大変な仕事になるのか、この時点ではわからなかったが、当時すでに立花さんと別の書籍を作っているところだったので、2冊同時に立花さんの本の編集をすることは難しい、とだけはわかっていた。
そこで、学生たちと会うことになった。そのとき、私の気持ちは決まっていた。私は監督の立場をとり、彼らに編集を経験してもらおうと。
書籍の構成は、第1章はゼミ生が興味のある人物を訪ねて、20歳の頃の話を聞くインタビュー集、第2章は本書に再録した講義録、第3章はゼミ生による手記である。この構成もゼミ生が考えたものだ。中でも第2章が重要なパートになることは学生たちも心していた。立花さんがその年3月に東京大学を退官しており、それならば「最終講義」をしてもらい、文献として残したいという気持ちがみんなの中にあったのだ。
講義は文藝春秋の大きなホールで、午後3時に始まった。事前に講義の内容を教えて欲しいと言ってあったが、立花さんが教えてくれるはずもなかった。たくさんの資料を抱えて登壇した立花さんだが、「今日話す内容を書いたメモを事務所に忘れてきた。今、取りに行ってもらっている」と言って、雑談からスタートした。
いざ本編が始まると、話は、死、マラルメ、自身の20歳の頃、物理、宗教、スーパーコンピュータ、ヴィーコ、デカルト、世界史、地理、社会と目まぐるしく変わっていく。しかしそれは全て1本の糸でつながっていて、我々はその糸の行きつく先を知らないまま心身が運ばれていくようだった。
終わったときには、午後9時を回っていた。誰もそんなに長くなるとは思っていなかった。おそらく立花さんも。
学生たちがこの6時間で得た刺激は計り知れない。彼らはたくさんの扉を一気に目の前にし、知識欲に駆り立てられ、これからどの扉を開けていこうかと身震いしていたに違いない。
しかし、講義を終え、彼らを待っていたのは、この講義録の編集作業だった。理系の学生は理系のパートを、文系の学生は文系のパートを担当。文字に起こしてから、学生にもわかりやすくまとめ、できたものから立花さんに提出。立花さんは手書きで大幅加筆をし、また学生がタイプする。それを何度も繰り返し、出来上がった原稿には、最初の講義録は跡形もなかった。
注釈は、学生による力作で、これが、本書を一層読みやすくしてくれる。
『二十歳の君へ』として1冊になったあと立花さんは、第2章の講義だけでも十分本にできる内容だと言って、満足げだった。それから、『二十歳の君へ』が書店で入手しにくくなった後も、何度もそう言われた。存命中にかなわなかったのが心残りだが、きっと空の上で喜んでくれているはずだ。
そして、70歳の師が、20歳の徒に残したかったここにある一字一句は、いつの日の若者にも必要なことばかりだ。
知の旅の入り口にようこそ。
(「はじめに」より)